| 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / NOVEL / HOME |
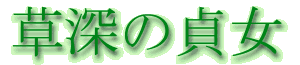 -8- 舌を絡ませながら、俺たちは草むらの上に横たわった。幾らも離れていないところにセツと晴子が倒れているのに、そんなことはちっとも気にならなかった。「旺、旺」 俺が呼んでいるのは従兄弟なのか、それとも庄右衛門なのか。 余裕のない俺をなだめるように、旺はしがみつく俺の背を優しく撫でながら、浴衣を引き剥がして行く。 広げたその上に寝かされて、濡れた下草の感触がじっとりと背中に伝わってきた。 そうして、初めて旺がちゃんとした洋服姿だということに気づく。風呂のあと、同じような浴衣を着ていたはずだが、わざわざ替えてきたらしい。 「旺……」 俺はそのシャツを握りしめる。 「あの夜も、こんな風だった」 「あの夜?」 「最後の夜だよ……。庄右衛門との、最後のよる……」 影のような木々の上に丸く覗く空は、まだ少し明るかった。鼠色の空に白い星が幾つも浮かんでいる。 土と草と水の匂い。懐かしさがどっと押し寄せてきた。こうして、何度も抱き合った。岡の家に見張られていた時、小さな弟が伝言を伝えに来ると、夜半に人目を盗んで山を登った。 庄右衛門が好きだった。請われるままに於賀まで来た。東京へ行くという話にも恨みは覚えなかった。 結局は家の命令に逆らえる人ではないこともわかっていたのだ。 目の端を、蛍が飛ぶ。今はもういない筈の、淡い光……。 「あ……」 胸の上を滑っていく旺の長い指が突起を引っかけていく。 「痛い……」 「何が?」 上から優しく聞かれる。 「胸が……」 こんな風に男を待って乳首が痛くなるものだなんて、俺はちっとも知らなかった。 旺は帯を残したまま、俺をすっかり裸にしてしまった。 そこでちょっと上体を起こし、無防備な俺を見下ろしてくる。 「旺……?」 俺は不安になって名前を呼んだ。 「大丈夫、今さら後には引けないよ。俺も泰ちゃんも」 ただちょっと、と旺は独り言のように呟いた。 ――ただ、後で泰ちゃんが恨まないでくれるといいなと思ったんだ……。 俺は恨んだりしないよ、旺。 旺がどこまで理解しているのかはわからないけれど、半ば明野に乗っ取られながら、それでも自分の心の部分はちゃんと残っていた。 旺が俺を助けようとしてくれてることはわかっていたし、本当に気づかってくれる気持ちは伝わってきた。 俺が自身の熱を持て余して体をくねらせても、旺の顔に軽蔑や侮りに近いものは浮かばなかった。薄暗がりの中でも、不思議と旺の顔はよく見えた。 旺は屈み込んで俺の腕に唇を滑らせた。そして胸に。まるで本当の恋人を相手にしているかのようだった。 俺はもしかしたらいるかもしれないその女――旺の本当の恋人――のことを考えながら、ただ息を荒らげていた。 旺はきっと、顔だけでなく、性格も庄右衛門に似ているのだろう。 庄右衛門はかつて俺が考えていた様な、要領のいい女たらしとは似ても似つかなかった。 優しく、気が弱い男だった。けれど、その分他人の痛みがわかる人で、そこにたまらなく魅かれてしまった……。 吐月楼でも、彼に思いを寄せていたのは自分だけではなかった。 きっと、妻になる人もこの男を愛するだろう。東京へ行っても、他の沢山の女たちがこの人を好きになるだろう。 待っているとは言えなかった。男を困らせるだけだから。今宵で別れなのだ。自分はもうこの夜を最後にこの人を思い切らなくてはいけない……。 ここへ置いていこう。あたしの気持ちをこの沼に沈めていこう。 ただひたすらに好きな男を求めることしか知らなかった明野という女は、今宵を限りに冷たい水底に眠らせてしまおう。 凍りついていた記憶が一気に解け出したように、胸の奥にぽつりと開いた針の先ほどの穴から、次々に溢れてくる。俺は切なくて、流れた涙が耳に溜まっていった。 「つ……」 肩に痛みが走る。 旺の歯が白く覗き、奴のやったことに気づいた。他の男のことを考えていた俺を咎めるように、旺の眉は顰められていた。 俺が考えていたのは、お前のことなのに。そう、たぶん……。 「泰ちゃん……」 囁きながら、そっと俺のものを握りしめてくる。「あき、旺……」 右手で扱きながら、左手は足の付け根から、腰の辺りを揉むようにさすってくる。 「あ、ああっ、旺、旺……」 俺は堪らなくなって、無理な姿勢で起き上がると、奴の腕の間からズボンのファスナーに手を伸ばそうとした。 「泰ちゃん」 少し困ったように俺の名を呼び、愛撫を続けながら腰を引く。 でも一瞬触れた時にわかってしまった。旺の熱さ。 「泰ちゃん駄目だ、無理だよ、まだ……」 「駄目じゃない、もういいから……っ」 俺がイっても明野は満足しない。今、彼女の望みは俺の望みだった。一刻も早く取り戻したいのだ、男を、自分の中で。 俺は脚を開いて旺の体を挟み込んだ。躊躇する奴の腰を引き寄せ、ファスナーを下ろし、下着の中からそれを取り出した。そして頼む。 「早く解放してくれよ、明野を……俺を」 旺は唇を噛み、そして僅かに頷いた。 体を裏返されそうになると、首を振って拒む。顔が見えなくなるのは嫌だった。 膝の下に手があてがわれ、少し持ち上げられる。腿に当たって滑っていくものが何かに気づいても、羞恥心は感じなかった。必要なものだ。俺の欲しいものだ。 「つ…う……」 覚悟を決めていたはずなのに、俺の体は容易に開かなかった。助けるものは何もないし、二人とも慣れていないから当然なのかもしれない。 気持ちばかり焦って、体がちっとも思うようにならない。俺は声を上げて泣きたくなってしまった。 「旺、旺っ」 奴の髪をもどかしげに引っ張る。 「なんとか、なんとかして……」 「うん……」 旺は軽く顔を振って汗を飛び散らすと、俺の耳に唇を押しつけ、そして囁いた。女の名を。 「あけの……」 そういえば、こうなってから、旺はまだ一度もその名を口にしていなかった。 呪文のように力のこもった言葉だった。 俺は、あっという間に熱い感情の奔流の中に投げ込まれた。 愛しい男に呼ばれた女は、俺を押し退けて表に出て来た。もう俺にはしゃべることも手足を動かすこともできず、ただ五感だけは敏感なほどはっきりしていて、旺の声を聞き、その匂いを嗅ぎ、重さを感じながら顔を見上げていた。 明野は俺の想像もつかないような体の使い方を知っていた。自分が雄の体だということも、大した障害にはならないようだった。 気づくと、俺は揺すられながら声を上げていた。 「泰ちゃん……」 旺はかすれた声で俺の名を呼んだが、俺は奴の名を呼び返してやることはできなかった。 旺の肉が、俺の体の内側を擦り上げる。その快感に目眩がする。この悦びを恋しがった明野の気持ちがよくわかった。 手放して、どんなに後悔したか。 互いの息遣いがどんどん早くなっていく。 旺の動きが余裕のないものになり、同時に湿った草の匂いが俺を圧倒した。 自分がイったかどうかはわからなかった。ただ、相手の体を強く抱きしめ、その射精を体の奥に感じながら、俺は最後の涙を流していた。 この先俺は、これほど愛しい相手と抱き合えることは、もうないのかもしれない……。 於賀の月、幻のホタル、きらめく草の露と水面。全ての光が流星雨のように俺たちの上へ降り注いだ。 闇の中で明野がこちらを向いていた。 ほんの僅か、左目が外を向いている。 「馬鹿だよ」 近寄ることもできず、俺は言った。 「行かないでくれって言えなかったんだろ。待ってるとも言えなかった」 明野の長い髪が僅かに揺れた。 「黙ってついて行きゃ、良かったんだ。それでもあの男ならなんとかなったよ」 明野の姿がすーっと消えていく。 俺は、本当に、彼女が好きだった。 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 「……一番線の列車は十二時二十四分の発車となります。ご乗車のお客さまはお急ぎくださいますよう……」 「あ、ほら、もう乗らないと」 俺はぺちゃくちゃと喋り続ける晴子をやっとのことで遮った。 「でもでも、セツ婆さんが無事でよかったでしょう? こっちの病院にいるのよ。退院はまだ無理みたいだけど、娘さんが戻ってきて面倒見てるって。それにしても於賀で強盗なんてねぇ!」 「晴子、ここんとこその話しかしないな」 「だってだってぇ、あたしのお手柄なのよっ。知らない男に脅されて連れて行かれるのを見て、村の人を呼びに行ったんだから! 犯人は山越えて逃げちゃったらしいけど、セツ婆さんはホタル池のとこで見つかったの……」 「もう百回くらい聞いたよ」 俺はうんざりして言った。 ちなみに晴子をおぶって山を降りたのは旺だ。誰かを担いで下るのはこれで二度目だとかなんとかぶつぶつ言っていた。 俺自身はボロボロで、とても人の面倒まで見られる状態じゃなかったから、セツ婆さんの方は無事だけ確かめてその場に置いて来たのだ。 生きてる、ってわかった時は流石の俺も神に感謝したい気持ちだったけど……。 山の麓まで来ると、旺は晴子を下ろし、額に触れて何かを呟いた。それを見ながら、俺はふと子供の頃のことを思い出した。 「なあ、それ、俺にもやったことある?」 昔、お前ん家泊まった時……。 旺の返事はなかったので、俺はそれ以上尋ねなかった。よく思い出せないあの時なにがあったのか知りたい気もあったけど、なんとなく怖かった。 気づいた晴子が村中を起こしまわって大騒ぎになったので、俺たちはそのどさくさに紛れて屋敷に帰った。 俺が風呂に直行している間、旺が着替えを取りに部屋へ戻ったのだが、流石に二人がいないことに気づいていた母親に捕まり、今まで何をしていたのか厳しく問い詰められたと言う。 俺は後からそのことを聞いて、つくづくその場にいなくて良かったと思った。とてもポーカーフェイスを保てるだけの余裕はなかったろうから。 「それでお前なんて言ったわけ?」 「喧嘩したって言ったよ」 旺はけろりとして答えた。 「喧嘩? 俺とお前がかァ?」 「だって俺も泰ちゃんも擦り傷だらけだもん。泰ちゃんなんて浴衣は泥まみれだし。それに、最近俺たちが仲悪いの、母さん気にしてたからね」 う……。そう言われると、身に覚えのある俺としてはそれ以上文句がつけられなくなってしまう。 「殴り合ったらすっきりして、仲直りできたって言っといたよ。あ、それから喧嘩は俺が勝ったことになってるからそのつもりでね」 「なにー!?」 俺が旺に負けたことにするなんて、と面白くなかったが、なんとそれが意外に成功だったらしい。 普段、旺のおとなしさに内心歯痒い思いをしていた慶子叔母は、息子が殴り合いの喧嘩という「男らしい」 行為に出たことに拍手喝采し、しかも俺に勝ったということで、鼻を高くしたらしい。勿論口に出してはそう言わなかったし、朝なかなか起きられない俺に気の毒そうな顔をして見せたが。 母親ってそんなものかね。呑気な叔母の別の一面を見た思いで、俺は腹が立つよりなんだか面白かった。 おかげで他の都合の悪いことには全然気づかれなかったようだし。 「あ、おばさまー、これ、母からです。列車の中で食べてくださいね」 先に席に着いていた叔母に向かって、晴子は窓越しに包みを手渡した。俺たちはこれから一時間ほどこの汽車に揺られ、それから新幹線に乗り換えて上野へ向かう。 「まあ、悪いわね、お母さまによろしく言ってね」 「泰生さんと旺さんには、休み中子守をさせたって、うちの親、すっごく恐縮してるんです」 晴子はそう言って舌を出した。 「そんなことないよ、晴子ちゃん、こっちこそ色々案内してもらったし、今日もわざわざ隣町まで見送りにきてくれたしね。今度は是非東京に遊びにおいで」 旺が如才なく声をかける。 俺もこの元気な少女と別れるのが柄にもなく寂しくなって、横で何度も頷いた。 「そいじゃ慶子さん、昌弘さんに会ったら宜しく伝えてくれ」 晴子の横で扇子を使いながら、凡範伯父がのんびり言う。彼はこの後、また病院のセツを見舞うのだと言う。 あの人付き合いの悪そうな老婆に対し、於賀村の人々は優しかった。全員とは言わないが、知っている者も多いだろう。 今は孤独な老女の過去を。 明野は死んだと彼女が嘘をついたことを知った時、村の老人たちは申し合わせたように口を噤んでいた……。 「悪かったわ、あんまりお役にも立てなくて。こっちは一夏遊ばせてもらいに来たようなものだったわねぇ」 慶子叔母が苦笑しながらそう言うと、発車のベルが鳴った。 「じゃあ」 「また遊びに来ます」 「さよならぁ」 ゆっくりと列車が動き出すと、ホームで手を振る晴子の姿は見る間に小さくなった。 日が当たるからと、慶子叔母は俺たちをボックス席の窓際に座らせた。ちなみに車内は冷房がきいているから、窓は閉めておく。 向かいあった旺とぶつからないよう、仕方なく脚を交差させる。そっと奴の顔を伺ったが、相変わらず何を考えているのかわからないような顔でぼんやりと外を眺めている。 俺は誰にも気づかれないよう、溜め息をついた。 俺たちはこの先どうなるんだろう。東京に戻ったらもう会わないのだろうか。 旺はあれ以来、あの晩のことについては何も言わないし、仄めかすようなことすらしない。 表向きは何も起こっていないかのようだ。 だが、何も変わらない筈がない。なかったことになどできるわけがない。 俺は何一つ忘れていないし、忘れようという気があるかどうか、自分でもわからなかった。あの、旺の優しさと熱さ。 白状すると、俺はどうしようもなく旺を意識し、一方で昔のままに見下し、そしてどこかまだ怖かった。 彼は蔵で写真を見つけた時から、おおよそのことはわかっていたという。そして、俺が巻き込まれていくだろうということも。いったい、なぜ? この同い年の従兄弟には、まだ俺の知らない面がある。彼の力も、彼の気持ちも。 それを知りたいと思うだけで、もう俺は夏前とは違ってしまっている。なんとも腹立たしいことに。 慶子叔母ならいざ知らず、あの鋭い美奈子の前では何もかも見抜かれてしまうような気がして、俺はもし会うなら旺が俺ん家へ来てくれないかなあ、などとどうでもいいことを考えていた。と、膝の内側を足で強く押される。 心の中を見透かされたような気がしてぎょっと顔を上げると、旺が黙ったまま窓の外を指さした。 列車はすでに町中を離れ、車窓にはのどかな田園風景が広がっていた。ところどころに立つ高い電柱が次々と銅線で結ばれ、線路と平行に走っている。電線に仕切られた向こうに、こんもりと丸い山が見えた。 「あっ、あの向こうが於賀なのねえ」 横でしみじみとした慶子叔母の声がする。 凡範伯父にはああ言ったけど、俺も、旺も、於賀を訪れることは二度とないだろう。 右へと右へと流れていく景色を見ながら、俺はふと思い出したように足元の鞄のファスナーを開けて、中から朱色のノートを取り出した。 あんなことがあった後も、なんとなく捨てがたくて持って来てしまった。 ほつれかけた布表紙にそっと触れる。こちらを見ているに違いない旺の視線には気づかないふりをして。 そうして避けるように窓の外に目をやり……ぎょっとして思わず立ち上がりかけた。 疾走する列車の窓にぴたりと張り付き、髪をなびかせた女がこちらを覗きこんでいる。 「あけ、明野……っ」 慌てて旺の方を見ると、流石に仰天したらしく、肘をついていた手のひらから顎を外して、あんぐりと口を開けている。 「なんなのよ、泰ちゃん?」 幸い、叔母や他の乗客には見えないようだ。 俺のせいだ……。 ――東京までついて行けば良かったのに。 無責任にも口に出してしまった言葉を後悔したが、もう遅い。 明野の水色の着物の袖が、激しい風にあおられてバタバタしている。 窓越しの黒い大きな瞳。俺を見ているのか、それとも旺か。 冗談じゃねぇぞ。 俺は思わず窓の金具を押して、ガラスを上に押し上げた。車内に風が吹き込み、後ろの席の客がなにやら言ったが、気にしていられない。 親父、約束したけど、ごめん。 こちらへ伸ばす明野の手を掻いくぐるようにして、俺は手にしていたものを力一杯外へ投げた。 「あっ……」 旺が小さな声をあげる。 小さな赤いノートと女はすぐに視界から消えた。 強い風が痛いほど顔を叩く。 旺は僅かに窓から身を乗りだして俺の背後を覗いていたが、もう何も見えないだろう。 それでも俺にはたやすく想像できた。 緑の熱い、あの於賀の空で、弱った糸が切れ、ばらばらになって飛んでいく黄ばんだ白いページを。 そして明野が美しい腕を伸ばして、風に翻る一枚の写真をいとおしげに抱きしめる様を――。 終
|
| 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / NOVEL / HOME |