| 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / NOVEL / HOME |
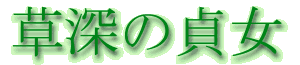 -2- 遠慮なくうちで夕飯を平らげてから、午後七時も過ぎると晴子は帰っていった。旺の方はというと、気分が悪いとかで夕方から布団を敷いてもらっている。 「やっぱり、蔵の埃が悪かったのかも。ごめんな、慶子叔母さん」 と俺は自分の責任とは全然思ってなかったものの、一応謝っておいた。 「あら、泰ちゃんが気にすることないのよ。子供の頃に比べて丈夫にはなったんだけど、精神的に疲れちゃうとすぐね。長い時間汽車に乗ってたのが、今時分に出たんでしょ」 慶子叔母は食卓の後片付けを手伝いながら、けろっとしていた。 「西瓜だったら食べられるかしら。後で持っていってあげましょうか」 「あら、いいんですよ、頼江さん。お腹がすいたら起きてくるんだから」 「そうですかー。でも本当に、デリケートなところも似てるわねぇ」 と、頼江伯母は、俺の顔を見ながら言った。 この家の凡範(ひろのり)、頼江夫婦は、親父や慶子叔母の従兄弟に当たるので、正確に言うと俺たちの伯父ではないが、他に呼びようがないので昨日の初対面では 「伯父さん、お世話になります」 と殊勝に挨拶しておいた。 「こんなところまで、無理言って来てもらって悪かったなあ」 「でも、そうでもしないとお互いなかなか会う機会もありませんものね」 隣町で汽車を降り、迎えに来てくれていた伯父の車で山道を抜ける。山道といってもきちんと舗装されていて、於賀村までは二十分ほどだった。 「まあ、長いこと大変だったでしょう、冷たいジュースでも召し上がれ」 「奥の部屋に布団は敷いておいたから、荷物はそっちにな」 岡家は、昔この村の庄屋だったという話で、屋敷は流石に古いものだったが、その分途方もなく大きかった。俺たちが通された部屋も、襖をいくつもいくつも開けていった最奥にあり、凝った造りの欄間とか、床の間の黒ずんだ柱など、いつの時代のものにしろ、当時随分贅沢な建物であったことがうかがえた。 「いや、だけど本当にお父さんそっくりだなあ」 凡範伯父は、スポーツバッグから着替えを取り出している旺を眺め、つくづくと言った。 「あら。凡範さん、うちの主人に会ったことあったかしら」 「え? あれ? 昌弘さんとこの子も連れてくるって話じゃなかったっけ」 「あのー。昌弘は俺の父ですけど……」 遠慮がちに言った俺に、凡範伯父は「ええっ」と心底驚いた声を出した。 悪いけど、驚いたのはこっちだ。俺は思わずまじまじと、旺の困った顔を見てしまった。 旺が親父にそっくり? それはつまり美奈子も似てるってことになるのか? 実の親だから遠慮なしに言わせてもらうけど、休日に腹出して引っくり返ってるあの親父と美奈子の美貌は似ても似つかないぞ。 「旺が兄さんに似てるなんて言われたことないわねえ」 と、これも意外そうな慶子叔母。 「うーん、そう言われてみればやっぱり泰生君の方が面影はあるな。だけど、なんて言うか、雰囲気がなあ。線が細いというか……」 凡範伯父はひとしきり首をひねってから、 「どうもうちの家系じゃ甥が伯父に似るもんだな」 と呟いていた。 あの太鼓腹親父の、どこが線が細いって? が、そういえば、若い頃はハンサムだったのにとお袋が嘆いていたことを思い出す。今でも筋だけは通っている鼻や鋭角な顎を大幅に美化修正して、ひとまず納得することにした。 この従兄弟も人の親になればあんなふうになっちまうのかなあ、と些か同情をこめた視線を送られて、旺の方はきょとんとしていたものだ。 しかし、デリケートとは。いくらなんでもそれは間違いだ、と俺が抗議すると、 「あら、昌弘さんも確か体が弱かったわよ」 と頼江伯母が言った。 「私がお嫁に来たばっかりの頃、一度だけここに来たことがあるんだけど、うちに連絡がうまくつかなくて、その頃タクシーなんかもなかったし、山道を歩いて来たのね。着いた途端玄関先でばたっと倒れて、えらい騒ぎだったわ。まあ、日射病だったらしいけど」 それは体が弱いというのだろうか。単に馬鹿なんじゃあ……と、自分の親のことなので、恥ずかしくなった。 「あ、そうだ。頼江伯母さん、この人誰かわかる?」 話題を変えようと、俺は蔵で見つけたノートから、写真を引っ張りだした。 「まあ、なんでしょ」 頼江伯母はどっこいしょ、と言って俺の隣に座ると、エプロンのポケットから眼鏡を取り出してかけた。 「なあに、なにか見つけたの?」 と慶子叔母も面白そうに身を乗り出す。 この部屋は三十畳はあろうかという大広間で、伯父たちも普段はこんな広いところで食事はしないのだそうだ。 「だけど、折角皆さんが来てくれたんだから」 と、立派な座卓をいくつも並べて御馳走をふるまってくれた。 「悪いけど、TVはこの部屋にはなくてね」 と若い俺たちを気づかって申し訳なさそうだったが、障子を開け放すと廊下を挟んでこれまた広い庭に面している。金がかかるとかで手入れはされていなかったが、古木の根元や伸び放題の雑草の陰から蛙や夏虫の声がうるさいほどで、TVなどなくても十分賑やかだった。それでも寝室にはポータブルを探してあげるという申し出を、断りはしなかったが。 「まあー、古い写真ね。明治か大正くらいのじゃないかしら」 「そんなに古いの?」 俺はびっくりして尋ねた。 「だってこれカラー写真だろ」 色褪せてはいたものの、着物は水色地に白い花を散らしたものだし、女の口元もしっかりと口紅で赤い。 「これはカラーと違ってね、後から色をつけたのよ。うちの親の昔の写真なんか、こうして着色したのがあるわ」 慶子叔母は懐かしそうに言って、 「それにしても綺麗な人ねえ」 と呟いた。 俺も「うん」とだけ答える。 晴子と太陽の下で見た時は勿論、こうして人工灯で見ても、写真の女は魅力的だった。日本髪に結った頭も重たげに、障子にそっと手を添えた立ち姿は、全体になよっと「く」の字を描いていて、何といったらいいか……全身から、見る者に対しての「媚び」のようなものが感じられる。しかもそれでいて、ちっとも厭らしい感じがしないのだ。 「これは、素人さんじゃないわね。芸者さんでしょう」 「芸者?」 「当時…って正確にはわからないけど、普通の人は滅多に写真なんかとらなかったし、とっても写真館で家族揃ってポーズをとって、というのがほとんどだった筈よ。こんなスナップみたいな写真……これは一種のブロマイドみたいね」 「ブロマイドってアイドルとかの?」 「そう。昔は綺麗な女優さんとか、芸者さんの写真が出回っていたのよ。ほら、外人さんなんかのお土産にもなるし、今でもポストカードとして残っていたりするらしいわ」 ふーん、と俺は呟いた。 「あ、ほら、見て」 写真を引っ繰り返して調べていた慶子叔母が声をあげた。 「かすれていて読みにくいけど……『吐月楼 明野』とあるわ。吐月楼(とげつろう)というところにいた明野(あけの)さんていう人なのね」 「明野さん……やっぱりねぇ」 不意に、今まで無言だった頼江伯母が、しみじみと吐息をついた。 「あんた、泰生君、やっぱり昌弘さんの子だわ」 「え? 親父?」 再び親の名が話題に上がったので、俺は驚いて頼江伯母の顔を見た。 「親父とこの人となんか関係があるの?」 「いやねえ、頼江さん。どう見たって、兄さんとこの写真の人じゃあ、年代が違うわ」 口々に言う俺と慶子叔母を、いささか芝居がかった仕種で黙らせて、頼江伯母はそっと秘密を打ち明けるように言った。 「さっき、昌弘さんが若い頃に於賀まで遥々やって来たって言ったでしょう。それ、明野さんを尋ねて、のことだったのよ」 「ええっこの人を?」 「なあに、そんな話聞いたことないわ」 俺たちは揃って驚きの声をあげた。 「もっとも昌弘さんは写真なんて見たことなかったでしょうに。蔵にあったなんてねぇ。 私も見るのは初めてで。この人が明野さんて人なのねえ」 頼江伯母は、眼鏡の奥から覗き込むようにして、写真に見入った。 「それで? 明野さんて、誰なのよ」 と意気込んで聞く慶子叔母の言葉に、頼江伯母は初めて困ったように口ごもった。 「えーと、それがねぇ。言ってもいいのかねえ」 「なあに? まずいことなの?」 好奇心で瞳を光らせながら慶子叔母が聞く。俺は黙って二人の会話を拝聴している。 「いいかしらねえ。もう昔のことだし。二人とも亡くなってるんだから」 「ええ、大丈夫よ」なんて無責任な。 「この人、庄右衛門(しょうえもん)の相手の人なの」 頼江伯母は、躊躇った挙げ句、声を潜めて言った。 「えっ。噂に聞くお妾さんなの?」 「まあ、その一人、というわけだけど」 「あらそうなの。へえ、この人がねえ。流石に綺麗な人ねえ」 「あのー」 一気に井戸端の噂話と化した叔母たちの会話に、俺は無理やり割り込んだ。 「庄右衛門て、誰?」 「泰ちゃんや旺のお祖父さんのお兄さんよ。私の伯父さんてことね」 「私にとっては舅なの。生前会ったことはないんだけどね」 と、これは頼江伯母。 「つまり主人の父親というわけ」 「旺君。そんなとこに立って何やってんだァ」 と、背後から、突然その主人、つまり凡範伯父の声がして、俺たちは文字通り飛び上がった。 「腹へったのかい。頼江、なんか出してやれ」 言われて、頼江伯母は慌てて立ち上がった。 「あ、旺。ご飯にするの? 西瓜もあるって」 「具合はもういいのかよ。麦茶でも飲めば」 俺と慶子叔母は何だか慌ててしまって、必要以上に旺の世話をやいた。いつから薄暗い廊下に立っていたのか、旺は俺の前の写真をちらっと見たっきり、おとなしく出てきて、促されるままに座布団の上に座った。 「いやー。こう広くちゃ、戸締りも大変だ。うちの蔵がやられる前は、この村じゃ誰も鍵なんてかけなかったもんだけどなあ」 伯父は首をふりふり、旺の前にあった麦茶のポットから自分の分も注いで言った。 俺は気づかれないように、そっと写真を引っ込めると、ノートに挟んで尻の後ろに置いた。旺が気づいてじっとそれを見ていたけど、何も言わなかった。 なんたって、さっきの話じゃ伯父さんの父親のオンナの写真だってことだ。もう時効かもしれないが、知らずに先に伯父に尋ねなくて良かった、と俺は思った。 九時が過ぎると、することもないので俺たちは寝室に引き上げた。布団に入ってポータブルのTVを見ていたが、毎週見ているというドラマが終わると、慶子叔母は本格的に寝についてしまった。 さすがにまだ眠たくないので、俺は俯せになって電気スタンドを枕元まで引き寄せ、例のノートから写真を引っ張りだして眺めていた。 大人びているが、二十歳前、というところかも。妾……とはちょっとショックだけど、でもこんな女なら愛人にしたいという気持ちはわかるなあ。 と、勝手なことを考えていると、俺はふと視線を感じて、枕の上で横を向いた。 「何だよ」 「泰ちゃん、その人のこと随分気に入ったみたいだな」 ……その通りなんだけど、どうもこいつの口調は気にさわる。 「悪いか」 と喧嘩腰の俺を、旺は 「別にそんなことないよ」 とさらりとかわした。 「すごい美人なんだってね。俺も見ていいかな」 満更お愛想でもない口調なので、俺は機嫌を直して 「いいぜ」 と答えた。俺が見つけたから俺のもの、という理由でもないだろうが、褒められると妙に嬉しい。 旺は、枕を持って、肌掛けごとずるずるっと這って側まで来た。 「ほらよ」 手渡してやると、スタンドの明かりに照らして、ためすがめつ眺めている。 おい、今までの無関心さはなんだよ、と言いたくなるほどだ。俺はちょっと不安になって、 「もういいだろ」 と写真を取り返した。旺はほうっと大きく息を吐いた。 別に旺に対抗意識なんて燃やす必要ないんだけど。相手はすでに死んでるっていうんだし。 だけど実在していたら危なかったかも知れない。顔は敵の方がいいし、背丈だって、ちょっとだけ負けてるし。この写真だって、隣に旺がいたら、きっと似合う……。 なんだか我ながら考えが変な方向に向かっている。 妙な考えを振り払うように、俺は尋ねてみた。 「お前、庄右衛門って知ってる?」 「うん。母さんたちが話してるの、聞いたことがあるよ」 「俺たちの祖父さんの兄貴ってんだろ。俺は全然聞いたことなかったなあ」 昌弘伯父さんは、噂話ってあんまり好きそうじゃないから、と旺は笑った。 「噂? なんの? お前、この明野って人のこと知ってた?」 俺が言うと、旺は、うーん、と唸りながら、自分の布団に戻って行った。 「おいっ、なんだよ。知ってるなら教えろよ」 「だってもう死んじゃった人の話なんか」 気が乗らない様子に、今度はこっちが身を乗り出す。 「死んじゃってるからいいんだろ。俺が知らなくてお前が知ってるなんて不公平だ」 旺は仰のいて、枕から頭を少し落とし、俺を横目で見た。前髪を片手でかきあげる仕種が、厭味に決まる。何だか昼間の印象とは違う奴だ。 「明野さんて人のことは知らないけど……庄右衛門て人のことなら」 「それでいいから」 俺がせっつくと、旺はしぶしぶ、といった口調で話しだした。 田舎とはいえ、これだけの家を構えた庄屋だったのだから、岡家は戦前大した金持ちだったらしい。村の名前の於賀というのも、もともと岡の方からきているという。 庄右衛門は何不自由ない跡取り息子だったが、三十代で死んだそうだ。名家の特権で戦争にも行かず、上京して、当時雑誌に載るくらいのモダンな洋風建築の家を吉祥寺に建て(屋敷自体は戦争で消失している)、生涯働くこともなく気儘に暮らしたらしい。 だが、特筆すべきはその贅沢ぶりではなく、音に聞こえた漁色家だったということだ。 「ぎょしょくか?」 俺は意味を確かめてから、旺に先をうながす。 何しろ、若くして死ぬまでに三人の妻を娶っている。一人は死別したという話だが、三人目は人妻を寝取ったというので、当時かなりのスキャンダルになったらしい。 「俺たちのお祖父さんもすでに上京していたんだけど、兄貴に意見しろって田舎からかなりにうるさく言われたらしいよ」 「へええ」 俺は何とも言いようがなくて、曖昧な返事をした。 「幸治伯父さんと凡範伯父さんも母親は違うっていう話だし」 「幸治って、もしかして議員だかなんだかやってるって人?」 それなら聞いたことがある。 「ふーん、凡範伯父さんの兄弟だったのか」 「兄さんらしいね」 「うーん……」 頭の中がこんがらがってくる。 「お前、よくわかんなくなんないな」 「うちはどっちもあんまり親戚が多くないからね。従兄弟だって泰ちゃんと智ちゃんの二人きりだし」 旺は、ちょっと笑った。 そうだった。子供の頃は考えもしなかったけど、それであんなに俺に懐いてきたのかも知れない。 俺はふと思い立ち、布団から伸び上がって、鞄からシャープペンを取り出した。 「えーと、まず、祖父さんたちがいて……。で、親父と慶子叔母さんが兄妹だろ」 ノートの一頁目に、皆の名前を書き込んでいく。 「俺、と智晴。でもってお前ん家が美奈子と旺……と」 「なに? 整理してるの?」 旺が再び体を寄せてきて、俺の手元を覗き込んだ。 「うん……。で、祖父さんの兄貴が庄右衛門、と。で、幸治と凡範……あれ、あれ?」 庄右衛門の下にその子供の名前を書こうとして、俺は迷ってしまった。母親が違うって言ってたっけ。 「ちょっとわかんねぇ。旺、書けよ」 俺がシャープペンとノートを押しつけると、旺は嫌な顔もせず受け取った。 「伯父さんたちの名前を書けばいいんだね」 「うん。庄右衛門の家族」 旺は少し考えて、幾つか名前を書き入れた。 「わかるとこだけだけど」 岡家の――ちなみに俺たちの祖父さんは養子なので、姓は岡ではなく、大野木という――系図は、こんなふうになった。 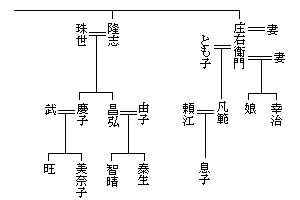 「……へー…」 俺は旺の書いてくれた部分を見て、ため息ともつかない、かすれた、妙な声を出してしまった。 庄右衛門の名前から、夫婦を示す線が三本も出ている。今更驚くことはない。さっき旺から聞いた通りだ。だが、名前のわからない二人を含め、一度は彼の妻を名乗った女たちなのだ。 何だか胸苦しくなってきた。 本当は、この他にも「愛人」や「妾」として多くの線が引かれているはずなのだ。表には出てこないだけで。系図には残らないだけで。 そして、明野はそのうちの一人なのだ。 「ちぇっ」 俺は写真を乱暴にノートの間に戻すと畳の上に放り投げ、スタンドの紐を引っ張って明かりを消した。 「泰ちゃん?」 「もう寝ようぜ」 俺は枕に顔を押しつけたまま言った。俺がせがんで話してもらったのだから、旺に腹を立てる筋合いはないんだろうけど。 旺は黙って立つと、部屋の電気を消しに行った。 首の後ろがまた痒い。シーツや枕カバーは清潔だけど、虫の多そうな家だから、刺されるのは仕方ないのかもしれない。 ばりばりと首筋を掻きながら、俺はふと、親父が明野を尋ねて於賀まで来た、という話を思い出した。つまり、この女は東京の女ではなかったのか。 それにしても、なぜ親父はわざわざ彼女に会いに来たんだろう。そして望みはかなったのか。その時はまだ、少なくとも女は生きていたのだろうか。 土曜の夜はいつも帰宅が遅いが、明日は日曜だから昼間から家にいるはずだ。忘れずに電話して話を聞いてみよう、と思った。 俺は闇の中で、そっと布団から手を伸ばした。旺に気づかれないように、手探りで布表紙のノートを引き寄せると、枕の下に押し込んだ。 薄いから、別に違和感も感じない。その上に、そっと頭をおいた。 こんなに早くて眠れるわけがないと思っていたのに、その心配はなさそうだ。旺はさっきから身動きもしない。 真っ暗だ。あの辺に欄間があるはずなのに、まるで見えない。 それにしても、虫がうるさかった。 そうしてその夜、俺は、おかしな夢を見たのだ。 熱い夢。 耳元で聞こえる、自分のものではない荒い吐息が確かに愛しかった。 熱にうかされて夜中に目が覚めたような気がする。 翌朝にはもう、ほとんど覚えていなかったのだけれど。 |
| 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / NOVEL / HOME |