| 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / NOVEL / HOME |
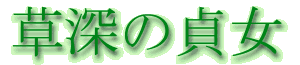 -4- 「あのー、こんにちはー?」 晴子は勝手にがらがらと引き戸を開け、流石にそこからは遠慮して、中に向かって声を張り上げた。 「館林商店ですけどー」 「晴子ォ、御用聞きじゃないんだからさ」 「それならお勝手から入るってば」 晴子の背中から中の様子を伺って俺、その後ろに旺だ。 「返事ないね」 「留守なんじゃないかな」 「だいたい、なんだってこんなに暗いわけ?」 俺は頷いて、いっそう身を乗り出した。 たった今背にしてきた、陽の照りつける外界が嘘のように、山村家の屋敷の中は、ひやりと薄暗く、静かで人の気配もなかった。さすがに蝉の声はしていたが、それも先刻ほどの迫力はない。 だだっ広い玄関の三和土の部分には靴一つ見当たらず、傘立てらしい陶器の瓶が隅に置かれているだけだ。右手の壁に大きな額縁がかかっていて、よく見るとそれは竹藪と虎の絵だった。 正面はどうやら木目の廊下がそのまま奥へと続いているようなのだが、その先はよくわからない。 「山村さーん、セツお婆さーん」 晴子はえいっと玄関へ足を踏み入れた。気は進まないように見えてもやはり頼りになる。俺には、留守かもしれない他人の家に勝手に入り込む勇気はない。上がり口に手をついて、晴子は何度かごめんくださいを連呼したが、やはり人の出てくる気配はなかった。 「いないみたいだな」 「清さんの家かも。行ってみる?」 うん、と俺はおとなしく踵を返し、後ろに立っていた旺にぶつかりそうになった。 「おいっ、なんだ…よ……」 どこうとしない相手の体を押し退けようとして、俺はふと振り向いて旺の視線の先を追った。 その時、俺があげた悲鳴を確かに聞いたと、後で二人に指摘されたが、それは誤解だ。 ちょっとくらい声は出したかもしれないけど……単にびっくりしただけだ! いつの間にか、薄暗い板張りの廊下の真ん中に、白っぽい着物を着た老婆が立ってこちらを見ていた。 「誰だい」 老婆の唇から漏れた言葉が、ひんやりした廊下を滑ってきた。 「あ、山村のお婆さん。私、館林商店の晴子です」 晴子は大して気後れした様子もなく、すぐに挨拶した。 「お婆さんに話があるという人を連れてきたんです」 老婆は軽く頷くような素振りを見せたが、それきりこらちに近寄るでもなし、じっとこちらを伺っている。 晴子が肘で脇腹を突いてきたが、俺はまだ痺れるような驚きから立ち直っていなかった。 「あ、のっ……」 舌が強張ってしまって上手く動かない。 「お、おれ……いや、僕、大野木泰生といいます。ええと、大野木隆志の孫です」 そこで、相手の反応を伺う。 老婆はにこりともしない。 「ええと、……」 俺が助けを求めるように二人を見ると、旺が助けを出してくれた。 「祖父は岡から養子に行った人間です。先代の庄右衛門の弟です」 山村セツの上半身が揺れた。僅かに一歩踏み出したからだった。 「おか……」 低くてかすれているのに、明瞭な声だなと俺は思った。 だが、待っても、セツの次の足は出なかった。 「……保険屋が今ごろ何を言ってきたやら。言っとくが、あたしゃ自分で自分の面倒は見られるし、この調子で百まで生きるつもりだよ」 続いて口から出た言葉は、ひどくぶっきらぼうだった。 「ほけん?」 意味がわからず、面食らう。 だが、旺の方はすぐわかったようだ。 「いや、凡範伯父さんの使いじゃありません。伯父さんは関係ありません」 そういえば、定年前の凡範伯父さんは隣町で保険関係の仕事をしていたという話だった。 「あの」 俺は口を出した。 「明野って人のことが知りたくて。俺のおや……父が、山村さんに話を聞いたって言ってました。もうずっと前の話だけど」 また乱暴な調子で言い返されると思いきや、セツは、「ああ」と驚いたような、それでいてひどく懐かしそうな、優しい声を出した。 「覚えている……」 セツは指先を持ち上げ、こめかみの辺りにゆっくりと触れた。 「覚えているよ。ずいぶん前だが。そういえば、庄右衛門の甥だと言っていた」 「そう、そうです」 嬉しくなって思わず何度も頷く。 「それで? まさかあんた達もまたあの女の話を聞きたいっていうのかい」 その途端、俺は親父の言葉を思い出した。 『嫌な女だった。明野のことも俺のことも馬鹿にして……』 それが本当なら、明野の話などしたくないかも知れない。 だが、意外にもセツはあっさりと言った。 「いいさ、お上がり」 「えっ」 「どうせ暇だし、聞きたい話があるんならいくらでも教えてやるよ」 そう言って、背を向ける。 そのまま、出てきた時のように静かに奥へ引っ込んでしまった。 「あ、ちょっと……どうしよう」 「どうしようって、上がっていいって言うんだから、そうしよ」 晴子が屈託なく言う。 「何だか思ったより好意的みたい」 「旺?」 俺は思わず、従兄弟の顔を伺ってしまった。 旺は無言で、「お先にどうぞ」というように首を傾げた。 二人に促され、俺は仕方なく一番に靴を脱いだ。 「暗いね」 「何で電気点けないのかな」 「ケチなんじゃない」 通された洋室のソファにおとなしく腰をかけた俺たちは、ひそひそと囁き合った。 昼間だというのに、分厚いカーテンがひいてあるせいで、室内は薄暗い。高い天井からはシャンデリアらしきものが下がっているのに、スィッチはどこにあるのか、セツは点ける素振りも見せなかった。 ごてごてと調度品が多い部屋である。ソファの隣にも木彫りの大きな象がいて、それが埃を被っている。アレルギー気質のあるらしい旺は、そわそわとやや落ち着きをなくしている。 「なあ、これ何かな」 俺は目の前のテーブルにおかれた皿を指さした。 セツが出してくれたものであるが、黒くて得体が知れず、手を出す気になれない。 「えーと、たぶん葛餅だと思うんだけど……」 「食べてみろよ」 「えっ、あたしがぁ? えーと、旺さんどうぞ」「俺はちょっと……」 そんなことをやっているうちに、どこかへ行っていたセツが戻ってきた。 最初の得体の知れないような印象に比べ、間近で見ると、セツは普通の小柄な老婆だった。頭はすっかり白く、シワだらけの顔と手は日に焼けて、そこへ茶色の染みが幾つも浮いている。 ただ、背筋だけは真っ直ぐで、俺たちを前にした姿には、どこか屋敷の主人然とした貫祿が残っている。 死んだ山村は村長だったという話だった。この屋敷の構えからしても、於賀の他の家とは格が違う。 一時は岡家と村を二分する力があったに違いない。 「そう、あんたがあの子の息子ってわけかい」 セツは、親父の若い頃によく似ているという旺には見向きもせず、俺の顔を見て言った。 顔を寄せられて、俺はセツがやぶにらみであることに気付いた。皺に埋もれた右目はぴたりと俺にすえられているのに、左だけが僅かに余所を向いている。 「それでまだ明野のことなんか言ってるのかい? もういい年になったろうにね」 「あ、違う。話を聞きたいのは俺なんです」 「あんたが?」 皺が伸びて、濁った目が丸くなる。 「あの、これを岡の家の蔵で見つけて」 俺は、手にしていた朱色の本から、写真を取り出した。 「なんだい」 受け取ったものの、じっくり見るでもなく、セツは興味なさそうに言った。 「あのー、それが、明野さんだって、伯母が。裏にもそう書いてあるし」 「明野の写真だって? これが」 セツは驚いたように、写真を持った手を持ち上げた。 あれ、と思う。ひょっとして、この婆さんは明野を知らないのか? 「違うんですか」 「あ、いやいや」 と、セツは慌てて首を振った。 一瞬裏返してから元に戻し、 「これがあの女だ」 と確認した。 「どこにあった?」 「だから、蔵に。文机の引出しの中にありました」 へえ、とセツは手の中の写真をつくづくと眺めた。端の擦り切れた、ぼろぼろの写真だ。だが、老いて骨張った手に妙に似合う。 「これは……何時の写真だろう……」 「団扇を持っているから、夏でしょう」 旺が口をはさむ。 「夏かい。花柄の着物……だね」 独り言というより、俺に話しかけているようなので、 「そうですね」 と答えた。それだけでは愛想がないようで、付け加える。 「夏だから、水色の着物なんですね」 「色?」 「ああ、それ、後から職人が着色したものなんでしょ。叔母が教えてくれました。俺は一瞬、カラー写真かと思っちゃったけど」 「いや、違う」 とセツは否定した。 「違う?」 「この写真は配られた時は白黒だったはずだよ。写真屋が色付けしたんじゃない」 セツは爪の短い指先で、そっと表面に触れた。 「誰だか知らないが、自分で色をつけたんだろう」 旺は、へえ、とセツの手元を覗き込んだ。 俺も驚く。専門家の手によるものとしか思えなかったほど、丁寧な仕事だった。 誰……って、写真は恋人の持ち物だったのだから、色を塗ったのはおそらく庄右衛門だろう。 ふ、と目の前の光景が変わった。 和室の奥に、文机に向かった男の後ろ姿が見える。男の背格好は曖昧だ。だが、俺には背を丸めた彼が何をしているかはわかる。 恋人の写真に色を塗っているのだ。 夏だから、着物地は水色にしよう。花は白。 そして、丁寧に、唇を赤くなぞって。 ……絵の具かな、色鉛筆かな。当時、色鉛筆なんて日本にあったんだろうか。想像力の乏しい俺は、細部に自信が持てなくなって、そこで現実に帰った。 セツはまだ写真を手にしていた。が、それをポイとテーブルの上に放った。 「物好きな男だよ」 どこか馬鹿にしたような口調に、むっとして、写真を回収する。 「それで? あんたまで、明野の何を聞きたいって言うんだい」 聞かれて、俺はすぐに答えられない自分に気付いた。 これと言って、特になにを、というつもりではなかった。 ただ、写真の女性が、どんな人だったのか、何を話したのか、そんな他愛ないことを漠然と聞いていたかったのだ。 だが、セツはどうも好んで昔話をしようという婆さんではないようだし、親父に聞いた話では、それが明野のことなら、尚更らしい。 旺や晴子は明らかに付添い、という態度をとっていたので、俺が黙っていては話が始まらないようだ。俺は仕方なく、一番気になっていたことを尋ねてみた。 「庄右衛門と別れたあと、明野さんはどうしたんですか」 「どうとは」 口調は素っ気ない。 「ええと、於賀に住んでたんですか。確か、ここの出身ではないって話ですけど」 「そうだよ、家を貰ってね。どっちみち、家族もないようだったし、芸者もやめさせられてたから、他に行くところも無かったろうけどね」 セツは淡々と言った。 「男は家に入れたかったようだが、家の者や親戚筋が許すわけはない。それなら側におこうというつもりだったのかもしれないが……」 口元が妙な具合に歪んだ。もしかしたら、笑おうとしたのかもしれない。 「あたしら村人にしたらいい迷惑。岡の跡取り息子が、村の隅で女を囲っているんだよ。 本家も分家も揃って反対してるから、当然於賀の人間もそちら側につく。といって、息子の手前邪険にもできない。追い出すわけにもいかない、厄介な女さ。せいぜいがところ、無視するくらいしかできなかった」 ソファの隣で、晴子が「可哀相」と呟いた。 セツの耳にも入った筈だか、何の反応も示さない。 「それで……?」 「それでって、息子は東京に行っちまったのさ。もう誰も遠慮なんかするもんかね」 「遠慮?」 旺が眉をしかめて聞き返す。 「明野は死んだんだよ。以前、あの男にも教えてやった筈だよ。聞かなかったのかい」 「知ってます」 俺は、自分の声が震えがちなのに気付いた。 「病死じゃなかったんですか」 セツは、俺の剣呑な様子に気付いて、笑った。 「ははは、まさか、あたしらが苛め殺したと思ってるんじゃないだろうね」 「違うんですか」 皺くちゃの老婆は、首を振った。 「あの女が勝手に死んだのさ」 「そんな、いくらなんでも殺したりするもんかね。実は、岡の家も、跡取りがいなくなった後は、以前のように辛く当たるようなことはなくなってね。息子が何か言ったのかもしれないが、もう邪魔にする必要もなくなった、っていうのが本当のところだろうね。肝心な男の方はもう村にいないわけだからね」 「男は……」 俺は、写真の端を強く掴んだ。 「庄右衛門は、女を捨てたんですか」 「ああ」 「でもっ」 乱暴に身を乗り出したために、葛餅の乗った皿が弾かれて音をたてた。 「祖父さんが……庄右衛門の弟が、彼はそのつもりはなかったって。東京で縁談が起こって、仕方なく……」 薄暗がりの中で、老婆の笑い声が響いた。 一瞬ぎょっとするほど若い、生々しい女の笑い声だった。 「隆志……思い出したよ、当時はまだ子供だった。そう言えば、あの子は兄の味方だった。明野の家にも時々遊びに行っていたようだね。明野を訪ねてきたその息子。それから、そのまた息子のあんた。お笑いだね。なんてめでたいんだろう」 セツは可笑しくて仕方ない、というように手のひらで口元を覆い、笑い続けた。 「めでたいのは、あの女も一緒。男の当てにならない約束を信じて、待って、死んでしまった」 「約束って?」 「迎えに来る、って言ったらしいね。聞かされた者は皆、大笑いしたもんさ。あたしは面と向かって言ってやった。あんたは捨てられたんだ、って。あの男はもう二度と戻って来ないってね」 「ひどい」 小さな悲鳴を洩らした晴子の方を見て、さらに言い募る。 「何故? あたしは親切だから言ってやったんだよ。こんな田舎で愚図愚図してないで、さっさと次の金づるを探しに行った方がいいよ、とまでね。だけど、あの女は聞かなかったのさ。男に貰った金なんか、いつまでももつもんか。そのうち、死んでしまったよ。当然じゃないかい」 腹の底から沸いてきた怒りが体の外へ吹き出そうとするのを、俺はこらえた。 「あんたは、明野が嫌いなんだな。そうだろう。それで困っているのを見殺しにしたんだなっ」 「嫌いだね。あんた達にあの時代がわかるかい。女が体も張らずに一人で生きていける時代じゃなかったんだよ。あの女にはそれがわかっちゃいなかった。好きな男を待つってかい。そんなのは綺麗ごとだよ。あたしをご覧。あたしの旦那は成金だと随分後ろ指を指されもした。だが、金は金だ。お蔭でこうして老後は安泰なのさ」 「もういいっ!」 俺は激昂して立ち上がった。 「もういい、わかった。やっぱり親父の言う通り、あんたの話なんか聞きに来なけりゃ良かった。あんたは確かに金持ちの男を捕まえた、成功した女かもしれないよ。だけど、そんな皺くちゃの因業婆ァになるくらいなら、明野は早死にして幸せかもしれないな!」 初対面の年寄り相手に、暴言だという意識はどこかにあった。 だが、我慢できなかったのだ。 明野を、俺の明野をこんな風に馬鹿にするなんて……。 炎天下を歩いた時のように、体がカーッと熱かった。 「あんた達親子は一体何を求めてるんだい」 セツは、俺の飛ばした唾をのけ反って避けただけで、こっちの剣幕には一歩も引こうとしなかった。 「三代揃って、明野をどうしたいって言うんだい。大方、理想の女性像でも思い描いてるんだろう。男に都合がいいのが一途な女さ。それが美形なら尚更だ」 「悪いか!?」 「別に」 セツは肩をすくめた。 「明野はその通りだったからね。ああ、写真を見たんだっけね。 綺麗な女だったろう。それだけは認めてやるよ」 それから、クスリと妙に子供っぽい笑い声をたてた。 「そういう意味では、確かに早死にして正解だったかもしれないねぇ」 俺は、フン、と鼻を鳴らした。 明野がもし生きてたら、美しく上品に老いたに違いない。 「せいぜい崇めてやるといいよ、死んだ女でよかったら……」 「ああ、そうする……」 答えながら、俺は指の腹で額を強く擦った。先程から体を侵す熱が、頭まで上ってきて、瞬間くらりとしたからだった。 「それじゃあ」 今まで沈黙を守っていた旺が、立ち上がり、さり気なく俺の肘に手を添える。 「僕たちはこれで失礼します」 晴子も慌ててそれに倣う。 「送らないよ」 素っ気ない口調に、舌でも出してやりたい気分だった。 「どうも、御馳走さま!」 わざとらしく声を張り上げて、俺たちは足音高く、洋間を出た。 ドアのところで、もう一言何か言ってやろうと、室内を振り返る。 閉め切った、埃臭い洋間。 年代ものの家具の中で、年代もののセツの背中がこちらを向いている。 日の差さぬ仄暗い部屋に、捨てゼリフは出て来なかった。 ただ、俺はもう二度とここに来ることはあるまい、と思った。 不可解な熱を持て余す身で、それは予感というより、確信に近かった。 |
| 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / NOVEL / HOME |