| 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / NOVEL / HOME |
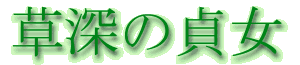 -5- あたしは十八で、あの人は、あたしが初めての女だと言いました。 あたしは、うれしかった……。 また、妙な夢を見た。いや、確かに夢だという確信はないのだが、状況を考えるとそうとしかいいようがない。 そもそも俺はあんまり夢をみない性質なのだが、於賀に来てからは夜毎おかしな世界に入り込んでいるようだ。目覚めると覚えていないことが多いが、体はだるく、痛むことさえある。 夢の中で、俺は歯を磨いていた。 眠っているのが夜でも、夢の世界では明け方らしく、周囲はぼんやりと明るい。珍しく一番に目が覚めたようで、屋敷の中はひっそりとしていた。 洗面台の上には端の欠けた大きな鏡があり、だらしなくパジャマを着た俺が映っている。 蛇口をひねると夏なのに冷水がほとばしった。 「つめて……」 俺は歯を磨くのが下手だ。だから、歯磨き粉を飛ばさないよう、うんと体をかがめ、洗面台に顔を突っ込むようにする。歯を磨いてる自分の顔なんか見てもしかたないので、これでいいのだ。 そうやってしばらく無言でゴシゴシやっていると、ふと自分が鏡に映った情景を眺めていることに気づく。 いや、鏡の中の俺は下を向いていて、頭頂部と丸めた背中しか映っていない。 では、こうして鏡を見ている俺は誰なのか? 夢ではまったく何でもありらしい。 赤茶チェックのパジャマの背中が、ハブラシを動かすたびに細かく上下している。 ――そして、そこから、彼女が現われた。 はじめに肉のない尖った背中。次に黒い頭が小さく覗き、長い髪が音もなく広がっていく。 昆虫がさなぎから孵るようだった。 明野――疑いようもなく、彼女――は、頭を起こし、黒々とした目で鏡に映った自分の顔を見た。確かめるように両手で頬を撫でる。流れる黒髪が水色の着物にまとわり付き、袖口から真っ白な腕が覗く。 その下では相変わらず、ジャージャーと水を流しながらせっせと歯を磨いている俺。 ふと鏡の中の明野と目が合う。彼女は写真の中のあの夢見るような瞳で、にっこりと微笑んで見せた。 「喧嘩したのね、そうでしょ」 相手のストレートな質問に俺は顔をしかめた。 「あいつ、なんだって」 「『泰ちゃんが嫌がると思うから俺は遠慮しとく』」 晴子は旺の口調を真似て言った。 「喧嘩してても、ちゃん付けで呼ぶとこが旺さんよねえ」 晴子は健康的でかわいい。素直で気取りがない。会話に変な駆け引きがいらないから、前に付き合ってた女たちみたいに面倒なところもない。向こうに俺に対する異性としての意識が足りないから、彼女にしようという気は起こらないが、一緒にいて楽しい、イイ奴だ。 美奈子の不参加のせいで、すっかりへこんでいた俺の気分も、この娘のおかげで八割方復活していた。知らないだろうが、これってすごい褒め言葉なんだからな。 そんな晴子の魅力だが、裏返せば遠慮のなさにつながる。しかも、それが俺にたいしてだけだと思うのは気のせいなんだろうか。 こいつ、 「早くあやまった方がいいと思うけど」 とまでぬかしやがった! 「な・ん・で、俺があやまるんだよ!?」 俺は沸騰寸前だった。 よりによって、なんで「俺が」「旺に」あやまるなどという状況が想像できるのだ! そりゃ晴子は、子供時代、美奈子と三人で遊んでいた頃のことを知らないだろうが、それにしても、見ててわからないのか? 俺と旺の力関係が……。 ちょっとここんとこ、そのへんが微妙かな、と俺自身感じないわけではないけれど……。 それでも、俺が旺に頭を下げるなどということは、絶対に、あり得ないのだ。 朝飯もそこそこ、晴子が裏山を案内するからと言って誘いにきたが、前述の通り旺は辞退したので、俺たちは二人で家を出た。 連日のかんかん照りに日射病を起こしそうになっていた俺は、凡範伯父さんの麦わら帽子を借りるつもりでいたが、山中は木が繁っているから直射日光は当たらないのだと教えられてやめた。言われてみれば当然だ。 上まですぐだ、年寄りや子供のお散歩コースだ、と聞いていたので、軽い気持ちで誘いを受けたのだが、十分もしないうちに顎が出た。 だいたい、これが散歩道か? こういうのを道っていうのか? 単なる「人が踏んだ跡」って言うんじゃないだろうか。 東京ではみすぼらしくどこか卑屈にさえ見える木々の幹も、太かったり細かったり妙に個性的で、触れたら変な病気にかかりそうな気がするし、頭上高くでわさわさと絡み合う梢はこちら側の気分を敏感に感じ取るのか、嵩にかかって威圧する。 確かに日は遮られているが、動いていれば汗はかくし、そこへ得体の知れない小さな虫がまとわりついてくるので、繊細な(?)俺はうんざりしてしまった。 晴子が明らかに俺に合わせてペースを落としてくれていることがわかったので、悪態は心の中でつくにとどめていたが、途中ようやく林が切れて明るく開けた場所へ出ると、ついに「タイム」を申し出た。 土と苔で汚れた切り株を見つけ、急いで腰を下ろし、膝に両肘をついて犬のように舌を出す。晴子も都会人の軟弱さを了解したと見え、内心どう思ったにしろ、少なくとも小休止をとることは承知してくれた。 中学まではバスケをやっていたが、今じゃ完全に帰宅部だもんな、俺……。体はなまりきってるよ。 けろりとした顔の晴子は、虫と下草対策だというハイソックスを履いた細くて長い足を絡ませて退屈気に俺の前に立ち、そこで先刻の喧嘩云々……という会話になったのだった。 「だって、旺さんて怒ると怖そうじゃん」 「怖い? 旺が?」 俺は馬鹿にした意味をこめて、旺がァ?と語尾を上げてみせたが、晴子は真面目な顔で、 「旺さんて、徳田さん家の裕司兄さんに似てるの」 と言った。 「誰だそりゃ」 「ほら、あたしん家の右隣の新しい家」 「えーと、車が二台ある家?」 「そこそこ。昔は裏手が広い庭でニワトリ飼ってたんだよ。で、あそこん家のお父さん、声がでかくてさ、和ちゃん怒る声が筒抜けで……あ、和ちゃんてのは弟の方なんだけど」 「ふーん」 於賀村の世間話には大して興味も持てそうになかったので、生返事をしておく。 「あたしが小六の時かなあ、日曜かなんかで家にいたら、徳田さん家からすごい怒鳴り声が聞こえてきて、どうやらニワトリをしめるとかしめないとかで和ちゃんが叱られてるわけ」 「にわとり……」 「がさつな親から生まれた割に、あの兄弟はおとなしくて、特に和ちゃんはちょっと気も弱くてさ、そこがお父さんの気にいらないとこでもあるらしんだけど。そいで、父親がニワトリをしめてみろって言ったのに和ちゃんが嫌だって泣いてて……」 なんだかいまいち状況がよくわからなかったが、ニワトリ云々という小道具に妙に感心して俺は聞き入ってた。 「お父さんは怒鳴るわ、殴られて和ちゃんはぎゃあぎゃあわめくわ、すごい騒ぎでさ、最初はああまたか、ってあたしも思ってたけど、いい加減うるさくなって窓から徳田さん家を覗いたのよ。そしたらちょうどあっちの二階の窓がガラッとあいてね、裕司さんが……」 あ、裕司兄さんも物静かな人なんだけど、その代わり頭がすごくよくて、今は東京の大学へ行ってるの、と晴子は付け加えた。 「裕司さんが、うるさい、って言ってテレビを落としたの」 「テレビ……」 俺は驚いて晴子の顔を見上げた。 「……液晶とかの小さいやつ?」 「違う違う、十四型くらいのちゃんとした奴。それをさ、両手で持ち上げて庭へ落としたの。二人のすぐ横へどすっと落ちてさ。和ちゃんはびっくりして泣き止むわ、お父さんは壊れたテレビをじーっと見下ろして。イヤー、怖かったよう」 晴子はドラマのように目をつむって首を左右に振って見せた。 「あたしさー、それまで裕司兄さんてちょっと好きだったのね。優しいし、いつも落ちついてて大人びてたし……。でもそのことがあってから、あたしにはついてけないや、って思っちゃった。普段おとなしい人ほど切れると怖いよねえ。なーんか旺さんて似たとこあるんだよねえ、雰囲気かなあ、裕司兄さんもハンサムだったし……」 晴子が俺に対するほど旺には杜撰にふるまわないわけがわかったような気がした。 その後すぐ出発したけど、俺は道々、両手でテレビを持ち上げて仁王立ちになる旺の姿を一生懸命想像していた。 「へーっ、いいじゃん」 思わず漏らした感嘆の声に、晴子は満足そうな顔をして見せた。 「ホタル沼って言うんだけど、流石に今はほとんど飛ばないみたい。でもきれいでしょう、見た目は水も澄んでるから、沼っていうより池みたいよねぇ」 うんうん、と俺は頷いて水面を覗き込んだ。 「泳げるの?」 「それはちょっと無理。さすがに底の方はドロドロしててね、危ないから遊泳禁止なんだ」 汗で濡れた首の後ろを、どこから吹くのか、静かな風がひんやりと撫でていく。 帰りたいという一言を我慢して登ってきた俺に、十分報いるだけのものがそこには待っていた。 鬱陶しい暗緑の天井が、ここだけは潔く晴れて、明るい光が矢となって降り注いでいるのがはっきりと見て取れる。 眩しく反射する水面から覗く多年草の穂も控えめな輝きを放ち、背後に残してきた陰気な緑と同じ植物とは思えなかった。 山奥ののどかな一枚絵のようでありながら、どこか浮き世離れした清らかさもたたえている。そして、同時に強い既視感。 沼として大きいものかどうかはわからなかったが、だいたい向こう岸まで二〜三十メートルといったところだろうか。 「入っちゃ駄目だよう」 俺があんまり沼ばかり眺めているので不安になったのだろうか、晴子は冗談めいた口調でしっかり釘を刺した。 「大丈夫だよ」 俺は明るく答えたつもりだった。でも、実際には声にならなかったかもしれない。 その時の俺の目には、陽光にきらめくこの場所の昼の姿が映っていたのではなかった。 暗がりに、小さな光が舞っていた。 晴子の言った通り……ホタル。 森は黒々とした影となり、俺とこの沼を取り囲み、沈黙を守っている。いや、どこかで夜の鳥の鳴き声が……フクロウだろうか。 頭上遙か太陽のあった位置には、青白い月が妙に大きく顔を覗かせ、同じものが眼下にもう一つ、ゆらゆらと笑いをこらえていた。 怖くはない。 それより体の芯が痺れるような、甘い記憶だった。 背後で身じろぎする気配。 すぐ近くに誰かが黙って立っている。 俺は振り返らなかった。このままいつまでも、相手の息づかいを聞いていたい気がした。 「いやっ、泰生さんっ!?」 不意につんのめるようにして倒れた俺に、晴子が悲鳴をあげた。 湿った草むらに顔を突っ込む。途端に鼻をつく、熱い、太陽の、昼の匂い。 ああ、駄目だ、まだ……。 楽しい夢から目覚めたくない子供のように、俺はいやいやと首を振った。 「……なんでもない、靴の紐が……」 現実に引き戻そうとする晴子の腕を振り切り、その場を繕おうと、上体を起こして震える手をスニーカーに伸ばす。 途端、バサッと髪が落ちてきた。 くそっ、邪魔だ、この長い髪、ちゃんと結ってくればよかった……。でも髪を下ろしているのが好きだと……。 「泰生さん、しっかりしてよぉ」 ああ、誰かの泣き声がうるさい。聞こえないじゃないか、声が。 俺を呼ぶ声が。 ざーっと音をたてるように、体中の血が後頭部に集まってきた。耳の後ろが激しく鼓動を打ち始める。 「やだー、もーっ、どーしたのよぅ……」 明野、明野。 俺は微かに感じる女の気配を逃すまいと、目を閉じ、激しい頭痛の中、その後を必死で追った。 あんたなんだろ? あんたなんだろ、明野? ソウ。 甘やかな感覚に包まれた。 ――アタシハ、ココデ、死ンダ。 息の詰まるような女の匂いに、俺は気を失った。 俺は死んで、焦熱地獄に落とされたんだろうか。体が燃えるようで、悲しくて嬉しくて切なくて驚いて……涙が出た。 自分が何をしているのかはわからないまま、身をよじって体を寄せる。 ひどく熱いものに全身が包まれていて、また、その熱が一点から進入してくる。 体を離してしまえば、この悲しみからも、憎しみからも開放されるのに。 でもできない。この熱さを失って、何で生きていくことができるだろう。 痛い……。 俺は、熱さに喘いだ。 こんなに苦しいのは俺だけなんだろうか。そう思うと堪らなかった。 地獄のような、それでいて天国のようなこの場所に囚われているのは自分だけなのか。 相手にまわした腕に力を込める。男の肉を引き裂くように爪を立てた。 同時に灼熱の波が一気に襲いかかってくる。 「ああっ……」 俺はたまらずに呻き、半身をのけ反らせた。 相手の固さにすがりつき、俺は夢中でその名を呼んだ。 俺のものだ、俺のもの。渡さない。 「泰ちゃん!」 俺は突然、横っ面を引っ叩かれた。 「起きろよ、泰ちゃん!」 俺は目を閉じたまま、夢から覚めた。 それこそ、一気に正気に戻った。 さっきまでの狂気が嘘のような、現実の世界。その落差に震えだすほどだった。 なんの夢だったのか、恐ろしくて思い出したくない。俺の受容力を遙かに越えた、渦巻く感情。光とも闇ともつかない陶酔。 そして、同じように恐ろしいのは、今、目を開けることだった。 薄い瞼を通して、まだ昼の明るさが感じられる。 そしてわかる。息も触れんばかりに俺を覗き込んでいる顔。 「泰ちゃん」 微妙な声音で、奴がもう一度手首を引いたのがわかった。 「よせ」 呟いて、目を開けた。 俺の額に、旺の長めの前髪がかかっていた。身を引こうとするが、枕で押さえられて頭が動かない。 「どけよ」 俺の言葉に、鼻先にある奴の瞳が、一度だけゆっくり瞬いた。茶色というより、灰色に近い目。逆光だというのによく見える。 「どけってば」 目を逸らさず、語調を少し強める。それでも声がかすれてしまう。 旺は片目を僅かに細めた。 「手を放してくれればね」 俺はようやく、奴の上腕を握りしめた、自分の指に気づいた。シャツの袖に激しく皺がよっている。見れば、こめられた力のせいで、俺の腕も震えるほどだ。 慌てて指を放そうとしたが、どうしたわけか、強張ってしまって動かない。 こちらの混乱に気づいたらしく、旺はゆっくりと片方ずつ、自分で俺の指を引き剥がした。 咄嗟に奴の手を振り払い、両手を自分に引き寄せる。そこで初めて、パジャマの胸元が大きく開いているのに気づいた。汗で掌が滑るのだ。 「な……、なんだ、これ」 急いで左右の襟を引き合わせ――同時に、それがひどく女じみた仕種に思えて赤くなる。 「なにすんだよ、旺!」 旺はわざとらしいほどの驚きを見せた。 「俺? 俺じゃないよ? どうして俺が泰ちゃんの服を脱がさなきゃならないんだよ」 奴の言葉に、俺は耳まで血を上らせた。 「いいから、どけって」 旺はゆっくりと馬乗りになっていた俺の上からどいた。 俺は暑さのせいか、上掛けまで剥いでしまっている。旺は畳の上からそれを拾い上げると、綺麗に広げて、寝ている俺の腹に被せた。その仕種が、ますます俺を逆上させる。 「じゃあ何やってたんだよ、旺っ!」 「何だか知らないけど、俺に当たるのはやめてほしいな」 旺は無表情に俺を見下ろした。 「自分が山の中で倒れたのは覚えるだろ? 晴子ちゃんが助けを呼びにきて、俺と凡範伯父さんが迎えに行ったんだ。目を覚まさないから担いできたよ。熱があるってさ」 確かに、ここは岡の家だ。部屋には三人の荷物が散らばっている。 「みんなでお茶飲んでたんだけど、母さんが泰ちゃんのこと見て来いって言うからさ」 俺は上掛けの端を握りしめたまま奴の顔を見上げる。庭へと続くガラス戸から、陽光が差し込んで、旺の顔を半分照らしている。 半分光、半分闇。ついさっき、よく似たものをどこかで見た。 「来たら、うなされてたよ。悪い夢でも見てた?」 「だからって、叩くことないだろーがっ」 旺は忍び笑いを洩らした。 「ヘンな声上げてるからさ。母さんたちに聞こえたらまずいと思って」 俺は咄嗟に、枕元に脱いであったTシャツを掴んで投げつけた。 旺の腹に力なく当たって落ちる。 「布団だってちゃんとかけてた方がいいと思うけどな」 奴に下半身を指さされ、俺の狼狽は頂点に達した。 自分の反応に気づかれたのかと思うと、身震いするような怒りと恥ずかしさを覚えた。 「旺っ、てめえっ」 乱暴に体を起こすと、またひどい頭痛がした。片手で額を押さえつつ、涙目で睨みつける。 「お前がやってんだろう!? あの時みたいに、お前がけしかけてんだろーがっ!」 旺の顔が歪んだ。 そんな顔をすると、ふいに幼く見えた。子供の頃、一晩だけ泊まりにいったあの夏の夜、俺は同じ言葉で従兄弟をなじったような気がする。 なにか言おうと奴が口を開いた時、晴子が廊下側から入ってきた。 「泰生さん、起きたの……」 険悪な空気を一目で見抜き、 「どうしたの?」 と小さな声で聞く。 「うるさい、でてけ」 俺は混乱していた。 怒鳴られてびっくりした晴子は、 「また喧嘩?」 と旺に尋ねた。 「熱があるみたいでね」 その冷たい口調は、意識してか、彼の姉そっくりだった。 カッとし、枕を掴む。 「きゃあっ」 悲鳴を上げる晴子を連れて、旺は慌てて逃げだした。 二人が行ってしまうとすぐ、俺は布団の上に突っ伏す。 どーしちまったんだ、俺は。女みたいにヒステリーを起こして……。 またあの、頭痛が甘くまとわりつく。 俺は待った。 悪夢が去ってくれるのを……。 熱が去り、頭が冷えて、もとの落ち着きを取り戻すことを。 それなのに、体の方は一向に静まりはしないのだった。 |
| 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / NOVEL / HOME |