| 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / NOVEL / HOME |
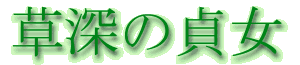 -6- 美奈子が最上級生だったという記憶があるから、あれは小五の夏だろうか。その頃まだ近所に住んでいた従姉弟の家に一人で泊まりに行ったことがある。 旺が俺と一緒に寝たいと言ったので、二段ベッドの上に寝ていた姉は両親の寝室に行き、代わりにそこへ俺がもぐり込んだ。 自分のベッドを明け渡すことを、美奈子は当時の俺に理解できないような言葉を使って嫌がったが、両親に説得され、何より弟の我が儘には弱かったようで、枕とシーツは客用を使わせることでしぶしぶ承知したのだった。 別に旺と上下に寝たって楽しくもなんともないが、そこはそれ、憧れの少女の布団で眠ることには少し後ろめたいような嬉しさがあった。 何やら一生懸命に話しかける旺に生返事を返しながら、俺はうとうとし始めたんだと思う。 閉じた瞼の前を、ふ、と何かが横切る気配がした。 「あっ、ついて来ちゃった」 間違いない、旺は小声だが、はっきりとそう言った。 その言葉にこめられた切羽詰まった響きに、俺は少しだけ眠りの世界から引き戻された。 また何かが素早く走り抜ける気配がした。 「旺、うるせーぞ」 眉をしかめて、ぶん、と振った手首を何かに掴まれた。 ここは、二段ベッドの上段だ。旺は間違いなく下にいる。俺は、思わず目を開け……ああ、確かに目を開けたと思う。だが、そこからの記憶がどうもはっきりしないのだ。 俺の悲鳴に叔父さん夫婦が飛んで来たこと、美奈子の前で男としてのプライドもかなぐり捨て、家へ帰ると泣きわめいて、夜中に自宅まで送り届けてもらったことをぼんやりと覚えている。 俺が旺の家に遊び行くことは二度となかった。学校や外で会うことすらなんとなく避けるようになり、そのうち彼らは社宅を出て隣県に引っ越してしまった。 俺は縁側に腰掛け、ぼんやりと庭の草木を眺めながら、こうした子供時代のことを思い出していた。 その日は朝から小雨が降っていた。於賀へ来て、初めての雨だった。 それはどこか心地よい景色だった。あのどぎつい蛍光色の緑は、霧雨の中、しっとりと深みを増し、いやらしいほどの自己主張は鳴りを潜めている。人間の足で踏んでも踏んでも頭をもたげてきた生命力が、糸のような細い水滴に打たれ、おとなしく頭を垂れている様は、どこか感動的ですらあった。 「泰ちゃん、電話」 ゆっくり首を回すと、廊下へ続く角の暗がりにGパンの長い足が見えた。 「智晴君から」 俺は黙って立ち上がると、奴の側を通り過ぎた。 そのまま二、三歩過ぎてから、ふと振り返る。 「お前、なに?」 オマエハ、イッタイ、ナニ? こちらを向いた旺の顔の部分は真っ黒い影となり、当然返事もなかった。 「明野はやっぱり殺されたんだと思う」 岡家の居間で俺がそう言うと、隣に座って煎餅をかじっていた晴子は疑わしげな顔をした。 「誰に?」 「決まってんだろ、セツ婆さんにだよ」 「どーしてよ、なんで?」 俺は返事につまり、少し考えて、 「婆さんも庄右衛門が好きだったんじゃないのかな」 と答えた。 いったんそう思うと、それが一番もっともらしく感じられる。 「うん、きっとそうだ。庄右衛門てのは金持ちのボンボンだろ。死ぬまで女遊びが激しかったってんだから、於賀で村の女に手を出してたって不思議じゃない」 「動機は嫉妬ってこと? でも、それってちょっと変じゃない? だって、結局、明野も捨てられたんでしょ? なんで殺す必要があるの?」 晴子が鋭く突っ込む。 「うーん、じゃあ、こういうのはどうだ。庄右衛門は明野を捨てたんじゃなくて、明野が死んだから仕方なく於賀を出たんだ。つまり明野は相思相愛のうちに殺されたんだってこと」 「それじゃあ、セツ婆さんの言ったことと違うじゃない。明野は庄右衛門が帰ってくるのを待ってるうちに死んじゃったって……」 「だから、それは嘘ついてんだよ」 俺は、苛々と言った。 そんなあ、と晴子は首を振る。 「自分の都合のいいとこばっかり鵜呑みにして、そうでないところは嘘だっていうの? そんなのおかしいよ。セツ婆さんの言うことを疑っちゃったら、どんな仮説だって立てられないじゃない」 「だけど!」 俺は思わず大声をあげていた。 「他の誰に聞けってんだ? 村の年寄り連中に尋ねたって、ぼけてんのかなんなのか、皆ちっとも要領を得ないじゃないか」 そうなのだ。ここ数日、俺と晴子はセツとほぼ同年代と思われる老人たちを訪ね、明野に関する話を聞こうとしたのだが、さっぱりうまくいかなかった。 「明野」 という名前に唯一懐かしそうな反応を示したのは清とかいう爺さんだったが、達者そうな口ぶりも、俺たちがセツ婆さんと会ってきた、と言い出すまでだった。 「明野が庄右衛門を待って死んじまったと、セツさんが言うたんかね」 そうだと認めると口をつぐんでしまい、後はウンともすんとも言いやしない。 明野は殺されたのか、なんて尋ね方は勿論こちらもしなかったけど、それでもいつどうやって死んだのかくらい、教えてくれても罰は当たらないはずだ。忘れたふりをしていたが、あれは絶対に何か隠しているのだ。 「くそっ、あの爺い、婆さんに借金でもあるのか……。待てよ、もしかしたら共犯だって可能性もあるぞ」 俺は後頭部をかきむしった。 「泰生さん!」 強い口調に顔を上げると、晴子が珍しくマジに怒った顔をしてこちらを睨んでいる。 「ちょっとやめてよ、ここはあたしの村なのよ。そりゃたいして親しくはないけど、セツ婆さんだって、清さんだって、同じ村の人なんだから!」 「同じ村の人なら何やったって許すのか? 明野が殺されたんなら仇をとってやりたいと思わないのか? それとも明野は余所者だからいいって……」 「泰生さん!」 晴子がだん、とちゃぶ台を叩いたので、湯飲みが倒れ、煎餅を盛った菓子皿が揺れて音をたてた。 「泰生さん、ここんとこちょっと変だよ。なんでそんなに明野、明野って言うの? 殺されたってなによ、そんなこと言ってるの泰生さんだけじゃない。旺さんも言ってたけど、まるで明野さんにとり憑かれ……」 「旺だって!?」 俺は思わず立ち上がっていた。 「やっぱりあいつか! お前、あいつに何か言われたんだろう。そうやって二人で俺のことを影で笑ってるんだな。ちくしょう、あいつ、こそこそしやがって……!」 「馬鹿!!」 左頬にぴしゃっときた。 「バカバカ、なによ、心配してるだけじゃない。あたし、もう帰る!」 晴子はパッと立ち上がると、そのまま物凄い勢いで部屋を飛び出していった。廊下を走って行く音が遠のき、続けて玄関で乱暴に戸が閉められる音が響いた。 「今の、晴子ちゃんかね?」 ガレージに干してあったらしい洗濯物を抱えた頼江伯母が、廊下を通りすがりに首を振る。 晴子が去ったあとの室内は、妙にひっそりと寂しく、俺は自己嫌悪を感じていた。 確かに俺は変だ。 でも変なのは俺だけじゃない。俺のせいじゃない。 いつもの場所に俺は立っていた。晴子と山に登ってから、覚えている限り、夢の舞台はいつもここだ。 沼の真ん中で、月の光に青く照らされ、明野が仰向けに浮いていた。 両の瞳は静かに閉じられているが、口許はわずかに笑みを浮かべている。 静かな水面は波一つたたず、力なく投げ出された彼女の手足を支えている。 明野は薄い着物をまとっていたが、濡れているために体にぴたりとまとわりつき、見ようによっては全裸よりも煽情的だった。 上を向いても形のよい胸の先が、固く張り詰めているのがわかる。 俺は引き寄せられるようにそのふくらみに手を伸ばした……つもりだったが、実際に動いたのは、体の両脇に垂らした、水に浸った二本の腕だった。 俺は濡れた腕で、自分の胸を抱きしめた。肘の柔らかい肉に、固くなった乳首があたる。 体が熱い。 体が痛い。 ホタル沼の水面に一人ただよい、丸く白い月を見上げながら、俺は孤独と満たされない欲望に泣いていた。 男が欲しかったのだ。白く丸い乳房に、力強い男の手が。 脚の間を割って入る、固く締まった男の腰が。 ――泰ちゃん。 そう、男の優しい声が……。 「泰ちゃん、駄目だ、母さんが起きる」 耳元で囁かれ、俺はハッと目を開けた。 月夜の明るさが不意に闇にとって変わった。それでも、今自分がなにをしているのかはすぐにわかった。 俺は旺にのしかかり、その喉元に唇を寄せていた。 手は相手の体をまさぐり、足が絡み合っている。 旺をなじれる状況ではなかった。夜半に従兄弟の布団に忍び込んでいるのは俺の方だった。 驚きのあまり身動きもできず、ただ言い訳のように繰り返す。 「俺じゃない、俺じゃないんだ……」 このままでは気が狂う。 明野は恨めなかった。なぜか、旺も。 俺の恐怖はそのままセツへの憎悪となって燃え上がった。 |
| 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / NOVEL / HOME |