| 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / NOVEL / HOME |
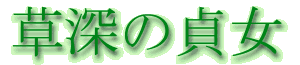 -7- 明野の仇を討つのだ。セツをなんとかしなくては、彼女は浮かばれない。 明野の望みを叶えてやれば、俺は解放されるだろうという確信があった。 彼女の願いは、おそらくセツが過去の罪を認めること。自分が沼に沈んでいることを、俺だけでなく、皆に知ってほしいのだ。もうかなわないながらも、きっと誰よりも、庄右衛門に……俺はそんなふうに考えていたのだった。 ところが、運悪く翌日は蔵の掃除に駆り出されてしまった。ここに来たそもそもの役目を無視するわけにはいかないから、仕方なく大人の指図通り、散らかった行李や木箱を運び出す。 ホコリに弱い旺も前回同様、口許にハンカチを巻いて果敢にがらくたに挑戦している。俺としては昨夜のことがあるから屋敷で休んでいてもらった方が良かったのだが。 なるべく顔を合わせず、口もきかない。何も今日に限ったことではなく、ここ数日の俺たちはこんな感じだ。だが、何故かこの日は、横顔に奴の視線を感じることが多かった。 それも、どこか気づかわしげな……気のせいかもしれない。 どちらにしろ、俺には旺にかまっている余裕はなかった。 片付けが済んだのは、もう夕方だった。順番に風呂へ入り、汗を流してすぐに夕飯となる。 俺は手早く済ませると、気づかれないようにそっと屋敷を抜け出した。風呂上がりに伯母さんが出してくれた浴衣を着ていたのだが、急いでいたのでそのままスニーカーを履く。 今日も午後に少し雨が降った。足もとに絡みつく雑草は濡れている。 山の端に覗く白い月を横目で見ながら、俺は赤いポストの立つ館林商店までやってきた。 店は閉まりかけていたが、既に顔馴染になっていたおばさんは、快く晴子を呼び出してくれた。 短いワンピースにサンダルをつっかけて出て来た晴子は、浴衣姿の俺を見てちょっと足を止める。だが、すぐに 「どうしたの?」 と笑顔を浮かべた。 「昨日は悪かったよ」 「あ……ううん、あたしこそ……」 俺の殊勝な態度に晴子は少し戸惑ったようだ。 「いろいろ考えたんだけど、確かにちょっと結論を急ぎ過ぎたかな、って反省したよ。それに晴子にも言われた通り、明野のことばっかりに構うの、やめたいんだ。ここにももうそんなに長くいられないし……」 「え、そうなの?」 晴子ががっかりしたような声を出す。 「うん、あと二〜三日かな。だから喧嘩はやめよう」 俺の言葉に、晴子はうん、と素直に頷いた。 「あ、上がる? もう夕飯済んだ?」 家に戻ろうとする晴子の腕を掴む。 「それでな」 俺はそのまま晴子を少し離れたところまで引っ張って行った。 「ケリつけるためにも、もう一度だけ、セツ婆さんと話がしたいんだ。いいだろ?」 「いいだろ、って何が……」 そこでようやく晴子は、俺が穏やかに話そうと努めながらも、顔に汗を浮かべた、切羽詰まった様子であることに気づいたらしい。 「呼び出してほしいんだよ、婆さんを」 「よ、呼び出す……? どこへ?」 俺は答えた。あそこしかない。ホタル沼。 「わ、わかった。一応言うだけ言ってみるけど、でも……」 「俺の名前を出すんだ。大野木隆志の孫が明野のことで話があるって言うんだ。絶対来るさ」 「泰生さん、い、痛い、手……」 弱々しく身をよじる晴子をいったんぐっと引き寄せ、「早く頼むよ」 と命じてから、突き飛ばすように手を放す。 「まさか、いま……!? もう暗くなるよ。それに泰生さんには一人であそこまで行くのは無理よ」 「俺のことはいいんだよ!」 俺は怒鳴った。晴子はびくりと体を縮める。俺は滴る額の汗を乱暴に拭い、その手を 「行け」 という意味をこめて右へ振った。 晴子はしばらく俺の顔を眺め、やがておずおずと、すぐに駆け足でその場から消えた。 晴子の心配は杞憂だった。 迷うだって……は! どうして俺が迷うことがあるだろう。 俺は静かな水面を見下ろした。この沼の底に、明野が眠っている。セツに殺された明野の体が。泥に埋もれ骨と化していても、彼女は美しいに違いない。 もうすぐだ、もうすぐ、俺があんたの願いをかなえてやる。 俺は導かれるようにして、ここまで辿り着いた。尊大な草木も皆、頭を下げて道を開ける。 いま、この山の、いや於賀の緑はすべて俺の味方だった。 木々を渡る夜風までが、媚を売るように客の訪れを告げる。間もなく、草むらをかき分けるようにして、疲れた様子の老婆が喘ぎ喘ぎ姿を現した。 村人には慣れた道だということだが、流石にその歳にはきついのか、髪が乱れ、着物の襟元が崩れている。雨上がりの濡れた下草に滑ったのか、裾だけでなく、着物の前も泥で汚れていた。 どうやら履物は草履ではなく、ズック靴のようだ。俺と同じ。ちぐはぐで、みじめだ。 俺は声を出さずに笑った。 足を一歩踏み出すと、セツははっと顔を上げた。その所作にふと気づく。 セツはかなり目が悪いようだった。山村の屋敷で会った時にはわからなかった。 盲の身でここまで来たのか。あの道ともいえぬ道を、何度も登り慣れていなければできないことだった。 哀れという感情はまるで起こらなかった。それどころか、目の前にしたセツの姿に心は制御を失い、強い憎しみだけが怒濤のように溢れ出す。 しわくちゃの、ちっぽけな婆。こんな女のために、こんな女のために……俺は。 この女がいなければ、こんな寂しい場所で、当て所なく待つこともなかったのだ。この女があんな成り金と結婚などしなければ……。 震える手が彼女に伸びた。 「だ、誰だい……こないだの坊じゃないのかい」 相手の怯えた口調が心地よかった。涙が出そうだった。 俺は勝ったのだ。 庄右衛門は戻って来るだろう。 もう二度と邪魔はさせない。 その時、真っ直ぐこちらに向けられた老女の見えぬ両眼が、俺の一部を正気に戻した。のぼせた頭が冷えていくのと同時に、視界が歪みだす。 二つの小さな瞳がぐるぐると回りだし、いつの間にかそれは二組の、四つの目となってこちらの狂気を責めたてた。愕然とする。 何てことだ、これは……。 この目、この瞳! 明野は、セツに殺されたのではなかったのだ! それどころか……。 俺はその時、真実を――少なくとも、真実の一部を悟った。 だが、もう遅い。 「ハア、ハア……」 俺は息を荒らげ、老婆の体に襲いかかった。 老いた二つの、皺に埋もれた、セツのやぶにらみ……。俺は、よく知っていた、知っていたのに。こんな風に片方が僅かに逸れた、宙に向けられた瞳を。夢見るようなまなざし――。 「やめ……やめろ、明……」 持ち主の意志を裏切り、両手がセツの首に巻きつく。俺は恐ろしさに震え上がった。力を込めた腕がぶるぶると痙攣し始め……。 「やめてっ、泰生さんっ!」 突然、背後で葉擦れの音がして、小柄な体がしがみつくようにぶつかって来た。 同時に痛いほどの力で両手首を握り込まれる。 「落ち着いて。のみこまれちゃ駄目だ」 耳元で奴の声がした。言葉使いは落ち着いていたが、それでもほんの少し上擦っているのがわかった。 「あ、あきら……」 「晴子ちゃん、婆さんを頼む」 旺に言われて慌てて俺から離れ、晴子はセツの方に飛びつく。 「駄目っ……指が、すごい力で……!」 必死になって俺の指を外そうと引っ掻くが、歯が立たないようだ。 晴子に協力したいのは山々だが、今は俺自身にもどうにもならない。これでも、これ以上力が入らないよう、必死で意識を保っているのだ。 「泰生さん、お願い、放して、放してよぅ。ごめんなさい、怒らないで。あたしが心配になって旺さんを呼んだの……いやっ、しっかりしてよぉ……」 晴子はわけのわからないことを喚きながら、終いには俺の腕ごとセツを抱え込んで泣きだしてしまった。 セツの方はもう目を閉じ、ぐったりして俺の手の先にぶら下がっている。 もう死んでしまったのではないだろうか。 腕だけでなく、全身が震えだした。 「旺…旺……俺、怖い……」 「大丈夫、大丈夫だから」 優しい声だった。 俺の頬にぴたりと寄せてくる髪から、奴の汗の臭いがする。 見なくとも、旺の表情がわかるようだった。きっと、この夏、会ったばかりのあの顔だ。汽車の中で、俺に懸命に話しかけていた旺……。穏やかで、少し緊張していて。いつから取り澄ました顔ばかり見せるようになったんだっけ。俺に会えた喜びを隠さなかった旺……。 「旺…助けてくれ……」 俺は乾いた喉を締めつける、指先の恐ろしい感触から逃れるように、体を逸らして旺の方に傾けた。 すると旺は手首を握っていた片手を放し、俺の頭を抱え込んでゆっくりと髪を撫でてくれた。 「大丈夫、大丈夫。絶対助けてあげるから」 「旺、旺、こんなの俺の意志じゃない、俺じゃないんだ」 「わかってる、俺が悪かった。俺にはわかってたのに。でも、まさかこんなことになるとは思わなかった。ごめん」 旺はそこでいったん口を閉じると、 「さあ、二人で楽になろう」 と囁いた。 その瞬間、奇妙な形に体が捩じれた老婆も、取りすがって泣いている少女も消え失せ、世界は俺たちだけになった。 暗がりの中、優しい沈黙を守る緑に囲まれ、俺は旺に抱きしめられて立っていた。 「さあ考えよう。泰ちゃん、何がしたい? 何が望みなんだ?」 俺に語りかけているようで、旺が尋ねているのは俺ではなかった。俺の中の明野だった。 「セツが憎い、殺したい」 『殺す』という言葉を口にした途端、新たな涙が流れた。俺はずっと気づかなかったのだ。憎しみは確かにあったが、セツを消してしまいたいとまでの明野の気持ちには……。 意識した途端、また生々しい現実が戻って来そうになる。 だが、セツの方を見ようとした俺の頭は、旺の手でがっちりと押さえられていた。思わず見上げると、奴は 「見るな」 というようにそっと首を振った。 「殺したい? なぜ? どうしてそんなにこの人が憎いんだ?」 「それは……セツが殺したから。俺を……明野を」 旺はもう一度首を振る。 「違う。もうわかっているはずだ。セツは明野だよ。彼女が本物だ」 そうだった。俺はあの瞬間気づいたのだ、老いた女の両の瞳に、好きな女の面影を。 明野は、真実を隠していた。 嘘をついたのではない、だが、のぼせ上がった俺を、巧妙に導いたのだ。 それでも、恨む気にはならなかった。こんな目にあってもまだ、どうやら俺は明野のものだった。 それは、美奈子に対する憧れとは違う。そして、いま俺を腕に抱いているこの男に対するものとも。 見ろよ、旺でさえ、こんなに簡単に俺を所有している――。 「でも、明野を殺したも同然だ。セツは庄右衛門を待たずに成り金と結婚した。一途だった明野の思いを捨てて」 「そうかな」 旺は俺の髪に指を差し入れ、そっと梳き始めた。地肌を滑るその動きに、背筋が震える。 「明野を殺したのがセツなら、明野を生んだのもセツだ。セツは庄右衛門を愛していたよ。でも待たなかった。その理由は彼女にしかわからない、いや……」 旺は手をとめて、 「泰ちゃんにならわかるのかな……」 と言った。 そして、顎に指を滑らせ、擦るようにそっと動かした。俺は思わず目を閉じ、軽く頭を仰け反らせた。 「セツが捨てた庄右衛門への思いは、明野という形で残された。でも、その時の明野はまだ小さな、固い種子でしかなかった。それを東京へ持っていったのは俺たちのお祖父さんだ。お祖父さんは兄の恋人に憧れを抱いていて、その思いを昌弘伯父さんに伝えた。 蒔かれた種は、伯父さんが於賀を訪ねた時に発芽した。セツは伯父さんに明野が死んだと告げた。愛人を待てなかった自分の代わりに、一途なまま死んだ美しい貞女を造り上げたんだ」 旺の指先が偶然のように唇に触れると、思わず体中の力が抜けそうになった。そこでハッとする。旺のもくろみに気づいて。 「言ってみれば明野という幻は、セツが生んで、大野木家の三人の男が育てた。そしてとうとう、泰ちゃんの体を借りて、明野は花開いた。 綺麗な花だね……泰ちゃんが魅かれたのはよくわかるよ。でも、毒の花だ。あってはならない花だ。俺たちの力で、枯らせてしまわなくては……」 暗がりの中で、奴の顔が近づいてくるのが見えた。でも俺には動けなかった。薄く唇を開いてそれを待った。 「う……」 俺の正気がどこかへ押し流されていく。旺は救ってあげると叫びながら、俺を崖の上に追い詰めている。旺、旺……。俺はどうなるんだ。俺たちはどうなってしまうんだ……? 二人の唇の間で、濡れた音がする。 指の背で、触れるか触れないほどの微妙さで俺の頬を撫でながら、旺は舌を抜いてそっと囁いた。 「さあ、もう一度聞くよ……。望みはなんだい? こんなお婆さんなんか放っておけばいいじゃないか。本当に求めているものは別にあるだろう? 長い間待っていたのは何のためだい」 優しい笑みこそ浮かんでいたが、揺れる瞳から旺の押し殺した緊張感が伝わってくる。 奴は俺を助けるために、明野を開放しようとしている。その為に、俺の中の女を引き出そうとしている……。 ああ、俺は今になって、凡範伯父さんの言葉の意味がわかった。 『家の家系じゃ甥が伯父に似るもんだ』 似ているのは誰だ? 俺はあの時、単に旺が親父に似ているだけだと思った。だが、親父も自分の伯父に似ているのだ。 昔、訪ねて来た大野木昌弘にセツは嘘をついた。本当のことは告げられなかったのだ。彼の伯父――つまり、庄右衛門の面影を引き継いだ若者には。 庄右衛門から親父へ。親父から旺へ。伯父と甥。そしてその甥。三人の男の容貌はよく似ていた。 つまり、つまり――ああ、俺の中の明野が悦びに震える。 旺は、庄右衛門にそっくりだった……。 「さあ、何がしたい……?」 明野という花を精いっぱい咲かすのだ。枯らしてしまうために。今夜だけ……。 俺には旺の言いたいことがよくわかった。 腕から力が抜ける。視界の隅に、解放されたセツと、そして彼女に被さるようにゆっくりと倒れていく晴子の姿が見えた。 俺は痺れたようなその手を、長い長い間待ち続けた男の首筋にまわした。 「お前が欲しいよ……」 |
| 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / NOVEL / HOME |