| 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / NOVEL / HOME |
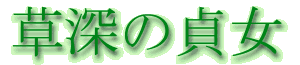 -3- 俺たちの歩く、周囲の何もかもが緑と黄緑色だ。きみどりいろ……絵の具のチューブに書いてある文字の色じゃない。生きているのだ。何もかも光り輝き、ざわめいている。 なんだか、息苦しい。 カッと直射日光に照らされたアスファルトが唯一白く続く。周囲をうめつくす夏の稲穂。そしてどちらを向いてもその行く手には、濃緑の木々が壁のように、延々と山を形作っている。於賀は小さな盆地なのだ。 一昔前の田舎が舞台になっているアニメがヒットして、俺も集団で見に行った。嫌というほど緑が溢れていたが、木も草も田畑もそこでは慕わしいものだった。俺たちにさえ、どこか懐かしく思える心穏やかな風景だった。 だが、本当の夏の緑というものは、あんなに爽やかで優しいものとは思えない。このどぎつい蛍光色、道端の雑草でさえ、我も我もと自己主張を競っている。 同じ村の中だというので軽く見て、帽子をかぶってこなかったせいか、暑さで頭がぼんやりする。それなのに、風になびく稲の波が、目を逸らすことを許さない。 ――それともこのクソうるさい、蝉の声のせいなんだろうか。頭の中にびっしりたかって鳴いてるようだ。 少し遅れがちな俺に気づかず、土地っ子の晴子と、これまたいつもと変わらぬ様子の旺が何かを話しながら歩いている。 ぽつぽつと見えるのは、今風の新築の家だし、庭先の車も都会と変わらぬ洗車の行き届いたセダンだ。だが、東京では肩身の狭い植物が、ここでは動物を凌いで主役なのだ。 渋谷の人込みには慣れっこの筈なのに、草木の生命力は俺みたいな都会っ子には毒なんだろうか。 酔ったのかもしれない。この緑……。鮮やかすぎる……。 俺はぼんやりと、額に吹き出た汗をぬぐった。 親父のしてくれた打ち明け話には、俺が期待していたほど、特に謎めいた、衝撃的な部分は何もなかった。ただ、親父がちょうど俺くらいの年に、話に聞いただけの女性に憧れてたまらずに旅に出てしまったという告白は、意外でもあり、何だか妙に微笑ましかった。 「なんていうか……俺も若かったからなあ。小説の登場人物とか、そういうのに一途に入れ込んだ時代があったのさ。夢想家っていうか……」 遠く電話線を隔てても、親父が照れて赤くなっているのがわかった。 聞いてるこっちも気恥ずかしいが、今でも空いた時間は文庫本を手放さない親父の青年時代が、ほんの少しだけ想像できた。 「明野さんか……古い話だなあ。お前、一体どうしてそんな話を聞き込んできたんだ?」 咎める気配はなく、しみじみ懐かしい、という口調で親父が言った。 親父は小さい頃、庄右衛門の恋人だった明野という女性の話を、祖父さんから何度も聞かされて育ったらしい。 「慶子も一緒に聞いてたように気がするが……覚えていないところをみると興味がなかったのか、それともやっぱり俺だけが聞いていたのか。流石に娘にはしにくい話だったのかもしれないなあ」 祖父さんはまだ親父が未成年の時から晩酌には付き合わせていたらしいが、酒が入ると必ず故郷の女の話をしたという。 明野はやっぱり、この土地の女だったのだ。 「正確には、於賀の人じゃない、隣町で座敷に出ていたそうだよ。江戸時代に街道が通っていた名残でね、当時はまだ結構大きな町で、旅籠が沢山あって賑やかだったそうだ。 親父は言ってた。目が覚めるように綺麗な人だったって、酔うと、何度も繰り返していた。庄右衛門の伯父とは年が離れているから、親父はまだ子供だったらしいけど――俺は一度聞いてやったよ、初恋だったんだろ、って。親父は笑いもしなかった。そうだとも言ってくれなかったけどな。その時からかな、俺がその女に興味を引かれるようになったのは……」 「明野って人は、その、捨てられたの?」 「放蕩息子が水商売の女を弄んで捨てた、という関係を想像しているのなら、それはちょっと違うらしい。俺も最初はそう思ってたんだけど、絶対にそんなことはない、と親父はムキになって否定した。庄右衛門の伯父も、彼女とは別れたくて別れたわけじゃないらしい。東京で縁談話がおこったらしいんだな。まさか女を連れて行くわけににも行かなかったんだろう」 それが、捨てたってことじゃないのか? 俺がそういうと、親父も小さな唸り声をあげた。 「まあな、そこのところは俺も納得できなかったよ。当時は時代も違ったんだろうし、親戚筋に説得もされたんだろうが。でもそのあとのご乱行があるからな。俺は実は庄右衛門の伯父には会ったことがないんだ。だから、どうして親父がああも自分の兄貴を庇うのか、最後まで理解できなかったね」 電話の向こうで、何とか言うお袋の声がした。日曜の朝から息子相手に長電話なんて、珍しいからだろう。俺は、どちらかというと無口な親父の、普段にない饒舌を快く感じていた。 「別れた後の明野は、於賀に家を貰って独りで住んでたらしい。庄右衛門の伯父にしてみれば、いずれは迎えに来るつもりもあったのかもしれないが」 でも、結局行かなかったんだ、と親父が続けようとした言葉を、俺は察した。 「それで、親父は、会えたの?」 と、俺は、一番聞きたかったことを尋ねた。 「於賀に会いに来たんだろ? どうだったんだ?」 「もう死んでた」 親父は簡潔に言った。 「俺は、自分が何を期待して行ったのか、今でもよくわからないね。単純に計算したって、相手はもう五十すぎのおばさんだ。それにもう於賀にはいない、と考える方が当然だったかもしれない。たぶん……薄幸の美女を実際に見たい、とかそういう興味本位の動機だったんだろうな。勝手なもんだよ」 親父がちょっと口を噤んだので、俺は例のことを告白することにした。 「親父、俺、見つけたんだ、蔵の中で」 「何をだ?」 「写真だよ。古い写真。頼江伯母さんにみせたら、明野さんだって。裏にも書いてあった。吐月楼の明野って……」 「とげつ……そう、そんな場所だった、聞き覚えがある」 親父は、そう言うと、驚いたように黙ってしまった。そして、しばらくの沈黙の後、囁くように言った。 「蔵に写真があったって? そうか、どうだ? 俺は見たことがないんだ。どんな人だった?」 「美人だよ。祖父さんが言った通りだ。俺くらいの年で、着物を着ている」 俺は手にした写真を見ながら一生懸命説明しようとした。でも上手く伝わらなかった。 「お前が写真をね……、それで興味を持ったのか? 親子三代、何の因果やら」 苦笑しているようだ。 「なあ、親父、明野さんはどうして死んだんだ? 誰に聞いたんだよ、凡範伯父さんか? 確かもう頼江伯母さんもいたんだよな」 「まさか。新婚の従兄弟に故人とはいえ父親の昔の女の話なんかするもんか」 「じゃあ、誰が教えてくれたの?」 親父は、またちょっと黙ってしまった。 「もしかして、お前まで聞きまわろうってわけじゃないだろうな」 「どうして? いいだろ。暇なんだし」 別に親父の許可なんてなくても俺は既にその気になっていたが、何とか認めて欲しくて頼み込んだ。 「お前がそんなことに興味のある性格だとは思わなかったが……」 「やっぱり親父の息子ってことじゃねぇの?」 俺がそういうと、親父なりに嬉しかったのか、当時話を聞いたという人のことを教えてくれる気になったらしい。 「だけどなー、名前なんて忘れちゃったよ。それにもう亡くなってるかも」 「頼むよ、親父」 「一人だけなら覚えてるけどな」 「いいよ、それで。まだ生きてるかどうかはこっちで調べるから」 俺は勢い込んで言った。 「岡の家は、戦後の農地開放で、もう以前のような力はなかったんだ」 全然関係ないことを話しだしたので、俺は面食らった。 「その頃の於賀を仕切ってたのは、村長の家で、東京で成功をおさめたとかで、随分なお大尽ぶりだった。まあ、成り上がりってことらしくて、岡の家では相手にしないというか、その家の話題には触れない、という感じだったな」 「その村長がどうしたんだ? そいつに聞いたってこと?」 「いや。話してくれたのは村長の奥さんだ。どういうきっかけだったか忘れたが、その人が俺に教えてくれたんだ、明野という女は死んだと」 俺は、親父の口調に苦々しいものを感じ取った。それでその理由を聞いてみた。 「嫌な女だったんだ。明野も、彼女に会いに来たという俺のことも馬鹿にしきってた。明野は死んで当然だったんだ、と言っていた。俺は若くて、かっとしたよ。でも何も言えなかったな。だって俺は会ったこともない女のことだったんだから」 「明野は、なんで死んだの?」 「さあ。病死だったんだろうな。はっきりとは言われなかったけど、俺はそう感じたから。馬鹿な女だ、と何度も言ってた。東京へ行ってしまった男の帰りを待って、こんな小さな村で死んでしまって」 俺と親父は離れた場所で二人、黙り込んだ。 「聞きたいか? 何だかあの女はまだ生きているという気がするな。殺しても死なないようなタイプだった。俺は辛くて、憎くて、東京に逃げ帰って、二度と於賀には行かなかったし、いつの間にかそんな話も忘れていた」 親父は山村、という姓を教えてくれた。大きな村ではないし、村長だったというんだから、簡単にわかるだろう。 軽く礼を言って電話を切ろうとすると、親父は 「なあ」 と俺をとどめた。 「その写真、貰ってきてくれないか。お前と話してたら、懐かしくなってな。一度くらい見てみたい。それに、あの女も言ってた。明野が美人だったのは確かだって。馬鹿だが綺麗な女だったと教えてくれた」 夢見るような口調は、青年時代に戻ったようで、俺には馴染みのない人のように思えた。不快だったわけではない。ただ、不思議な気分だった。 俺は親父に約束して、電話を切った。 「あ、ほら。あそこが山村さんの家だよ」 そう言って、晴子が指さした先には、黒光りする立派な瓦ののった、二階建ての建物があった。家の周囲をぐるりと土塀が取り囲み、その上にも濃い葉の繁った枝が覗いているので、屋根くらいしか見えないのだ。塀は元の色がわからぬほど汚れ、雨の染みで黒ずんでいる。 俺たちの場所からは門が見当たらず、周囲の開放された明るさの中で、唯一、人の出入りを拒んでいるような、閉鎖的な雰囲気を持つ屋敷だった。 近年に新築ブームがあったのか、於賀の家々は白やベージュの小綺麗なプレハブ系のものが多い。その中で、ちょうど村の両端にある岡家と山村家だけが――山村家は岡家よりはまだ新しくそれほどボロでもないが――、要石のようにどっしりと、時代という重力のバランスを保っているようだった。 ただし、どちらも孤高を持しているようで、印象は微妙に違う。それは中に住む人間の人柄のせいなのか、すでに岡家が時間の流れに逆らわず、いずれ於賀の歴史の一部として埋没する運命に任せている印象を受けるのに比べ、ここには、まだこの家を過去のままに生き長らえさせている何かが、しぶとく他人を拒んでいる。 「どうしたの?」 晴子の声に、俺はハッとして我に返った。 「いや、別に……ちょっと暑くて」 ぼんやりする頭を左右に振った。 「さ、行こうぜ。どっから入るんだ」 「もしかして、泰ちゃんの方が今更気後れしたんじゃないよね」 晴子と並んで立った旺が、笑みを浮かべて言った。 よくよく見れば、奴の額や首筋にも、汗の玉が浮いている。暑い筈だ。 なのに、何故だろう。旺の言葉がどこかひやりとするのは。 どうしてだろう。厭味な口調に俺の方が目を逸らしたくなってしまうのは。 昨晩まではそんなことはなかった。いや、今朝までは、旺のことなんて、気にもならなかった筈なのに……。 午前中、早速遊びに来た晴子に、俺は親父との会話の内容を話してやった。興味津々といった態度でそれを聞きながら、俺と旺の書いた系図を面白そうに眺めていた晴子は、山村の名を聞いた途端、あからさまに眉を八の字に寄せた。 「それって……セツ婆さんのことだよねえ」 「セツ?」 「山村セツっていうの。旦那さんの方はもう死んじゃって、子供たちも村を出ちゃってるから、今は一人で暮らしてるの」 「その旦那が昔村長だったっていう?」 「それは知らないけど……。でもあり得るかも。今でもずいぶん財産持ちだっていう噂なんだ。この村の土地だって、ほとんどセツ婆さんのものだって。あと、利子をとってお金を貸してるって聞いたこともあるし……」 「何だよ、於賀の人間のことならまかしとけ、って言ったくせに、はっきりしないんだな」 俺が言うと、晴子はだってぇ、と口を尖らせた。 「うちは雑貨屋だから、よく奥さんたちが噂話に集まるの。それに、お父さんが頼まれる買いだしの注文取って歩くの、あたしの役目だから、大概の家は知ってるんだけど……」 あそこの家だけは呼ばれたことないんだ、と晴子は続けた。近くに清(せい)さんていうお爺さんが住んでて、その人がセツ婆さんの用事を頼まれてくるの。他の人とはほとんど付き合いがないみたい。 「会ったことないのか?」 「そんなことはないけど。時々裏山を散歩してるし。こっちは挨拶するけど、向こうはね……」 晴子は朱色のノートを両手で持って、 「セツ婆さんに話を聞くの?」 と俺の顔を見上げた。 「嫌な奴なのか、やっぱり」 俺が親父の言葉を思い出して聞くと、晴子はますます困ったように鼻にしわをよせた。 「嫌なって、だって、知らないんだもの。それより話なんか聞いてもわからないんじゃないかなあ、と思って」 「ぼけちゃってんのか?」 わかんないけどぉ、と晴子はまた口を濁した。はっきりしないが、要するにセツってのは、村でも得体の知れない婆さんで、あんまり係わり合いになりたくないらしい。 俺は内心困ったな、と思った。 親父との電話は、俺の好奇心をますますかきたてた。 ガキのくせに兄貴の女に憧れた祖父さんや、思い出話を追っ掛けてこんな田舎まで来てしまった親父のようなロマンチストな部分が自分にあるとは思わなかったが、親父の言うように三代に渡る因縁があるというなら、のってやってもいい。 何よりも、写真の明野が俺を招いている。漂うような、独特の視線が、時間の隔たりを越えてこちらに据えられている。 俺は写真を片手に、晴子を説得しようとして口を開きかけた。すると、今まで聞いているのかどうかもわからないような様子で側で団扇を使っていた旺が、 「気が進まないなら無理しない方がいいよ」 といらぬ口を出してきた。 「お前には関係ないだろ」 又か、という感じだ。何だってこいつは、こういう言い方をするんだろう。しかも悔しいことに、俺の浮かれた気分に水を差す効果が十分あるのだ。 別に旺に一緒に遊んでほしいわけじゃない。だけど、従兄弟が乗り気になっていることにケチをつけたがるなんて、一体どういう了見なんだ? 「ううん、すごく興味はあるの」 晴子が慌てていった。また険悪になりつつある雰囲気を取り繕おうとしたのだろうが、まんざら嘘でもないのだろう。実際、山村の名前が出るまでは、俺を上回るはしゃぎぶりだったのだから。 旺は、団扇を動かす手を止めて、長い足で胡座を組んだまま、首だけをこちらに向けた。 「泰ちゃんも、晴子ちゃんも、どうしてそんなに昔のことにこだわるんだ? 変だよ」 整った眉の辺りに苛立ちが浮かんでいる。俺はちょっとの間それに見惚れ、それから慌てて言い返した。 「お前こそ、なんでいちいち煩いわけ? 変だと思わないのかよ」 「別に理由なんかないよ。ただ、そんなこと、つまんないだけだ」 旺が俺に喧嘩を売ろうというなら、それは成功したし、悪気がなかったとしても、俺の怒りは十分買った。 「お前、なあ!」 他の友人に言われたのならば、そんなに腹は立たなかったのかもしれない。だけど、旺が、新幹線の中で俺の機嫌を取るように一生懸命話しかけてきた旺が、俺にこんな言い方をするなんて、許せなかった。勿論、奴の存在をことごとく無視してきた俺の言い分としてはかなり勝手なものだったんだろうが。 「旺!」 俺の紅潮した顔を見ると、奴は僅かに、失敗した、という表情をした。だが、俺も晴子も驚いたことに、旺は一歩も引く気配を見せなかった。 「昔のことなんか掘り返して何になるんだ? 放っておいた方がいいと思うよ。でないと……」 旺はそこでいったん言葉を切り、俺と晴子の顔を眺めてから、ゆっくりと囁くように言った。 「ロクなことにならないと思うよ……」 俺は、ほんの一瞬のことだったが、背中がゾクッとして、振り返りたい衝動を覚えた。 晴子のノートを持つ手がびくりと震え、彼女も同じように感じたのだとわかる。 旺の能面のような顔は、こちらの反応に気づいたとしても、毛筋一本ほども変わらなかった。ただ、奴の右手の団扇が、思い出したようにゆっくりと動き出したので、俺は我に返ることができた。 「何、言ってんだ、お前?」 大丈夫、言葉は震えていない。旺に脅されたんだと思ったら、腹の底はさらに熱くなった。 「ロクなことにならないって、どういうことだよ。お前、何かやる気なのか」 「俺は何も」 というのが旺の返事だった。俺は別に何も。 そう言って、旺は俺たちから顔を逸らした。 オレハ、ベツニナニモ。 団扇の緩慢な動きに、旺の軽く垂れた前髪がなびいている。 「……わかったよ。お前は嫌なんだろ。付き合えなんて言わないから安心しろよ。だから、俺たちのことは放っとけってんだ」 「泰生さんてば……」 晴子が俺のシャツの裾を引っ張る。 「何だよ、先に喧嘩売ったの、こいつじゃないか」 「……東京に戻ろうかって考えてるんだ」 突然の台詞に、晴子はびっくりしたように旺を見た。 「俺がいない方がいいかも……」 「ああ、その方がいいね!」 俺は大して考えもせず、怒鳴った。 「ちょ、泰生さんっ」 「本人が帰りたいって言ってんなら、止める必要ないさ。こっちは清々する」 「ちょっと、やめようよ……」 晴子は困ってしまって、俺と、顔を背けたままの旺を交互に見た。 「お前が帰って、代わりに美奈子でも来てくれれば俺は……」 突然振り向いた旺の冷たい視線に、俺はびっくりして口を噤んだ。 「美奈子だって?」 「みなこって誰?」 晴子の質問には旺が答えるかと思ったのに、奴は何も言わなかった。 ただ、微かに顎を上げ、目を細めて俺を眺めると、口の端を歪めた。 「美奈子ね……」 「そう……だよ」 俺は気圧されないように、何とか言葉を続けた。 「だいたい、お前が来るなんて俺は思ってなかったんだからな。美奈子が来るっていうから楽しみにしてたのに……」 「美奈子、美奈子、美奈子、か」 「……なんだよ、美奈子がどうした」 「どうもしない。昔のままだと思っただけだよ」 旺は俺を見たまま、静かに、ゆっくりと息を吐き出した。 「なるほど、そういうわけか……」 旺の虹彩はすごく色が薄いのだ、ということに気づいた。真っ黒な誰かとは違う。光がちらちらしているのは、俺の背後の庭木が風に揺れているからなのか。彼の顔の中で唯一動きを見せたのはその部分だけだったのだが、俺は、奴がひどく怒っていると感じた。もしくはひどく……ひどく……わからない。 「なにが、そういうわけなんだ?」 沈黙に耐えられず、俺は尋ねた。 旺は、すぐには答えず、そのまま真っ直ぐに俺に視線をあてていた。そして、不意に笑った。 「別に、別に何でもないよ、泰ちゃん」 手にしていた団扇の存在を、思い出したように、放り投げる。 「旺?」 「ごめん……怒らせるつもりじゃなかったんだ。謝る」 「あ……ああ?」 「本当のこと言うと、俺もその写真には興味があるんだ。ただ……ただ、ちょっと心配しただけ。でも、もういい。そのお婆さんのとこに行くんなら、仲間に入れて貰えるかな?」 急に態度の変わった旺に戸惑っている俺に代わって、晴子が笑顔を見せた。 「もちろん、いいよ、ねえ泰生さん?」 あからさまにほっとした様子を隠さない。 「ああ、びっくりした。取っ組み合いでも始まるかと思っちゃった」 「取っ組み合い? そんなことしないよ」 旺がくすくす笑う。 あら、あたしするよう、弟と、と晴子が舌を出す。 その時、台所の方から 「とうもろこしをゆでたわよ」 という頼江伯母さんの声がした。 「取りに来てー」 晴子が元気に返事をして立ち上がる。旺も後に続いて居間を出た。 「みなこって誰?」 という晴子の問いに、姉だと答えてやっている。 後には、何が起こったのかまだよく理解できない俺と、机の上の写真。 ぼんやりとした俺の目に、旺が畳の上に投げ捨てていった、薄い青色の団扇がうつった。 何かとんでもない間違いを犯した気がする。それが何なのか知りたくて、置いていかれた俺は開け放たれた居間の中を見渡したのだけれど、誰もおらず、何も教えてくれなかった。 |
| 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / NOVEL / HOME |