| 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / NOVEL / HOME |
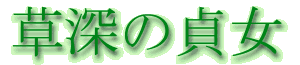 -1- 両の乳房を掴まれた痛みに、俺はたまらず目を覚ました。 柔らかなふくらみの上に、男の指一本一本の感触が痺れるように残っていて、痛かった。 はだけた浴衣の胸元に無意識に手を伸ばす。 その指が、つるんとすべった。 あれ、と思い、もう一度掌で確かめ、そこでようやく、ハッキリ目が覚めた。 がばっと上掛けを剥いで起き上がり、財布をなくした奴のように、懐を何度も探る。 ナイ。 何にもない。 握られるままに自在に形を変えたふくよかな盛り上がりもなければ、男に応えて強く突き上げた乳首も、今は微かな突起が指にひっかかるだけ。 当たり前じゃないか。俺は男なんだから。 胸なんてあってたまるか。 俺は闇の中で息を吐いた。その拍子に鼻筋を伝って落ちてきた汗を、舌を伸ばして舐めとる。 この塩辛さと同じくらいリアルだったのに、全部夢? 夢の内容は思い出せなかった。ほんの10秒前にいた世界が、もう俺のものじゃないらしい。 目尻が濡れているのに気づく。 夢だったなんて。子供みたいに夢を見て泣くなんて。 だって、実際にまだ胸の筋肉が痛かった。本当にさっきまで、誰かに触れられていたような……。 俺はぎくりとして、顔を左に向けた。 シン、とした闇だ。都会と違って、どこかから漏れてくる明かりというものがない。 いくら目を凝らしても決して馴れることのない暗がり。 だが、自分の隣に微かに規則正しい寝息がする。 そこに、従兄弟の旺(あきら)が眠っているはずだ。 俺は見えない闇の中に体を乗り出して、彼の様子を伺った。枕や布団の位置がぼんやりとわかる。旺は平和な眠りの中にいるようだ。 それでも信用できずに、しばらく息を止めて彼の呼吸音を聞いてみる。 乱れのない、静かな空気の音だった。きっと人形のように行儀良く、上を向いて寝ているに違いない。 俺は諦めて寝ることにした。従兄弟の向こうには、彼の母親が布団を敷いているはずだが、まさかあの叔母が夜中に寝ている甥の胸を触ったりするはずがない。 さっきはね飛ばした肌掛けを手で探る。昼間の直射日光は東京より熱かったのに、この肌寒さはなんだろう。汗ばんだ体がすうっと冷え始め、俺は耳をすませて扇風機のタイマーが切れていることを確認した。 肩まですっぽり薄い布団の中に入って、旺に背を向ける。 まだ疼く胸に軽く手をおいて、目を閉じた。 記憶はなくても、少なくとも続きを見たい夢じゃなかった。 囁き、懇願、汗。荒い息づかいがふと耳元によみがえり、俺は肌掛けをこめかみまで引っ張りあげた。 嫌だ。もう触るな。俺にもう触れるな……。 不思議なことに、眠気は安らかに訪れた。闇はすぐに俺を仲間に取り込んだ。 そうだ、知っていた。あれは悪夢ではなかったことを。敵ではない、何故なら俺自身が向こう側にいたから。 でももう一度渡りたい川じゃなかった。 俺の願いは聞き届けられて、そのまま朝までぐっすりと眠ることができた。 だから、俺は知らなかった。 おとなしく寝息をたてながら、旺の目が開いていたこと……。 |
|
一月ほど前、田舎の蔵に泥棒が入ったという話だ。 何でもトラックで乗り付けて、目ぼしいものは全部さらっていったと言う。 布団のカバーだけが剥がされて空き地に捨てられていた、と親父が話していたが、一体なんだってそんなことをしたのか、俺たち家族には見当もつかなかった。 父方の親戚といっても、うちの親自体、若い頃に一度行ってみただけ、という縁の薄い家だ。祖父母は若くして上京していたし、二人ともすでに他界している。 勿論、俺も弟の智晴(ともはる)も遊びに行ったことはないし、多分、一生行くことはなかったろう。於賀(おが)に住む伯父から電話を貰わなければ。 親父は知らなかったらしいが、蔵には何やら彼にも権利のある値打ちものもあったらしい。とはいえ盗まれてしまったのだから、財産も何もないのだが、この際蔵を処分するから親父に立ち合って欲しい、という話だった。 親父ははっきり言って迷惑顔だった。そりゃそうだろう、何か貰えるならまだしも、ガラクタ処分のために会社を休んで遠路はるばる出掛けていくというのは割に合わない。そこで、お鉢が回ってきたのが、暇な夏休みを持て余していた俺だった、というわけだ。 「どうせお父さんが行ったって何にもわかりっこないんだから、あんたでもいいのよ」 「ヤだよ、何で俺なんだよ、智晴に行かせろよ」 「智晴はクラブがあるって言うし。泰生(たいき)が一番暇なのよ」 「お袋が行けば」 「あんたが代わりにお父さんと智晴のお弁当作ってくれるの?」 抵抗したって、どうせ俺が行くことになるのはわかってた。俺がクラブ活動をしていないのは、デートの時間を惜しんでなのだが、休みに入る直前にふられて家でゴロゴロしている毎日を、嫌でも家族には知られてる。クラスメートに電話をしてあぶれ男になったことをわざわざ知らせるのも業腹だった。 「いいじゃない。田舎でのんびりしてくれば。あんたも来年は受験なんだから、そう呑気にしてられないでしょ」 「そんな僻地、俺一人で行けんのか。第一、会ったこともない人ばっかだぞ」 既に諦めの境地に達していたにもかかわらず、俺はまだぐずぐず言っていた。 「大丈夫、慶子叔母さん行くって。あそこも叔父さんは会社があるけど、子供を連れて避暑がてら、と言ってたわ。あんたも良かったじゃない。遊び相手がいて」 お袋のその言葉を聞いた途端、俺は気分は一気に浮上した。慶子叔母は、親父の妹で、昔は近所に住んでいたのでよく行き来もあった。俺と従兄弟の姉弟は年も近く、しょっちゅう一緒に遊んだものだ。 俺の目的は専ら一つ年上の美奈子だったのだが。 美奈子は、子供心に非常な美少女だった。女王様的な性格で、はっきり言うと俺も随分ひどい目に合わされたものだが、ませガキだった俺は、それでも喜々として後をついて行った。初恋だったと言っていい。 美奈子に会える。現金なもので、別れたGFのことは頭から吹っ飛んだ。 二年前、祖父の葬式で会ったのが確か最後だ。先に高校生になっていた美奈子は、妙に俺に対してツンケンしていたが、真っ黒で真っ直ぐな髪は、軽薄な茶髪女を足元にも寄らせないような雰囲気を漂わせていた。今はノリがいいこと、軽いことが女の子でも重要視されるから、美奈子みたいなタイプは流行らないんだろうけど、世間の思惑などどこ吹く風、といった姿勢の良さが俺にはどうしても無視できない。 別にモノにしたい、とかじゃないけど。従兄弟だし。でも、家で厭味を言われながらTVを見てるよか、あの美貌を近くで拝ませてもらってるほうが、どれだけマシか。 俺のこの夏の運命は、こうして決まった。 「こわ……」 梯子みたいな階段を一歩上がるごとに、古びた木材は瀕死の猫みたいな声を出す。ほとんど直角に近くて手すりもないから、俺は四つんばいになって蔵の三階へと登っていった。 「上がって右手に電気のスイッチがあるって。泰生さん、わかる?」 俺のすぐ下から晴子の声がする。俺は言われた通りに右手を探ってそれを見つけ出した。 「ぎゃー……」 「なに、なに?」 俺より身軽に上がってきた晴子が、肩ごしに覗いて、 「泥棒に入られたあとみたい」 と呟いた。 「その通りなんだけどね」 蔵の二階までは、すでに伯父さんたちが片付けに入っていたので、俺たち東京組は荒らされた直後の有り様は見ずにすんだのだが、手つかずのこの階は、引きずり出された行李、散らばった衣服、壊れた陶器や箱が、それこそ足の踏み場もないほどに散らかっている。おまけに一つきりの白熱灯に、乱舞する埃が照らされて息苦しいほどだ。 「すっごー……」 思わず口許を手で覆っている晴子は、於賀村で一軒しかない雑貨屋の娘だ。一つ下だが、物怖じしない明るい娘で、昨日が初対面だったというのに今日は朝早くからこの家に遊びにきた。 「だってここ、他に高校生いないんだもん」 というのが晴子の理由だが、こう無条件に懐かれれば俺だって悪い気はしない。よく日に焼けていて、小柄な上に髪を二つに結んでいるので、とても高校生には見えないが、こんな妹ならいても良かった。 「どうする? 降りるか」 窓は開かないと聞かせられていたし、晴子を気づかってこう言ったものの、この散らかりようを前に、不思議と俺の中には「ここにいたい」という気持ちがあった。 慶子叔母は、蔵の中を一目見た途端、「お客さん気分でいらしたらいいんですよ」という伯父夫婦の言葉に甘えて、母屋で涼んでいる。俺だって、晴子と一緒に裏山の探検にでも行けば、と薦められたのだが、一応父親代理としての義務感も手伝って、「いっちょ覗いて見るか」とやって来た。 もう普段の出入りはしないからという話で、蔵の周囲は伸び放題の雑草に囲まれており、泥棒も、釘で打ちつけてあった入口を壊して侵入したらしい。しかしいくら母屋から離れているとはいえ、隣町からトラックで乗りつけて扉を叩き壊した輩がいたというのに、朝まで気づかなかったというのは田舎とはいえ呑気すぎやしないだろうか。 泥棒にさらわれた後で、目ぼしいものは残っていないだろう。だが、重なり合った家具や、何やら見当もつかないガラクタの下から、「見て」「探して」と、好奇心を刺激するものがあって、俺は肌がちくちくした。 自分にこんな傾向があったとは意外だが、宝探みたいな子供の遊びを未だに楽しみたいらしい。 「わあ、可愛い着物があるー」 晴子は俺の気持ちを察したのか、少しわざとらしいほどの賑やかな声を上げて、行李の一つに飛びついた。引きずり出したのは鮮やかな柄の浴衣だった。高価なものには見えないが、今時の安っぽい花柄とは一味違っていて、俺が見てもちょっといいな、と思える。 「伯父さんに頼んで貰ってやろうか」 「ええっいいのかなあ」 「ほとんど捨てるって言ってたし、この家女の子いないじゃん」 一人息子は東京でサラリーマンをやっているという話だ。 「うれしー。他のも見ようっと」 現金な晴子はすっかり夢中になって行李をひっかき回しだした。 俺は彼女の背後に立ったまま、薄暗い蔵の中を、ぐるりと見回した。何となくまだ首の後ろがちくちくする。虫にでも刺されたか。 二階から想像したのよりも天井が低く、物に溢れているせいか狭苦しい。 うすべったい紙の箱が散らばっている奥に、ひっそりと一台の文机を見つけて俺は興味を引かれた。 俺はどこにでもすぐごろりと横になるため、我が家では和室をあてがわれている。畳の上に一畳分のカーペットを引いて勉強机が置いてあるのだが、そこは物置になっていて、卓袱台を持ち込んで宿題とかはそっちでやっている。 その卓袱台も足の一本にガタがきていて、その代用品にどうかな、と思ったのが第一印象だった。 邪魔な箱を注意深くどけつつ、文机に近づいてみる。 俺が電灯との間にいるのでよく見えないが、黒くて漆塗りの立派なものらしい。その辺の布で適当に表面を拭うと、つやつやした表面が現れた。 だが同時に、幾つもの大きな傷を見つけ、泥棒たちが置いていった理由もわかる。おまけに机の上にこれもまた何やらわからない大きなものが沢山のっているので、その手間を考えても東京へ送ってもらう、という案は一気に失せた。 「……泰ちゃん、晴子ちゃん……?」 「あれ? 旺さんじゃない?」 下階から聞こえる声に、晴子が頭を上げた。 「旺さんー? 上だよ、三階」 返事をしない俺に代わって、梯子の下を覗き込む。 がたがたと音がして、旺が顔を出した。 「大丈夫なの? ほこり凄いよ」 奴は慶子叔母同様、午前中に蔵内に一歩足を踏み入れた途端、咳き込み始め、リタイヤした軟弱な野郎だ。 「大丈夫。一人であっちにいてもつまらないからね」 旺はそう言って、ポケットから大判のハンカチを取り出し、三角に折って、顔の下半分に巻いた。 美奈子そっくりの顔の上に。 受験生の美奈子が予備校で来られない旨を上野駅で告げられ、俺の気分は墜落したが、八年ぶりだかでもう一人の従兄弟の顔を見た途端、これまた驚いた。 すっかり変わっていたとか、そういうわけじゃない。大体俺は同い年のこいつの顔をほとんど覚えてなかったし、今回も従兄弟といっても美奈子のことばっかり考えていた。存在を忘れていたのではないから、眼中になかったということだ。 子供時代も、俺は美奈子の後ばかり追い回し、俺の後ろをついてくる奴のことなんて、考える暇もなかった。美奈子が弟に対しては過保護だったので、どっちかと言うと面白くない存在だった。 それに……おとなしくて目立たない奴だったが、得体の知れないところがあって、俺は旺が苦手だったのだ。 正確に言うと、旺は二年前葬式で会った美奈子本人に「そっくり」というわけではなかった。美奈子は子供時代に比べてより華やかにもなっていたが、その強気な性格にも拍車がかかっていて、それが容貌にも現れていた。じろりと睨まれ、俺などびびってロクに挨拶もできない始末だった。 旺は、俺が幼い頃、こうなるのではないか、と想像していた美奈子に「そっくり」だったのだ。実物よりも、穏やかで、優しい顔だち、現実には絶対拝ませてもらえそうもない歓迎の笑み。 勿論、女に見えるということはない。それにハンサムで目立つというには存在感がなさすぎた。 泰ちゃんに会えるというので、旺はとっても楽しみにしていたのよ、という慶子叔母の言葉には、ひきつった愛想笑いで答えるしかなかった。汽車内で心底嬉しそうに何度も話しかけてくる相手を、無視するほど俺も礼儀知らずじゃない。けれど返事がぶっきらぼうになってしまうのはどうしようもなくて、性格と思ってくれたかそれとも何か感じるところはあったのか、於賀に着く頃には旺の態度も少々ぎこちなくなっていた。 うう……。俺だって反省はしているよ。旺は別に嫌な奴じゃない。だけど、苦手なんだ。どうしようもない。美奈子に似た容姿も違和感が増すだけで、良い印象にはならなかった。まあ、こっちはそのうち慣れるだろうが。俺の不自然な態度が慶子叔母にはばれていないらしいのが、唯一の救いだ。 おまけに晴子という遊び相手を見つけたんで、旺のことは奴が埃に降参して母屋に引っ込んだのを幸い、朝から放っておきっぱなしだった。 「二人とも体に悪いよ」 旺は似たようなハンカチをポケットから取り出し、俺たちに寄越した。 「ありがとう、借りるね」 「あ、どうも」 俺たちはおとなしく旺の真似をしてマスクをし、大掃除三人組みたいな恰好になった。 「ねえねえ、旺さん、これ見て」 「へえ、可愛いねえ、浴衣?」 「ねえ、泰生さんは貰ってもいいって言うんだけど、どうかなあ」 「大丈夫じゃない。俺も伯父さんに頼んであげるよ」 二人のモゴモゴした会話を背に、俺はまた文机に向き直った。旺が上がってくる前に、文机に薄い引出しがあることに気づいたのだ。 下に指をかけて引っ張るが、何かに引っ掛かったように開かない。音をたてて軽く揺すってみるが、1センチ以上は出てこない。 なんだかまた首の後ろが痒くなってきて、俺が面倒くさくなって諦めようとした途端、それを察したように、引出しがすうっと滑り出てきた。 さぞかし中身がつまっているかと思ったのに、中には一冊の本が入れられていただけだった。教科書くらいの大きさで、布の表紙がついている。 「あらっ、なあに? それ」 脇から晴子が覗き込んできた。 「昔の本? どんなの?」 俺は促されるまま、ボロボロの朱色の布の表紙を開いてみる。 中は、真っ白だった。 「なーんだ」 よく見ると、横罫が入っている。本ではなくてノートだったのだ。一度も使われていない。そのまま、ぱらぱらっと惰性でページをめくっていると、何かがはらりと床へ落ちた。 あっ、とか何とか、背後で声が上がったような気がするが、俺は構わずそれを拾いあげた。 「あらー」 晴子が思わず、といった声をあげて俺の手元を覗き込む。 それは一枚の写真だったのだ。 紙も古びた、女の写真。 着物姿の女性が団扇を片手に障子に寄り掛かっている。 「綺麗な人」 晴子の言葉通り、現代っ子の俺にも十分通じる美しさだった。黒々とした目が、どことなく宙を彷徨いつつも、カメラに向いている。唇は合わさっているのだが、何となく物言いたげだ、と俺は思った。 「それは何?」 背後からかかった旺の声が、気のせいかきつい口調で、俺と晴子はそろって振り向いた。両側から仲良く写真を手にしたまま。 「写真だよ」 「泰生さんが見つけたんだよ。ノートに挟まってたの」 この薄暗さで、立っている位置からよく見える筈ないのに、旺の目は俺たちの手元にじーっと注がれていた。 「旺さんも見れば?」 明るい口調で晴子が誘ったにもかかわらず、奴はにこりともせず首を振った。 「それ、戻しておいた方がいい」 その命令口調にむかっときた。 「俺の勝手だろ」 つい、こっちも強い口調になる。 「あ、ごめん」 気づいて旺は慌てて謝ったが、こっちはすでに意地でも返すもんか、という気持ちになっていた。 「後で、返しておけばいいじゃない」 二人の雰囲気を取りなすように晴子が言った。 俺は黙って頷いて、写真をもとのノートにはさみ、手にしたまま、挑戦するように旺の顔を見る。 何でお前の言うことを聞かなくちゃならないんだ! と、俺の顔には書いてあった筈だ。 旺はノート、俺、晴子の顔を忙しく見比べた。 「だけど……」 「行こうぜ、晴子。明るいとこで見たいだろ」 奴を無視して晴子を促す。 「うん……」 流石に旺が気掛かりなようだったが、それでもおとなしく俺について階段を降りてきた。二人の従兄弟の力関係は敏感に感じているらしい。 「旺さん、どうしたのかなあ」 蔵を出る時、振り返ってまだ電気のついている上の階を見ていた。 「知らね。あいつ昔から、時々わけわかんないこと言うのさ」 だから、俺は旺が苦手だったのだ。 |
| 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / NOVEL / HOME |