| 1 / 2 / 3 / NOVEL / HOME |
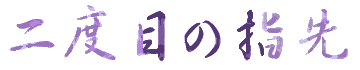 -3- 納期はぎりぎり土曜に間に合った。植村と真崎と、そして今度こそ業者の開発担当者は、半分徹夜の状態でTの工場にロボットを運び込んだ。 結果は満足のいくものだった。 「これはいい。据置タイプに比べてそれほどスピードも落ちてないし、このまま何ヶ月か様子を見て、問題がなかったら他の工場にも話をしてみよう」 西井の言葉に、真崎たちは「ありがとうございます」と頭を下げた。 安堵と達成感で、疲労で痛む目や肩の重みがすっと和らぐ気がした。 高揚した気持ちのまま、真崎と植村は西井に誘われて飲みに繰り出した。 開発担当者は自社へトラックを戻さなければならないので辞退し、真崎は社用車に残りの二人を乗せていったん会社へ戻り、植村と共に部長に簡単な報告を済ませて、待っていた西井と合流した。 「いや~ご苦労さんでした」 終始上機嫌の西井はよくしゃべり、よく飲んだ。睡眠不足の真崎たちはそれなりにセーブしていたのだが、彼に付き合ううちにいつのまにか杯を重ねていった。 西井が女の子のいる店に行こうなどと言い出さないのはありがたく、二軒目に足を向けたのも小さな座敷のある家庭的な飲み屋だった。 真崎の向かいであぐらを組んだ西井は充血した目で定期入れから娘の写真を取り出すと、だらしなく笑った。 「西井さん、お子さんいらしたんですか」 「いらした、いらした。小二と五歳。可愛いだろう?」 植村はトイレに立っている。しばらく戻ってこないところを見ると、また外で煙草でも吸っているのだろう。 真崎が如才なく娘の容姿を誉めると、西井は無邪気に喜んだ。 一緒に飲んでみれば、西井は根は人のいいオッサン、という感じだった。こちらの思いが伝わったのか、相手も同じようなことを言い出した。 「真崎君はあんまりしゃべらないからおとなしいんだと思ってたら、先週の土曜日は急にあの場を仕切りだすからびっくりしたよ」 「いや、生意気な真似をしてすみません」 「いいって、いいって」 西井は肩をすくめて顔の前で手を振った。 「君に言われなくてもロボットに問題ないことはわかってたしね。基本がちゃんとしてたし、あとはちょっと調整すれば済むだろうって思ったよ」 笑いながらそんなことを言う。真崎は「へ?」と赤らんだ男の顔を見た。 「わかってたですって?」 そりゃあ、と西井は言った。 「こっちだって何年もあの手のロボットは扱ってるんだ、わかるとも。植村君がなんか深刻そうだからそう言ってやろうと思ったら、君にお株を取られちゃったよね」 それじゃもしかしてこっちが言い出さなくても納期は延長してもらえたのかも、と、真崎が妙な脱力感を覚えていると、「だけどさ」と酔っ払った相手が身を乗り出してきた。 「どうして君ら、あそこで手をつないでたの?」 真崎はとっさの返答につまった。 顔を真っ赤にさせていると、背後から「どうした」と戻ってきたらしい植村の声がした。 「あ、西井さん写真出した?」 テーブルの上に置かれた定期入れに気づいて言う。 「それじゃそろそろ家が恋しくなる頃だな。やれやれ」 笑みを含んだ口調に真崎は顔を上げた。 「いつもこうなんですか?」 「そう。ぼやぼやしてると眠り込んじゃうからね。さっさとタクシーに乗せちまおう」 先ほどの件についてそれ以上追求しようとしない西井にほっとしながら、真崎は植村と二人がかりで彼を店から連れだし、タイミング良く捕まったタクシーに押しこんだ。 運転手にタクシーチケットを渡した真崎は、車を見送ったところで「やばい」と腕時計を覗きこんだ。 「どうした」 火照った顔をした植村が少し離れたところから声をかけてくる。 「電車が……。うちの方の私鉄、妙に終電が早いんですよ。くそっ、もう間に合わない」 どうしたもんかな、と頭を掻く真崎に、植村が「うちへ来るか?」とさらりと言った。 「えっ……」 思わず驚きの声をあげて見ると、植村はさり気なく視線をそらし、「ここからなら地下鉄一本だから」と呟いた。 そのまま背を向けて歩き出す。駅へ向かっているのだろう。 真崎は一瞬、足が動かなかった。かけられた言葉の意味を理解するにつれ、ますます素直に誘いに応じにくくなる。 「どうした?」 数メートル離れたところで立ち止まった彼がこちらを向く。夜風に乱れた前髪の一部が、眼鏡のフレームにかかっていた。それを払おうとレンズに触れてしまった植村は、いったん眼鏡を外してポケットからクロスを取り出した。 血液の流れが速くなったように感じるのは、アルコールのせいだけではないだろう。 繁華街のネオンに照らされる上気した頬。酔いで潤んだような瞳。 真崎が誘いに乗ることを期待しているのかどうか、その表情だけではよくわからなかった。もしかしたら彼自身にもわかっていないのかもしれない。 ついていっていいのだろうか。 真崎が迷っていると、酔っ払いの集団がどやどやと植村のそばを通っていった。 すらりとしたスーツ姿が視界から消えかけ、真崎は慌てて走り出した。 地下鉄の車内はわずかに暖房が効いているようだった。 ぽつぽつと空席はあったが、二人は乗りこんだドアにもたれて立っていた。 会話もなく、それぞれ真っ暗な外を眺めている。だが真崎は何度か相手の顔を盗み見た。 ドアに顔を近づけているせいで、かすかに開いた植村の唇の先に、丸くガラスが曇っている。 彼が呼吸をするたびにその湿り気が大きくなったり小さくなったりする。そのゆっくりとした動きは間違いなく彼の体内のリズムと直結していて、真崎はいつのまにかそれに見惚れていた。 ガラスが曇るのは彼の吐息が熱いから。 自分はそれをすぐ耳元で感じたことがある。喘ぎと共に吐き出されるそれを、自分の唇で塞いだことがある。彼はくぐもったような声を漏らし、そして――。 「植村さん……」 真崎は無意識にその名前を呼んでいた。大きな声ではなかったが、聞こえなかったはずはない。だが植村は顔をこちらに向けなかった。 「植村さん……」 もう一度呼ぶ。すでに躊躇なくその横顔を見つめながら。 酔いのために充血した彼の目は、じっと外に据えられていた。 街の灯りも見えない、地下鉄の闇。だが本当に見ているのは何なのか。 黒いガラスには、植村同様、真崎の姿も映っているはずだった。 「植村さん……」 眼鏡の奥の睫毛はぴくりとも動かない。だが、口もとの曇りがさあっと広がった。 真崎が片手を伸ばすと、それを避けるように植村は身を引いた。そして初めてこちらを向き、「もう着く……」と囁いた。 真崎は手を引っ込めなかった。彼の視線をとらえたまま、ガラスに手を押しつけると、彼の吐息で湿った曇りをぐい、とその手のひらで拭ってみせた。 植村は一瞬驚いたように目を見張り、そして顔を背けた。 彼のマンションは駅から近かった。 地下鉄の車内から続いていた緊張感は、狭いエレベーターの中でいっそう高まった。 真崎は耳をすませて相手の発するあらゆる音を聞き逃すまいとしていたが、今やそうしているのが自分だけではないことも明白だった。 不用意な息を漏らさないよう唇を噛み締め、表情を取り繕ってこちらに動揺を悟られまいとしているのがわかる。身動きしたら負けだと思っているのか、上昇する箱の中で不自然なほど身体を固くしていた。 だが、そんな勝ちなら、真崎はいくらでも譲ってやるつもりだった。 植村が鍵を開け、そのあとに続いて部屋に入る。重い扉が閉じきるのも待ち切れず、真崎は彼の肩に手をかけて振り向かせた。 女性相手では決してあり得ない高い位置で唇を触れ合わせる。 植村は拒んでいなかった。かすかな開いた隙間に舌を滑りこませると、彼は真崎の腕に手を添えてきた。 「ん……」 鼻に抜ける声に、真崎の背中が震えた。強く身体を押しつけ、いっそう激しく口内を蹂躙する。 鈍い音をたててドアが閉じると、廊下からの明かりが遮断されて、辺りは真っ暗になった。 それでも二人はしばらくアルコール臭い息を吐きながら舌を絡めあっていた。 長身の男たちが狭い玄関で靴も脱がずに抱き合う。いつ鞄を落としたのか、両腕で相手を抱きしめながら、まるで覚えていなかった。 「ふ、ん、ん……」 長い間焦がれていた声に煽られ、興奮した真崎は植村の肩から背中、そして腰へと手を下ろし、ぐっと掴んで引き寄せる。下半身を密着させると、さすがに腕が強く押された。離せと言っているのだ。 真崎はそれでもしばらく柔らかな舌を堪能していたが、再び腕を押しやられると、しぶしぶ身体を離した。 闇の中でも、かかる吐息で相手の唇がすぐそこにあることがわかる。互いの唾液で濡れているだろうそれが囁いた。 「これが……」 彼の声はかすれていた。 「これがおまえの言っていた〝お願い〟か?」 真崎の目がわずかに曇った。 「応えてくれたのは……約束だと思ったからですか?」 答えはなかった。ただまだ整わない互いの荒い息だけが玄関に響く。 真崎は軽くため息をついた。火をつけられた欲望がまだ身体の中でくすぶっている。だがこのままそれを解放したいという望みは叶えられそうもなかったし、彼としてもすべてがはっきりしないこの状態で、それは本意ではなかった。 「俺のお願いはね、植村さん。八年前のあんたの気持ちをきくことだ。あんたが俺をどう思っていたか……知りたい。ずっと知りたかった」 すっと植村が息を呑む音が聞こえた。断られるのかと思ったら、次に聞こえたのは「なんだ、そんなことか」という半分呆れたような声だった。 真崎はかっとした。 「あ、あんたにとってはそんなことかもしれないけど、俺にとっては大事なことなんです」 「……わかった」 しばらく逡巡するような気配のあとで、植村が口を開いた。視界がきかないせいか、彼の低く静かな声は柔らかく真崎の耳に響いた。 「おまえがそんなに聞きたいというなら言ってやる。ああ、そうだ、俺はおまえが好きだったよ――」 真崎は暗闇の中でさらに目を閉じた。 喜びと同時に奇妙な寂しさが胸に広がる。後者は多分、そのあとで離れてしまった年月のせいだ。 「俺は比較的早く自分の気持ちに気づいていた。こんな、四つも年下のしかも男相手になんでとは思ったけど、好きになったのは自分だからしかたないとも諦めた」 植村の優しい、懐かしげな口調は真崎の心に直接響いた。 「実際おまえは格好良かったしな……。外見もそうだけど、怖いもの知らずのその性格とか、ああこいつどんなにいい男になるだろうと思ったら、その成長に少しでも手を貸せる自分が幸福だった。嬉しかったよ。だから誘われたときも拒まなかった」 もっとも、と植村が軽くため息を漏らした。 「おまえが俺を何とも思っていないことはすぐわかったけどな」 違う、と言いかけた真崎を遮るように、植村は彼の腕においたままだった手に力をこめた。 「もちろんちょっとは興味も抱いていてくれたんだろうし、好意もあっただろうさ。でなきゃおまえだって男に手を出そうなんて思わないだろうしな。けど、少なくとも俺と同じ気持ちじゃなかった。俺と同じようにはおまえは俺を見ていなかった」 真崎は再び口を開こうとし、躊躇して、やめた。 狭いマンションの沓脱で向かい合ったまま、彼は植村の告白に黙って耳を傾けていた。 「もちろんそれでおまえを責めるつもりはないよ。人の気持ちなんてどうにもならないものだしな。俺もわかっていたから何も言わなかった。おまえは歓迎会の夜、失って俺への気持ちに気づいたと言ったが、それは気のせいだと思う。あのあとで俺に対する何らかの執着や恋しさがあったと言うなら、それは俺と別れたあとで生まれたものだと思うよ……」 そうだろうか、と思い、そんなものかな、という気もする。だが八年も前のことだ。自分ですらよく覚えていない。 「じゃあ、じゃあ、いきなりいなくなったのは、やっぱり俺が女の子と寝ていたから? 怒ったんですか?」 植村の右手が腕からはずれ、真崎は彼が離れてしまうのかと慌てたが、ゆっくりと前髪をかきあげる気配がした。 次第に目が慣れてくる。 都会では真の闇などあり得ない。カーテン越しに窓から漏れる外界の照明や電化製品の明かりのせいで、真崎には、自分よりわずかに背の低い植村の輪郭がぼんやりと白く見えた。 彼は眼鏡に手をやって、キスで傾いてしまったフレームを直していた。 「そう、とも言えるし、違うとも言える。確かにきっかけはあれだが、腹を立てたわけじゃない。さっきも言ったが、自分の片思いだってことはわかってたしな……。 だけど、ああ、確かに辛かった。自分の好きな相手が他の人間を抱いてるところを目の当たりにして、ショックだった……」 語尾がかすかに震えていると思ったのは気のせいなのだろうか。真崎は思わず彼を引き寄せようとして、やんわりと拒まれた。 「おまえが、初出社してきた日、俺が言った言葉を覚えているか? 俺にとって八年前のことは汚点だと……」 真崎は身体をこわばらせた。覚えている。忘れようったって忘れられない。あの冷たい口調は錐のように真崎の心に突き刺さり、未だじくじくとその傷は癒えていなかった。 彼が今まで植村との間に距離を置いていたのは、再びその傷口を抉られるのが怖かったからだ。 「おまえがあれを違うように受け取ったのはわかっていたが、今までその誤解を解こうとは思わなかった」 植村は意外なことを言った。 「俺はな、さっきも言ったけど、教え子のおまえに自分の気持ちを打ち明けるつもりはなかったんだ。負担になりたくなかったし……正直に言えば嫌われるのは怖かったしな。だから見かけだけは冷静を装って、いつも平気な顔をしていた。最後までただの家庭教師、たまには遊びで性欲処理の相手もするような、そんな関係を貫くつもりだった。あのときまで――」 だけど、と植村は額に手をやって俯いた。 「おまえはさっき八年前の俺の気持ちを聞きたいなんて言ったけど、本当はうっすらでも気づいていたんだろう? 当然だよな。何とも思ってなきゃ逃げ出したりなんかしない。俺にもわかっていた。あの翌日、俺が何も気にしていない顔でお小言の一つでもくれてやれば二人の関係はまた元のように戻れる。何にもなかった振りをして、おまえにも気持ちを気づかれなくて済む。でも、できなかった」 今度こそ間違いなく、植村の声は震えていた。 「馬鹿な高校生に片思いをしているなんて、俺は絶対知られたくなかった。それは俺のプライドだった。それなのに、なのに、俺は次の日、どうしても平気な顔でおまえの前に現れることができなかった。これからも同じようなことが幾らでも起こると思ったら、またこんなふうにどんどんおまえに傷つけられるんだと思ったら、もう我慢できなかったんだ。だから、逃げた。おまえに気づかれることになるとはわかっていながら――」 「八年前のことが汚点なのは」と植村は囁いた。 「おまえと寝ていたからじゃない。俺がプライドを捨てて保身に走ったからだ。俺は何年経っても、そんな情けない自分が許せなかった……!」 「植村さん!」 真崎は今度こそたまらなくなって、彼を腕の中に抱きしめた。首筋に鼻先を埋めて囁く。 「植村さんは情けなくなんかない。いつだって格好良かった。憧れだった。こんな風になりたいって思ってたよ。傷つくことが怖いのはあんただけじゃない、俺だって……!」 「真崎……」 八年前のこととは言え、自分なんかに真情を吐露するのは、それこそプライドの高い植村にとっては耐えがたいことだったろう。それを約束だからと打ち明けてくれた。必要以上のことまで……。 「ありがとう、植村さん、ありがとう、もう十分です――」 植村の手がゆっくりと背中にまわされる。二人はしばらくそうやって静かに抱き合っていたが、しばらくして、植村がフン、と鼻を鳴らした。 「うえ…むらさん?」 「もう十分か? おまえそんなに押しの弱い男だったか? 以前の強気はどこへ行ったよ? 西井さんの前で見せたあのはったりは?」 「植村さん?」 「〝お願い〟がそんなことかって言ったのはな、あんなキスのあとで、今更八年前の気持ちなんて聞くからだ。それで十分だって? 聞きたくないのか? それとも興味なんかない? 俺の今の気持ちには」 「植村さん!?」 真崎はがばっと身体を起こした。信じられない思いで、暗がりの中で懸命に目を凝らし、植村の表情を覗きこもうとする。 「言ってやろうか?」 その唇の端がわずかに上がっているように見えるのは気のせいだろうか? 「おまえが聞きたいなら、言ってやってもいい」 言って、と真崎は囁いた。片手を彼の顔に伸ばし、華奢なフレームを耳から抜き取る。 「言ってください、植村さん。俺は聞きたい……」 真崎の背中にまわされていた、植村の温かく大きな手のひらに、ぎゅっと力がこもった。 「好きだよ、真崎。助けてくれてありがとう。いい男になったな。俺が思った通りだった」 「ん、ん、はぁ……」 狭いシングルベッドが軋む。二人分の吐息で室内の温度が上がる。 「植村さん、これ、どう、気持ちいい……?」 「あ、あ……」 シーツの上の体が大きく揺れる。 「痛いですか?」 「キツイ……久しぶりだから」 彼の足元にうずくまっていた真崎は、その言葉にふと顔を上げた。 「植村さん……」 彼の身体の最奥を指で柔らかくほぐしながら、真崎はさり気ない口調を装ってきいてみた。 「植村さん、あれ以来、男と経験は……?」 返事はない。 わずかに逸らされた顔が答えを告げているようで、真崎は乱暴に体を起こした。 「うわっ、馬鹿……!」 「植村さんっ!」 「この馬鹿っ! ああっ、痛……もっと、ゆっくり、真崎!!」 真崎は言われた通り、いったん体を引いた。そしてゆるゆるとまた沈めていく。 「あ、ああ、真崎……!」 無駄な肉のない、滑らかな筋肉のついた胸が綺麗に仰け反っていく。こんなふうに抱き合うと、互いに何も隠せない。 「植村さん、呼べる? 俺の名前を覚えてます? 八年前みたいにあんたに呼ばれたい……」 「あ、あき、晃久、晃久、ああ……!」 真崎はその声に目を閉じた。緩やかに腰を動かしつつ、一度は離し、再びこうして手に入れた人の全てを味わう。 熱い肉、甘い声、そして――。 苦痛と快楽に眉をひそめた植村が、揺すぶられながらこちらの腕に爪をたててくる。 真崎はその手を掴みとって指を絡めた。 そう言えば八年前、最初に見惚れたのはこの指先だった。 工場で震えていたのもこの指。 そして今、痛いほど強く自分にすがってくるのも――。 こみ上げてくる愛しさに煽られるまま、真崎は身体を突き上げた。 「あ……あ!」 ぎぎっとベッドが危険な音を立てる。 このままベッドも世界もお互いも、幸福なまま壊れてしまえばいい。上昇する体温に溶け出して、飴のようにぐにゃぐにゃになってしまえばいい。 愚かなほどの刹那的な衝動に任せ、二人は互いを喰い合い、うめき声をあげてそれぞれが欲望を吐き出した。 1DKのマンションの玄関から寝室まで、二人分のスーツやワイシャツが点々と落ちている。ベッドサイドにはどちらかの靴まで転がっているのが見える。 植村の胸の上で頭を休めていた真崎は、満足げなため息をついた。 「なんか、嘘じゃないでしょうね、こんなの。あんなにずっと冷たかったのに――」 植村はかすれた声で笑った。 「そりゃそうだろう。こっちだって同じ若造に二度も失恋するなんてごめんだからな。慎重にもなる」 「だって、俺の気持ちはわかってたでしょうに」 「そんなこと、あるはずないだろう」 真崎はわずかに頭をもたげた。 「だって、言ったのに。歓迎会の晩。好きだって」 「好きだった、だろ。おまえがしたのは八年前の話だろ。それに、今度大事な人ができたら、とか何とか言うから、ああ、そういう奴がいるんだな、と俺は思ったよ」 「できなかったんですよ。その、植村さんくらい大事な人なんて……」 真崎はそう呟きながら、今夜は驚くことばかり聞かされる、と思った。 切ない思いを抱いていたのは自分だけではなかったのだと知って、嬉しさと同時に「勿体ないことをした」という気持ちがわいた。 変に弱気にならなければ、この心も体ももっと早く手に入ったかもしれないのに。 まあ最終的にはうまくいったんだからいいか、と思い直し、そこで真崎はふと思いついて口を開いた。 「そういえば植村さん、行かないんですか? アフリカ」 「アフリカぁ?」 無意識のように真崎の髪を撫でていた植村は、素っ頓狂な声を出した。 「なんだってアフリカなんかに行かなきゃならないんだ? 俺が」 「だって言ってたでしょう。昔。アジアやアフリカの僻地へ商社マンとして売りこみに行くのが夢だって。ずいぶん熱く語っていましたよ」 「馬鹿、あれはな。やる気のないおまえにモチベーションかけるために言ったんだ。将来の具体的な目標を持たせようと思ってさ」 「ええっ、そうなんですか? 俺はてっきり植村さんが本当にそういう夢を抱いてるんだと……」 「いや、もちろん嘘じゃなかったけどさ。アフリカってのはともかく、そのうち海外出張もあるだろうし」 真崎はふーん、と声を出した。目の前の乳首を悪戯すると、咎めるように髪を引っ張られる。 「いた、痛い……。ま、俺はその影響で商社マンになったんだし。それで再会できたんだから、いっか」 懲りずにぺろりと舐めると、尖ったそれは柔らかく舌先を押し返してきた。 「それにしても植村さんにここまで商社マンがはまるとは思わなかったな。もちろん頭のいい人だから何やっても成功するだろうとは思ってましたけど、まさか〝マグロの植村〟なんて言われるほど大胆なセールスをするなんて……」 意外か、と問われて素直に、ちょっと、と答える。 「まあな、俺も最初はこんな熱血じゃなかったけど。〝直需〟を担当するようになって、ただ客の言い分を聞いてるだけのいい子ちゃんの営業じゃ駄目だってわかったんだ。それでな、俺はおまえのことを思い出した」 え、と真崎は思わず頭を上げた。 「あの生意気な高校生。あの強気の男だったら、どんなふうに売り込むだろう、どんな大胆な戦術を取るだろうって。そう考えたら自然と口も体も動いたよ。もちろん今じゃおまえのイメージなんかに頼らなくてもやっていけるが、きっかけは確かそんな感じだった……」 寝室内に沈黙が下りた。 サイドテーブルの上のアナログ時計がカチカチと時を刻んでいる。 胸の上の心地よい重みを感じながら、植村は返事のない真崎はもう眠ってしまったのだろうと思った。 ただでさえ疲れて睡眠不足のところへ酒を飲み、そのうえ先ほどまで激しい運動をしていたのだから無理もないだろう。 植村の体も心地よい疲労に包まれている。乱暴にされたせいで鈍く疼く痛みまでもが愛しかった。 自分も眠ろう、そう思って目を閉じたとき、嬉しそうな真崎の声が聞こえた。 「それじゃあ今の植村さんて、俺のおかげ……?」 「なっ…!」 植村は一瞬絶句し、思わず言い返そうとしたが、直後に聞こえてきたのは安らかな寝息の音だった。 「おまえってやつは……」 呆れてため息をつく。 どうやら真崎は八年前の図々しさを一晩で取り戻したらしい。 「そういう調子のいい男だったよな、こいつは……」 ま、いいか、と植村は唇の端にうっすらと笑みを浮かべて瞼を閉じた。 年上の恋人らしく、ここは見逃してやることにしよう。その代わり、職場ではびしびししごいてやる。 甘い顔を見せるのはベッドの中でだけ。 明後日からはまた、多忙な日々が待っている。 【終】 |
| 1 / 2 / 3 / NOVEL / HOME |
|
参考文献 ここで題材にしたパレタイジングロボットの開発とその苦労については、産学社「最新データで読む産業と会社研究シリーズ5 商社」 掲載の事例を参考にさせていただきました。 |