| 1 / 2 / 3 / NOVEL / HOME |
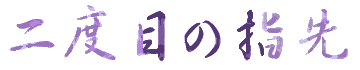 -2- それからさらに一カ月ほど、真崎は植村と行動を共にしていたが、やがて徐々に一人で担当を任されるようになった。 もともと三年間のMでの経験があるのだから、新卒者とは違う。仕事の呑みこみも早く、営業としての手腕もある真崎は、いくつかの得意先を植村からまわしてもらったこともあり、徐々に成績を上げていった。 前の会社では頭の固い上司と衝突して睨まれたこともあったが、今度は職場の人間関係もうまくいっている。 Mからの転職ということで初めはいくらか構えているようだった同僚たちにもうまく立ちまわって警戒を解かせ、数ヶ月も経つと、真崎はもう何年もここにいるような顔をしてすっかり部に馴染んでいた。 仕事はやり甲斐がある。上司の受けもめでたい。総務や秘書課の女の子たちから飲み会の誘いも頻繁だ。 だが、真崎にはどこか満たされないものがあった。 一人深夜に目が覚める理由。席を立つ姿を無意識に目で追ってしまう瞬間。 初めは昔の苦い後悔がそうさせるのだろうかと思ったが、月日が経つうちに嫌でもそうでないことがわかってくる。 真崎は植村に惹かれていた。八年前の思いを引きずっているのか、改めて彼の魅力に目が眩んだのか、それはわからない。それにそんなことはどうでもいいことだ。 わかっているのは彼のスーツ姿に見惚れ、その仕事ぶりに尊敬以上の気持ちを抱く自分。話すときにはやる鼓動と、ふと触れた折りに熱くなってしまう身体。 何度も思いを打ち明けたくなる。その手を掴んで、八年前のように引き寄せたくなる。 だがダイヤモンドのように冷たく硬質な植村の横顔は、固くそれを拒んでいた。 彼が真崎に辛くあたるということではない。むしろ仕事上ではよくフォローしてくれるし、彼が真崎を後輩として一番に目をかけていることは周知の事実だった。 ただし、彼が許すのはそこまでで、それ以上は決して真崎を内側へ立ち入らせなかった。たまに会うと一緒に昼食を取り、噂話や情報を交換したりもする。しかしそんな場所でもプライベートな事柄はいっさい話題に上らせなかった。 休日の過ごし方、趣味、親しい友人、恋人の存在。真崎の知りたくてたまらないことは、常に決して自分が入ることのできない場所にあって、そこには開けてくれとノックすることさえ許されないような頑なさがあった。 これまでの真崎を知る者なら信じられないというだろうが、彼は植村が怖かった。 強気に出ても憎まれない得な性格で今までの人生を乗り切ってきた真崎である。だが、八年前のできごとを「汚点だ」と言いきったときの植村の冷ややかな口調を思い出せば、無理に押すことなど到底できなかった。 真崎もあの晩の約束を守り、従順な後輩としての仮面の下に、胸のうずきを押し殺していた。 夏が過ぎ、秋も深まって、東京で木枯らし一号が吹いたころ、Tへロボットを納入する日がやってきた。工場のラインがストップする土曜日である。 真崎はTの担当から離れてすでに久しかったが、二人で受けた契約だからと言って植村が搬入に誘ってくれた。 実際契約書にも真崎の名が上がっており、あとから部長に聞かされて知った真崎が恐縮すると、植村は「馬鹿、失敗したら連帯責任なんだぞ」と笑っていた。 真崎はあの場所にいただけで、口をはさみすらしていない。実際半年という納期の中で、泣き言を言いかける業者をなだめすかし、時には一緒になって見よう見真似でロボットを作り上げたのは他ならぬ植村だった。 二人の仕事です、などと図々しくしゃしゃり出ていくつもりなど毛頭なかったが、植村の気遣いが嬉しかったのと、自分も立ち会った取引きを最後まで見届けたいという仕事上の純粋な好奇心から、真崎は誘いに乗ることにした。 「おまえと二人で出るのも久しぶりだな」 助手席の窓から外を眺めながら、植村は真崎が思っていたのと同じことをぽつりと口にした。 Tの工場に着くと、すでに業者は搬入を済ませていた。ただ植村との会話を盗み聞くに、どうやら開発担当者は都合で来られなかったらしく、別の人間が出向いてきたらしい。 植村はわずかに眉をひそめたが、小さく頷くと、待ちうけていた工場次長の西井をロボットの前に誘った。 「ほお、アームを上から下ろすのか。これで省スペース化を図るわけだね」 植村の肩越しにロボットを覗きこみながら、西井は感心したように言った。 そういえばこの西井という男との距離の近さも気になっていたのだった、と、真崎は少し離れたところで顔をしかめながら思った。 真崎の目の前で、二人は親密そうに何事かを話し合っている。時には植村が珍しく声をたてて笑うこともあって、本当に仕事の話をしているんだろうな、と疑いたくもなる。 それでもようやく次長立会いのもとでロボットを動かすことになったらしく、西井がその場を離れてベルトコンベアのスイッチを、植村がロホットのスイッチをそれぞれ入れた。 機械が動き出すのを確認して、二人は真崎の位置まで下がってきて並んで立った。 コンベアに乗ってダンボールが運ばれて来る。アームの先に付いたハンドがそれを掴んで持ち上げ、向きを変えて――。 ばたん、と音がしてダンボールが床へ落ちた。アームは空のままパレットへ向かい、ありもしない荷を下ろしてまた戻ってくる。そして次のダンボールを持ち上げた。 ばたん。 ばたん。ばたん。 アームは次々とダンボールを掴んでは落としていく。 声もなく固まっていた男たちのうち、一番最初に動いたのはやはり植村だった。 「……どうやら、ハンドの握力がゆるいようですね」 そう言ってロボットのもとに走り寄る。業者の若い男もあわててそのあとに続いた。 真崎はその場にとどまったまま、横目で素早く西井の表情を盗み見た。とりあえず何の表情も浮かんでいないように見える。 植村がいったんロボットを止め、若者と相談しながらあちこちをいじった。そしてまた作動させる。 アームは再びダンボールを掴み、そして落とした。 真崎は愕然とした。きちんと何度もテストされているはずだ。自分は携わっていないが、植村のことだ、その点は業者に徹底させたはずである。 だが半年かけて彼が作り上げたロボットは、目の前でボロボロと荷を落としている。真崎が知る限り、かつてない植村の不手際だった。 「ちょっと失礼」 真崎は西井に短く言い捨て、植村のもとに走った。 テスト作動のためにコンベアに載せた荷はもう数個しか残っていない。コンベアとパレットの間には、アームが落としたダンボールが幾つも転がっていた。 「植村さん」 声をかけても彼は背を向けたまま、振りかえろうとしない。 真崎は状況を伺うように、ロボットの向こう側にまわりこんだ青年の顔を見やったが、彼は力なく頭を振るばかりだった。 内心で舌打ちする。 「植村さん」 真崎はわずかに声を高め、視線を落としてはっとした。 植村はロボットの本体に軽く手をかけた形でコンベアの方を向いている。そのため表情は伺い知れないが、機械に触れた指先が、ほんのわずかに震えていた。 「あのな、植村さん――」 背後から西井が近づいてくる声がして、真崎はとっさにその指先を握った。 彼のそんな姿を誰にも見られたくなかったのだ。 植村ともあろう男が、一瞬とはいえ 不測の事態を前に対処につまって立ちつくしている。その現実を認識するやいなや、真崎の血液中のアドレナリンがどっと増した。 手のひらの中の指を、ぎゅっと強く握りしめる。 植村は手を振り払おうとはしなかった。 「なあ、植村さん、そのアー……」 「西井さん」 真崎は植村の手を取ったまま、振りかえると強い調子で西井の言葉を遮った。そして再びロボットの方へ向き直り、じっとその動きを観察する。 アームは最後のダンボールを掴み、旋回しようとしてやはり途中で落とした。 真崎は手を伸ばしてロボットのスイッチを切った。 「西井さん、申し訳ありません、あと五日、待ってもらえませんか?」 「真崎君?」 西井は少々驚いたように目を見張った。今まで真崎とは挨拶以外ろくに言葉も交わしていなかったのだから無理もない。 「アームを上から下ろすせいで、据置タイプのものに比べてちょっと調整が難しいんです。ですがすぐ直りますのでご心配なく」 真崎はきっぱりと言いきった。 西井はちょっと黙ってロボットの方を見やってから、「五日で大丈夫なのかい?」ときいてきた。 「ええ、お任せください」 「植村君?」 西井が黙ったままの植村を伺うように声をかける。はっとして顔を向け、何か言おうとする彼を、真崎は握った手に力をこめることで遮った。 「責任は僕が持ちます」 有無を言わせぬ真崎の口調に西井はわずかに口を開け、そして何も言わずに閉じた。 それほど親しくもない自分がが生意気な口をきいて怒らせてしまったかと不安になったが、ほっとしたことに西井はいつものにこやかな表情にもどって頷いた。 「まあ、五日といっても工場が動いてるからね。それじゃまた来週の土曜日ってことにしようか」 「わかりました。それでは七日後の同じ時間に」 こわばった表情のまま、真崎もわずかに笑みを浮かべた。そして業者の青年に指示を出し、自分も手を貸しててきぱきとロボットを設置場所から下ろす。 植村も黙ってその作業を手伝った。彼のそんな様子は気になるが、今は一刻でも早くこの場から連れ出したい。 真崎は西井への挨拶もそこそこに、半ば引きずるようにして植村を連れて工場を出ると、車に押しこんだ。業者のトラックに先へ行かせ、自分たちはその後を追う。 植村が口を開いたのは工場が見えなくなって間もなくだった。 「くそっ」 ふいにあがった罵り声に、真崎は驚いて助手席を見やった。 「くそっ!」 植村は両手で頭を抱え込むようにして俯いている。 「植村さん」 「くそっ、半年もかけたのに、欠陥品だとっ」 片手でダッシュボードをだん、と叩いた。 植村のそんな様子を見るのは初めてで、真崎は少なからず驚いた。 「ちょっ、植村さん!」 ガンガン殴りつける手をかばうように、真崎はあわてて左手を伸ばして拳を覆った。 「落ちついてくださいよ、植村さん!」 「これが落ちついていられるかっ。半年だぞ、半年! それがパー、しかもこれでTとの信頼関係もパーだ!」 「植村さんて!」 真崎は視線を前に向けたまま、握った拳を揺すった。 「担当の植村さんがそんなことでどうすんですか! 今はそんなこと言ってる場合じゃないでしょうが。七日でロボットを調整しなきゃならないってのに」 真崎の言葉に助手席の動きが止まった。その気配に真崎が視線を向けると、植村がぽかんと小さく口を開けてこちらを見ている。 乱れた前髪や紅潮した頬とあいまって、その表情は妙に幼く見えた。 「なんです?」 「調整?」 「そうですよ。もしかして聞いてなかったんですか?」 「聞いてた……」 「なら……」 「嘘だと思った」 今度は真崎が驚いた。 「嘘?」 「っていうか、あの場を誤魔化すための……」 冗談じゃないですよ、と真崎は呆れた口調で言った。 前を行くトラックに続いて、両手で大きくハンドルを左に切る。植村の体が頼りなく揺れてこちらにもたれかかってきた。 彼が体勢を立て直すのを待って、ごほんと咳払いする。 「俺の専攻はもともと機械工学ですよ。ま、設計とかそっちにはあまり詳しくなかったですけど、Mで包装機械に関わったせいでパレタイジングについては独学ですが勉強したんです」 横顔に植村の視線を強く感じ、真崎はぽりぽりと頬を掻いた。 「一度はきちんとダンボールを掴み上げるんだから、ハンドの握力が問題じゃないんです。俺が見るところ、アームが旋回時にわずかですが傾いてます。それが原因じゃないかと。ロボットの設置方向によってその影響が顕著に出るんでしょう」 「それで直るのか? 一週間で」 「そこまでは専門家じゃないですから――。でも死ぬ気でやればぎりぎり間に合うんじゃないかと」 なんだ、という声がした。 植村がため息をつくのがわかった。 「なんだ、俺はてっきり……」 「嫌だな、本当に嘘だと思ったんですか? 確かに五日って言うのははったりでしたけどね。どうせ土日しか納入できないんだ。いったん延期をOKすれば西井さんが七日まで伸ばしてくれるのはわかってましたから」 「計算したな」 植村さんのお仕込みで、と真崎は笑った。 「それにしてもひどいなぁ、俺の言葉を信じてなかったなんて。植村さんじゃあるまいし、そこまで大胆な嘘はつきませんよ」 先ほど殴りつけていたダッシュボードを指先でなぞりながら、植村は「どうだか」と呟いた。妙に無防備な仕草だった。 「おまえは昔から口から出任せみたいに強気な発言をかましてくれたよ。今度こそ宿題をやっておく、次こそいい点を取る」 植村の方から八年前のことに触れられ、真崎はどきりとした。全身の緊張を悟られないようにさり気ない態度を装って会話を続ける。 「え、そう? でも丸っきりの嘘じゃなかったでしょう? 約束はちゃんと守ったような気がするなぁ」 真崎がいくぶん拗ねた口調で言うと、そう、そう言えばそうだったな、と植村は助手席で呟いた。 「おまえはそういう奴だった。順位を上げるとうそぶけば、きちんとそれなりの成果は上げたっけ。まるで強気に振舞うことで自分を奮い立たせるみたいだった。そんなおまえを見ているのは気持ちが良かったよ……」 屈託のない、懐かしげな口調だった。 その場の雰囲気を壊すのが怖くて、真崎は両手でハンドルを握ったまま、黙ってトラックのテールランプを見つめていた。 それから一週間、真崎の予想通り、二人は死に物狂いで働いた。 状況を正直に部長に報告し、代われる仕事は誰かに代わってもらい、あとは業者の工場に缶詰状態になった。 ロボットの欠点についての真崎の指摘は大体正しかったが、調整は微妙で、今度は彼が開発担当者を叱咤激励する係だった。 「悪いな、真崎。自分の仕事もあるのに……」 植村は何度もそう言って謝った。 「なに言ってるんですか、これが失敗したら連帯責任だって言ったのは植村さんでしょ」 真崎は冗談に紛らわせたが、何度目かに同じことを言われると、それじゃあ、と言った。 「それじゃ、この取引きが成功したら、一つだけお願いを聞いてくれますか」 「お願い?」 「はい」 真崎は植村の目をじっと見つめながら頷いた。 しばらく黙ってその顔を見返していた植村は、やがて「いいよ」と答えた。 「おまえには借りができた。これがうまくいったら何でもきいてやる」 |
| 1 / 2 / 3 / NOVEL / HOME |