| 1 / 2 / 3 / NOVEL / HOME |
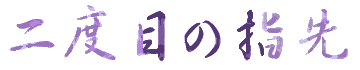 -1- 男子たるもの、高身長でそこそこ異性を惹きつけることができる。 真崎(まさき)はその上ルックスにも恵まれ、勉強もスポーツも人並み以上にこなしたから、ガールフレンドに事欠くようなことはなかった。 初体験は中二でさっさと済ませ、以来複数の女の子の機嫌を上手にとることも覚えた。もともとプレイボーイを気取っていても根は悪い人間ではなかったから、恨みを買うような真似は滅多にしなかったけれど、それでも結構遊んでいたことは違いない。 そんな真崎が、一人だけ男と寝たことがある。 高二のときの家庭教師だった。 いったい何だってそんな気になったのか、今ではさっぱり覚えていない。 相手にだって女っぽいところは少しもなかった。自分ほどではないが、背だって高かったし、肩幅だってしっかりあった。 整った容貌はしていたが、それだってかわいいなんてところはみじんもなく、どことなく軟派な自分とは対照的な、クールで硬質な顔立ちだった。 ノートの字を追うふりをしている自分の横で、淡々と数学の問題を解説している声がする。 ふと見ると、無意識のように彼の右手が赤ペンを弄んでいた。細く長い指。身長ではこちらが勝っているのに、そこだけは自分よりずっと大人びた彼の手。尖った関節。 真崎はなぜかそこから目が離せなくなった。 不可解な衝動を振りきるように顔を上げて彼の横顔を見る。視線に気づいたらしく、眼鏡の奥の目が「ん?」というようにこちらを向いた。 しかたないな、もう飽きたのか――。 そう言いかけた彼の顔に引き寄せられるように、真崎は唇を重ねていた。 配属された産業設備二部の部長席で、真崎は引き合わされた目の前の顔を呆然と見つめた。 「植村、彼が真崎晃久(あきひさ)君。M社で三年間包装機械を扱ってきたというから頼りにしていい」 部長がそう言うと、向かい合った男は、まったくのポーカーフェイスで「よろしく」と軽く顎を引いた。 真崎はあわてて頭を下げた。 「真崎君はしばらくこの植村の下についてもらう。うちの部はエンドユーザへ直接商品を売りこんでいく〝直需〟を行っているからね。時には飛びこみ営業もある。君には慣れないところもあるだろうから、二、三ヶ月かけてそのへんを植村から学んでくれ。こいつはこう見えても大胆不敵な男で、〝マグロの植村〟と呼ばれている。彼のノウハウを盗んだら是非こっちにも流してくれ」 よしてくださいよ、と植村が苦笑いする。ずっと忘れられなかったその顔を、真崎は食い入るように見つめた。 八年前、自分は高校生で、彼は大学生だった。教え子と家庭教師。だがそれ以外の顔も少しだけ、互いに見せていた。 別れも言えなかった。植村が一方的に曖昧だった関係を終わらせ、姿を消したのだ。 結果から言って裏切ったのは真崎だったが、捨てられたのもまた彼だった。けれど、当時の自分は戸惑うばかりでそんなことすらわからないでいた。 「そんなに見るな」 小声でたしなめられ、はっ、と気づいたときには、部長は席をたったあとだった。ちょうど昼時なので食事に行ったのだろう。気づけば部内にはほとんど人が残っていなかった。 「真崎君。メシは?」 「あ、ま、まだです」 「じゃあ外に出よう。午後は客先をまわる。今日は電車でこのまま直帰だから荷物は持って出てくれ」 「はい、あ……」 植村はすでに背を向けていた。 真崎は決して押しの弱い方ではない。この性格と人に好かれやすい容姿を最大限に利用して、Mでは同期の中でトップセールスを誇っていた。 だが突然再会した植村を前に、いったいどういう態度をとっていいものかわからなかった。まだその衝撃からすらも立ち直っていない。 一方、植村の方は自分の顔を見ても瞬き一つしなかった。 覚えていないのだろうか。八年前のことなど忘れてしまったのだろうか。 デスクの間を抜けていく相変わらずすらりとした後ろ姿に目をやる。髪型と眼鏡のフレーム以外、あまり変わっていないように見えた。もちろんあの頃はスーツなど着ていなかったが……。 寒がりの彼はセーターの下にもシャツをたくさん着こんでいて、そのボタンをいちいち外すのに閉口させられた。真崎が文句を言うので、何回目からかは植村が自分で脱ぐようになった。 他愛ない、だが未だに生々しい記憶に目眩がする。 新しい職場でなめられないように、と気負って出勤してきた今朝の決心が、後悔やら懐かしさやらのセンチメンタルな色に塗りかえられてしまったのを感じた。 連れて行かれたのは会社から少し離れた寿司屋だった。手頃なランチセットが人気らしく、店内はOLやサラリーマンで賑わっていた。 植村は慣れた様子で空いたカウンターに陣取ると、真崎に断りもなく、お茶を運んできた女店員に「セット二つ」と注文した。 熱いおしぼりで手を拭うと、植村は前を向いたまま、「Mだって?」とたずねてきた。 「はあ」 「なんでうちなんかに来た? あっちの方が会社としても一流だし、給料だっていいだろ」 「財閥系は風通し悪いし。なんかあんまりやりたいことやらせてもらえなくて。そこそこ成績は上げてたけど、上司とも反りが合わなかったんです。そんなときにここの取り引き先から話を聞いて」 「それでうちへか。物好きだな。歴史はあるがうちなんざせいぜい中堅どころだぜ」 「体は小さいほうがフットワークがいいんです。Mなんて古い因習に縛られて、絶滅寸前の肥大化した恐竜だ」 真崎が強い口調で言うと、植村は「ずいぶん生意気な口をきくんだな」と笑みを浮かべた。 「商社なんかこの時代、どこも青息吐息さ。うちだっていつ危なくなるか知らないぜ」 「だけど何とか危機を乗り越えようとふんばっている、そうでしょう? ここの会社独自の新しい開発部門は業界でも注目されつつある」 「まだ試行錯誤している段階さ。失敗すりゃ会社もろともって可能性もある」 「リスクを冒さなければ人に抜きん出ることはできません」 真崎がきっぱり断言すると、植村は今度こそはっきり声に出して笑った。 「変わらないな。おまえのそういうところが――」 そう言ってふいに口をつぐんだ。 「セン……」 思わず先生、と言いかけて、真崎はさすがに「植村さん」と言い直した。 「植村さん、あの……」 「よせ」 植村の声は鋭かった。 その冷ややかな口調と眼差しで、二人の間の温度は一度か二度、確実に下がった。 「おまえのしようとしている話を、俺が聞いて楽しいと思うか」 真崎は考え込み、しばらくしてかぶりを振った。 「なら黙っとけ。何もおまえが昔の教え子だったことを隠したいわけじゃない。だが八年前のあのことは……俺にとっては汚点だ」 ぴしゃりと言い切られ、真崎は青ざめたまま、何も言えなかった。 男である植村と寝ながら、高校生だった真崎はあまりそのことを深く考えていなかった。考えられなかったと言ってもいい。 なぜ植村が断らなかったのか不思議に思うことはあっても、理由を突き詰めることはしなかった。 同性同士は互いに初めてということだったが、体の相性は良かったのだろう。探るように相手の快感を高め合う作業は楽しかった。 抱くのはもっぱら自分だったが、だからと言って二人の立場が逆転するようなことはなかった。 情事に誘うのが自分でも、関係のイニシアチブは植村が握っていた。彼は自分がその気になったときだけ、そして勉強の妨げにならないと判断したときだけ、ベッドの相手をした。 だがそれで真崎が不満に思うことはなかった。女のようにしつこくしない、体の関係を結んでもなびかない植村は新鮮な上に付き合いやすかったし、普段冷静な分、自分の下で見せる彼の熱っぽい表情がたまらなかった。 ばかな、若いガキだった。 ちょっとは考えれば良かったのに。未発達な脳みそを働かせれば良かったのに。 あの日、母親が留守なのをいいことに、真崎は自室にガールフレンドを連れこんでいた。定期試験前ということで、自分が無理を言って家庭教師の回数を増やしてもらっていたことをすっかり忘れていたのだった。 軽いノックの音がして、ドアを開けた植村と目が合ったとき、真崎はベッドの上で女の子のブラジャーを押し上げたところだった。 一瞬、わずかに目を見開いた植村は「失礼」と言ってドアを閉め、そのまま階段を下りていった。 罪悪感はまったくなかったが、さすがに気まずかったので、次の日彼が来たら何と言おうか、とさまざまな言い訳を考えた。 だが翌日帰宅した彼を待っていたのは「植村先生、おやめになるんですって」という母親のひとことだった。 「な、なんで?」 「なんでも家庭の事情ですって。残念ね。あんたも懐いて成績も上がってたのに」 植村は真崎が学校に行っている間に挨拶に来たという。 真崎はあわてて派遣センターに電話をかけた。教師と家庭が直接交渉することを嫌う会社は、派遣員が自分の連絡先を明かすことを禁じており、真面目な植村は真崎に電話番号すら教えていなかった。 昨日の今日では、彼がやめる理由は一つしか思い当たらない。だが授業の約束を忘れていたくらいで、女の子の服を脱がしていたくらいで、あの冷静な植村がそんなに怒るだろうか。真崎にはどうしてもそれがピンとこなかった。 派遣センターの事務員は母親の言葉を裏付けただけだった。担当教師の急な変更を詫び、すぐに代わりの人間を派遣すると言ったが、植村の連絡先だけはがんとして教えてくれなかった。こちらが食い下がると、逆に何かあるのかと怪しんできた。 真崎は愕然とした。植村は本当にやめてしまったのだ。自分にひとことも言わずに。 彼の突然な仕打ちに腹さえ立った。こんなふうに投げ出すなんて無責任じゃないか、とすら思った。 だが一週間経った後、真崎は放課後私服に着替え、電車に乗って、名前だけ聞いていた植村の大学をたずねていった。 しかし広大なキャンパスで彼の姿など見つかるはずもなく、学生課でも「部外者には教えられません」とそっけなく断られた。 自分と植村との関係など誰一人知らぬ年上の人間ばかりが行き交う構内で、真崎は初めて自分が失くしたものの正体を知った。 彼の下について一カ月が過ぎた。その間植村は真崎を得意先に連れまわし、さまざまなことを教えてくれたが、八年前のことをちょっとでも匂わすと、ぴしゃりと鼻先でドアを閉めた。 初めは諦めきれなかった真崎も、そのうち仕方ないと思うようになった。彼にとってあれが思い出したくない過去だというのなら、自分もそれに従うしかない。植村とは会社の先輩後輩という新しい関係を築けばよい。 実際仕事の話に限って言えば、彼との毎日は刺激的だった。食事を一緒にしながら交わす忌憚ない会話は、相手が一線にいるだけに学ぶことが多かった。植村ですら、自分とのそうした時間を楽しんでいるように見えた。 だがほんの時折、彼がソースをかけるときの指の節だとか、耳にかけた眼鏡の蔓を直す仕草などを見るたび、埋み火のように自分の中でくすぶる何かがあった。 真崎は忙しい毎日にまぎらわせ、その火を必死に灰の奥底へと埋めた。 ある日の午後、二人はTという食品会社の製造工場へと出向いていた。 真崎がここを訪れるのは二度目で、すでに工場次長だという西井という男に紹介されていた。 植村はこれまでに何度か物流機械を納品しているらしく、西井との間には良好な人間関係が結ばれているようだった。 「ちょっといいかな」 西井はそんなふうに言って二人を工場の一画に連れていった。 「他ならぬ植村君だから相談するんだけどね」 西井は老朽化したパレタイジングロボットを指差して言った。パレタイジングロボットというのは、ダンボールなどをパレット(荷台)に積む機械のことである。 「そろそろこれを入れ替えようか、という話が出てるんだが、ご覧の通りスペースにあまり余裕がない。一応候補に上がってるのがスイスのメーカーの奴なんだが、こいつが馬鹿高くてね」 西井は植村の肩に手をまわすと、「なんとかならないかな」と言った。 植村はしばらくロボットを見上げていたが、やがて「一つ心当たりがあります」と答えた。 「予算はその半分程度で済むと思いますよ。ただし納期は半年ほどいただきますが」 西井は「そうかね、そりゃ助かる」と喜んだ。 そこからの植村は素早かった。すぐに見積もりを提出する約束を取りつける。上司の許可を待たずに一切を自分の裁量で行う、最前線で働く商社マンとしての自信と実力がそこにはあった。 Mでは、決まりきった顧客相手にルートセールス(巡回販売)の仕事しかしてこなかった真崎は、このような取引きを目の当たりするのは初めてで、興奮が隠せない思いだった。 「さすが植村さんですね」 会社へ戻る車を運転しながら、真崎は感心したように言った。Tで話が長引いた分、すでに日が沈み始めていた。 「何が」 「西井さんの希望にそうような機械がすぐに思い当たるなんて。いったいどれだけのカタログを頭に詰め込んでいるんですか」 「そんなものはない」 植村の口調はそっけなかったが、どこか面白がっているような響きもあった。 「え? ないって?」 「心当たりなんてない。あれは嘘だ」 「嘘ってそんな……」 驚いた真崎は危うく降り始めた遮断機を見逃すところだった。慌ててブレーキを踏むと、車体ががくん、と揺れた。 「だって、どうすんですか、納入……」 「作るんだよ」 「作るって、ちょっと、植村さん!」 「とりあえずうちの開発部に話を通す。それで駄目ならそこらの機械屋にあたってみる」 真崎は自分の耳が信じられなかった。何という大胆なことをこの人はやろうと言うのだろう。 カンカンカンカン、という警報機の音が窓の外でうるさいくらいに鳴り響いている。 「だって、もし西井さんが他の工場で動いている機械を見たいって言ったら……」 「言わないよ、西井さんは」 植村は自信たっぷりに言った。車体が揺れたせいで落ちてきた前髪を、すっと後ろへかきあげる。 「あの人との間には信頼関係があるから。もちろん今回の件が失敗すればそれも水の泡だけど」 だけどな、と、植村は左手を額においたまま、助手席からこちらを見やった。 「おまえが言ったとおり、リスクを冒さなきゃ人の先に立つことはできない」 そうだろう? 〝ルートセールス〟の坊や。 そう言ってにやりと笑った植村の顔の片側を、轟音をあげて通りすぎる車両の明かりが照らしていく。 かっと頬が熱くなったのは、馬鹿にされたと思ったからなのか、挑むような彼の笑みに見惚れてしまったからなのか、多分その両方なのだろう、と真崎は思った。 予想通り、開発部からは色よい返事がもらえなかった。 だが植村はたいして落胆した様子も見せず、取引きのある工場へ片っ端から問い合わせる。それでもらちが明かないとわかると、真崎を連れて直接機械屋や電気屋を訪ね歩いた。 とうとう彼の熱意にほだされた小さな会社が首を縦に振った。植村が計画の一段階を自分の足で突破した瞬間だった。 そしてちょうどその夜、部での真崎の歓迎会が開かれた。 彼が配属されて随分経つのだからかなり遅い歓迎会だったが、部内の人間が皆多忙を極める産業設備二部にあってはようやく空いたスケジュールだったのだ。 もっとも歓迎会というのは皆で飲むための口実らしく、部長と真崎がそれらしき挨拶を述べて皆で乾杯したあとは無礼講となった。 おまけに部外の人間も顔を出しており、店内には事務職の女の子たちの姿もあった。 「こんにちはぁ」 そういう女性たちは目的もはっきりしているようで、早速ビール片手に真崎の隣へやってきた。 真崎も嫌いではないからにこやかに応対する。 「真崎君て、Mにいたんでしょう、すごいよね」 「学校どこ?」 「身長いくつ?」 「ご自宅なの?」 矢継ぎ早の質問に、自慢にならないよう、だが無礼にならない程度に答えていく。こういうのはお手のものなのだ。 「だけど植村さんといい、真崎君といい、産設二部っていい男率が高いよね」 「植村さん?」 「そう。白状しちゃうとね、ここにも植村さん目当てで来たの。でも真崎も噂通りかっこよくてびっくり……」 真崎は苦笑いしながら目線だけで植村の姿を探した。 彼は向こうのテーブルで、自分と同じように二三人の女の子に囲まれていた。真崎に視線に気づくと、ほんの少し片方の眉を上げてみせる。 真崎もビールの入ったコップをわずかに持ち上げ、それに応えた。 「植村さん、またすごい取引きまとめたんだって?」 「知ってるんだ?」 「ちょっとだけ。さっき部の人が話してたの聞こえちゃったから」 すぐ右脇にいた子がぺろっと舌を出した。 「秘密だよ」 わかってます、と唇を尖らせる仕草がかわいい。真崎は適度に疲労した体にアルコールがまわってくるのを感じた。 「でもやっぱり植村さんはすごいよね」 「〝マグロの植村〟だもん」 くすくすと笑い声が起こる。 「あ、それ聞いた。どういう意味? マグロって」 「マグロって常に前に向かって泳いでないと死んじゃうんでしょ? 彼ってほら、猪突猛進タイプだから」 「見かけはそんな風でもないのにねぇ」 そういえば、と真崎はふいに思い出した。 彼は学生時代からそんなところがあった。普段はあれだけクールで冷静なのに、時折熱に浮かされたように子供の真崎に将来の夢を語った。アジアやアフリカの現地へ出向き、日本の顔として商品を売り込みたい、そんな風に言っていた。 真崎が就職時に悩み、最終的に商社を選んだのも、そんな植村の言葉が頭のどこかに残っていたからだろう。まさかそのおかげで再会するとは思ってもみなかったが……。 「猪突猛進って言っても、植村さんは向こう見ずなわけじゃないよ。それだけの実績がある人なんだから」 真崎がやさしくたしなめるように言うと、女の子は「あ、ごめんなさい」と素直に謝った。 「悪い意味で言ったんじゃないんだけど……」 「うん、わかってるよ」 真崎はそう言いながら、改めて右側に座っていたその子の顔を見た。 肩までの柔らかそうな髪、華美ではないが女らしいスーツ。素直にいいな、と思える。 以前付き合っていた彼女とは、転職前に別れていた。久しぶりに女性の甘い匂いを身近で嗅ぎ、もう三ヶ月も女性に触れていないことに気づく。 だが、そんな真崎の注意を引いたのは、さり気なく席を立つ植村の姿だった。 見ていると静かに外へ出て行く。 「あ、ちょっとごめん」 真崎はそんなふうに周囲に断って立ち上がった。 居酒屋のドアを開けると、春だというのにひやりとした夜気が真崎を包んだ。思わずぶるっと震え、上着を持ってくれば良かったと後悔する。 辺りを見まわすと、少し離れたガードレールに座って、植村が煙草を吸っていた。 真崎と同じワイシャツ一枚の姿が暗がりに白く浮かんでいる。 「真崎か」 近づいてくるのが誰かを知ると、植村は煙草を咥えたまま呟いた。 「植村さんが煙草を吸うなんて知りませんでした」 「ああ、普段はな。ただなぜか人が多いところにいると吸いたくなるんだ」 真崎は彼と並んでガードレールに腰かけ、長い脚を投げ出した。 「一本もらえます?」 「やめたのか」 植村はそう言ってパッケージを差し出した。彼は高校時代の真崎が親の目を盗んで吸っていたのを知っているのだ。 真崎が指に挟んだ一本に、植村はライターを取り出して火をつけてくれた。かちり、とライターの蓋を閉じる金属質な音がして、植村の体が離れていく。 「植村さん……」 真崎は衝動的に口にしていた。 「植村さん、俺はずっとあんたに会いたかった。会って謝りたかった」 明らかに八年前のことを話しているのに、植村は今度はやめろとは言わなかった。ただ聞いているのかいないのかわからないような素振りで黙って横で煙草をふかしていた。 「あんたは聞きたくない話でしょうけど、今だけ、今晩だけ言わせてください。もう二度と言わないから。明日からはまた、ただの後輩に戻るから。あんたは何も言わなくていい、ただ聞いてくれるだけでいいから」 真崎はそこでいったん植村の方を向いた。 その横顔は無表情で、ただ時折ふうっと唇から細く白い煙を吐いていた。 真崎はまた体を元に戻し、ビルの隙間から覗く黒い夜空をじっと見上げながら口を開いた。 「あんたがいなくなったとき、俺は勝手に腹を立てました。こんな仕打ちをされる覚えはないって。あんたのことなんてもう放っておこうって思いました。俺が授業を忘れてたことや女の子とよろしくやってたことで怒っているなら、俺にそう言うべきだと思ったんです。黙って姿をくらますんじゃなくて」 繁華街を酔っ払いの団体や女連れの集団が声高に通りすぎる。ガードレールに腰かけた長身の二人連れなど、誰も見向きもしない。 「それでも我慢できなくなって、結局俺はあんたを探しました。派遣センターや……知ってました? 俺、あんたの大学にまで行ったんですよ。でも見つからなかった。それまでは何となく、またあんたが目の前に現れるような気がしてました。会ってもし怒ってるなら、謝ってもいいだなんて不遜なことを考えていた……」 でも、本当に、もう二度と会えないとわかったとき……。 「しばらくして、あんたがもう本当に俺とは終わりにしたんだって気づいたとき、ショックでした。いや、ショックなんてもんじゃなかったな。親にも、友達にも、新しく来た家庭教師にも八つ当たりして、成績だってめちゃくちゃ落とした。そんなにしても、もう戻ってこないのが信じられなかった。俺のだいじなもの――」 真崎はため息をついた。レールについた手がわずかに震えている。もう八年も経つのに、あの若い傷心を思い出すと今でも心が痛むのだった。 いや、こうして植村の隣にいると、酔いもあってか十七の頃に戻ったような気がした。残酷なほど無神経で、そのくせ自分だけは傷つきやすかったあの頃。 「失くしてわかるなんて陳腐な歌の歌詞じゃないけど、そんなことすら、ガキだった俺にはわからなかった。好きだったことも気づかなかったなんて、中坊じゃあるまいし、笑える……」 真崎は気づかれないように、煙草を持った手の親指で目尻を拭った。摂取したアルコールが体内をめぐり、そんなところから滲み出ていた。 「大切にすればどうにでも育てていけたものを、自分が壊したんだって、認めるのは辛かった。でも認めないわけにはいかないでしょう? それとも俺もそこまで馬鹿じゃなかったってことかな。もう遅かったけど……」 俺はね、植村さん、と真崎は視線を落とした。 「今度大事な人ができたら、もう二度と後悔しないよう、絶対に大切にするって誓ったんですよ。目先の楽しいことばっかり追って、自分の気持ちに気づかないで失敗するなんて、二度とごめんですからね」 投げ出した脚の先の、革靴のつま先を見つめる。 「あんたは八年前のことを汚点だって言うけど、俺にとっては違います。馬鹿な俺の目を開いてくれたからってだけじゃないですよ。俺にとってあれは――後悔してもしきれない辛い過ちだけど――でも、大事な思い出なんです」 真崎が言葉を切って黙り込むと、そうか、という静かな声がした。 植村の返事はそれだけだった。何も言わずに立って足元で煙草を踏み消すと、そのまま店内へ戻っていく。 これでいい、とその背を見送りながら真崎は思った。 本当は、本当は、まだ言いたいことはあった。植村に確かめたいこともあった。 だがこれ以上は口を噤むことが、黙って聞くだけは聞いてくれた植村に対する礼儀のように思えた。そして八年前の謝罪のようにも。 力なく下がった右手の先で、一度も吸われなかった煙草の灰が、赤く燃えてアスファルトに落ちた。 |
| 1 / 2 / 3 / NOVEL / HOME |