| 1 / 2 / 3 / NOVEL / HOME |
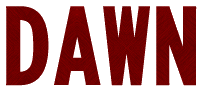 -3- 昼はケータと勉強、夜は加西とセックス。そんな毎日を過ごしながら、十日ほどが過ぎた。俺の無節操な体はこの新たなパターンを覚えはじめ、懸念や疑問はあったにしろ、他はたいした不満もなく、離れでおとなしく飼われていた。 ふと気づくとケータや加西がこちらをじっと見つめていることがある。だが俺にはその意味がわからなかった。 「出かけるぜ。支度しろ……たって、おまえはそのままでいいか」 珍しく家にいたのか、昼前に加西が姿を現した。 「出かける……どこへ?」 まさか、要のところへ? 不安が黒雲のように胸にわいてくる。 「特にどこってわけじゃあねえが……。たまにはおまえを外に出すのもいいと思ってな。外でメシでも食うか。ケータ、おまえもだ。今日はうるさい連中はおいていく。おまえが運転しろ」 「俺も?」 ケータは驚いたようだったが、声には嬉しさがにじんでいた。 ここに連れて来られたときのような大きな車を、ケータは慣れた手つきで運転した。後部座席には俺と加西。 しばらく走ってどこかの繁華街へ出ると、車は路上に止まった。車外へ出るとき、加西がかなり長い間背後を眺めていたように感じたのだが、気のせいだったかもしれない。どちらにしろ俺はそれどころではなかった。 昼日中にこんな町中を歩くのは本当に何年ぶりかだったので、俺は興奮すると同時に少し怖くもあった。その上人々がちらちらとこちらを見るのでどうも落ちつかない。 二人に慣れてしまっていたせいなのか、家にいるときは気づかなかったが、加西もケータもやはり周囲からはかなり浮いている。 体も大きく辺りを睥睨するような、いかにも危ない感じの加西はもちろん、あんなに人懐こく見えたケータでさえ、歩き方とか周囲を見る目つきが、一般人と比べて異質だった。 「郁、みんながおまえを見てるぜ」 肩に手をまわして抱き寄せながら、加西がおもしろそうに言った。 「違うよ、二人を見てるんだよ。俺は今日は普通の格好してるんだし……」 正直女の姿をしているときはじろじろ眺められるのには慣れていた。だが今日はケータとたいして変わらないような服装をしているのだ。 それともやはりちゃんとした男には見えないんだろうか。そう思うと少し心が沈んだ。 うつむいたまま連れて行かれたのは、中華料理屋だった。高い店なのかもしれないが、すでに食事というものには無感動になっていた俺は、個室であったことが何よりも嬉しかった。 それより驚いたのは二人の食欲で、彼らと一緒にものを食べるのは初めてだったが、次々と運ばれてくる料理を片っ端から平らげていくスピードには開いた口が塞がらなかった。 加西がそんな俺の口へ、時折思い出したように料理を放りこんでいく。 「郁って食細いよな。だからそんなに華奢なのか?」 鮭炒飯を頬張りながら、ケータがもごもごと言う。 「ああ。抱いてると骨当たって痛いときあるな」 加西がそう言うと、ケータは苦笑いした。 俺と加西が寝ていることについて最初は慣れない様子だったケータも、近頃はどうやら当たり前のこととして受けとめ始めたらしい。 午前中参考書を開きながらぼんやりしていると、「昨夜は激しかったのか」などと冗談を飛ばしてくることさえあった。 どうやら俺をからかいたいらしく、こちらが平然としていると、とたんつまらなそうな顔になるのだが。 海老を食べたせいで手がべとついていた俺は、食事のあとトイレに立った。 紳士用トイレはどこか落ちつかず、手早く手を洗って廊下へ出る。 どうやら個室のドアをしっかりと閉めてこなかったらしい。近づくと、開いた扉から、加西がケータの耳元に顔を寄せて何か言っているのが見えた。 ケータが驚いたように加西の顔を見やる。だが再び何かを言われて黙って頷いていた。 内々の話なのかと思い、しばらく待ってから席に戻ると、加西が「買い物にでも行くか。欲しいもんがあれば買ってやるぞ」と言い出した。 すぐに屋敷に戻るのだと思っていた俺は驚いた。そんなことを言われても、欲しいものなどない。 「何にもないのか。つまんないやつだな。行きたいところとかないのか」 妙にしつこい加西に閉口した俺は、あ、と思いついて声をあげた。 「じゃあ、本屋。本屋に行きたい」 「本屋ぁ? ケータ、ここらにあったか?」 「駅の方にでかいのがあるっすよ」 「よし、じゃあそこにしよう」 料理屋を出て車に戻る。車内のケータは妙に静かで、神経質そうに何度もバックミラーの位置を直していた。 本屋は五分ほどのところにあった。車が止まると加西は、 「俺は待ってるからケータについていってもらえ」 と、車を出ようとはしなかった。あれ、とは思ったが、興味のない買い物に付き合うのは面倒だったのだろう。 財布を預かったケータと俺は、二人で通りを渡り、本屋へと入った。一階は混雑していたが、店内案内図で確かめて二階へ上がると、そこは人もまばらだった。 「参考書?」 俺の向かった棚を見て、ケータが不思議そうな声を出す。 「うん、ケータ、そろそろ中3のも買っておこうよ。もう因数分解とか入ってもよさそうだし。あ、他の科目は? 英語とかはいいの? 俺、たいがい何でも教えられるよ?」 返事がないので振りかえると、ケータはパーカーのポケットに両手を突っ込んだまま、妙な顔をして立っていた。 「本が欲しいって俺のだったのか?」 「うん、そうだよ。加西の金でケータの本買うと、まずい?」 「いや、そんなことはないと思うけど……。なんなら俺が払ってもいいし」 ケータはしばらくためらっていたが、やがて俺の脇に並ぶと、一緒に本を選び始めた。 数学の参考書と、英語と漢字の問題集を選んだところで、ふいにケータがトイレに行きたいと言い出した。 「さっきの店で行っとけばよかったのに」 「うん、なんか急に腹が痛くなってさ。金払っといてくれるか? 会計、できるよな」 「できるよ」 唇を尖らせながら、差し出された一万円札を受け取る。 「レジのとこで待ってるからね」 背を向けたケータへそう声をかけた。 だが少々緊張しながら会計を済ませても、ケータは一向に戻ってこなかった。 柱の時計で二十分を過ぎるとだんだん心配になってきて、俺は買った参考書類を抱えたまま、トイレを覗きにいった。 だがケータの姿はなかった。 どうしたんだろう。お腹が痛いと言っていたけれど、具合が悪くなったんだろうか。 俺はもう一度レジのところに戻ってそこからさらに十分待ったが、やはりケータは現れなかった。 先ほどから店員の視線が痛い。それにこれ以上遅くなると車に残っている加西が心配するかもしれない。 俺はそう思って、いったん車へ戻ることにした。 きょろきょろとケータの姿を探しながら階下へ下りる。店のドアを開けて通りの向こうを見ると、黒い車の脇に立つ黄色いパーカー姿があった。 「ケー……」 「彩香」 俺は凍りついた。 「彩香」 手にしていた書店の袋が音をたてて地面へと落ちる。通りすがりの何人かが振りかえったようだったが、俺の目には入らなかった。 俺はただ、通りの向こうに停まったままの、黒い車体を見ていた。 「彩香。探したぞ。さあ帰ろう」 無抵抗の俺の腕を、要は優しく、だが有無を言わさぬ力で背後から引っ張った。 ずるずると引きずられながら、俺は必死で車を見ていた。 見ていたのはその脇に立つ少年ではない、スモークの貼られた黒いガラスの奥の、見えないはずの男の姿だ。 「彩香。さあ」 要が呼ぶ。彼に命じられたら俺は逆らうことはできない。ただ一縷の望みにすがって、ひたすらに待った。 あの車の後部ドアが開くのを。 少し離れたところに停めてあった車に押し込められるまで、俺は待ち続けた。 だが、ドアは開かなかった。 藤城邸に着いて外へ引きずり出される段になって初めて、俺は助手席に乗せられていたことに気づいた。運転していたのは要本人だ。こんなことは今までになかった。運転手はどうしたのだろう。 屋敷内はひっそりとしていた。玄関のドアを乱暴に開けても、いつもかけつけてくる使用人たちの姿はない。 「か、要、ナミさんはどうしたの?」 「あんな女はやめさせた」 「ほっ、他の人はっ……」 「いない。俺はもう終わりだ」 要は吐き捨てるように言った。 俺はその口調に驚いて、思わず彼の顔を見上げた。 いつも首元まできちんと締められていたネクタイは緩み、頭髪も乱れている。顎にはうっすらと不精髭すら浮いていた。 「俺には、もう、おまえしかいないんだよ。彩香」 彼はそう言うと、玄関から近い客間へと俺を引きずりこんだ。 「やめて! 要! やめて!」 俺は毛足の長い絨毯の上に押し倒されながら、必死で抗おうとした。 だが、パン、と左頬を張られると、条件反射のように彼への恐怖が先に立った。 「うるさい。お兄さまと呼べと言っているだろう」 要は自分のネクタイとベルトで、俺の左右の腕をそれぞれソファの足に結びつけた。 そして立って壁際へ近づき、何か光るものを手に戻ってきた。 俺はすくみ上がった。 それは装飾用カトラリーの中の、テーブルナイフだった。 「お……お兄さま、ごめんなさい……ごめんなさい……」 要は俺の上にまたがると、忌々しそうに着ているものを裂いていった。 「こんなものを着て……俺の買ってやった服はどうした!?」 ボルドーのラインの入った紺のトレーナー、グレーのシャツ。オリーブ色の綿ズボン。さすがに食卓用ナイフではきれいに切り裂くというわけにはいかず、要は半ば引き千切るようにして俺を剥いていった。 そして裸になった胸へナイフの刃を滑らせる。 まだ傷はつかなかったが、俺の目尻に涙が浮かんだ。 以前にも体を傷つけられたことはある。だがその時は要自慢のジャックナイフが使われ、おそろしく切れ味のいいその刃先はなでるだけで血がにじみ、かえってわずかな怪我で済んだ。 だがテーブルナイフのような鈍い刃物で傷をつけようと思ったら、それなりの力をこめなくてはならない。 俺は要の正気と加減が信じられず、殺されてしまうかもしれない、と思った。 が、彼はナイフの先で乳首を弄り、しばらく恐怖に固まっている俺の表情を堪能すると、それをぽい、と脇へ投げ捨てた。 そのまま上体を倒し、喉元に唇を寄せてくる。 「彩香、かわいい彩香……」 ほっそりと柔らかな手のひらでわき腹をなでながら、顔や首、胸や腹を舐めまわす。その粘着質な気持ち悪さに、俺は両手を頭上でしばられたまま、唇を噛んで必死に耐えていた。 嫌だった。 思わず叫びだしそうだった。 こんなことはなんでもないはずなのに。体を切り刻まれるより、鞭で叩かれるより、触ったり舐められたりする方がずっとましなはずなのに。 俺の体はわずか十日で馴染んでしまった、もっとごつごつした、もっと大きな、そしてもっと乱暴な手のひらの感触を恋しがっていた。 要が内腿を舐めようと尻に手をやった瞬間、俺は無意識にびくりと体を震わせた。 その反応に要は頭を上げて俺の顔を見た。 目が合う。 彼は眉をひそめて、さらに手を奥に進めた。 俺は思わずそれを阻止しようと下半身をよじらせた。 細い指が、入口に触れる。 「い、嫌だっ……」 俺はさらに足をばたつかせた。 「彩香、おまえ……!」 要はがっと俺の顎を掴んだ。 「加西だな!」 その名に、体が震える。 「おまえ、やつと寝たのか!」 普通の人間なら細い血管の浮かんでいる白目の部分が、兄の場合は異様に白かった。俺はいつも気味悪く感じていたものだ。 その白い目がじっと俺を見据えた。 「加西と寝たんだな」 体がこわばる。 「言え! 彩香。あのやくざと寝たな!」 俺は震えながら頷いた。 「そうか。それで……」 きれいに整えられた爪の先が、俺のそこをぐっと開いた。 「ここに入れさせたんだな」 俺は頷けなかった。ただ、頭に浮かんだのは、「要にセックスされてしまう」そのことだけだった。 セックス。 セックス。 セックス。 加西とのセックス。 「嫌だ、やめろ!」 俺は必死で抗おうとした。 しばられた腕を力をこめて引っ張り、足を振り上げて自分の上から要を蹴り落とそうとした。 だが革のソファは絶望的なほど重く、一瞬驚いたようだった要も、難なく俺の抵抗を抑え込んだ。 今ほど自分の非力さ加減を呪ったことはない。俺は本当に女みたいに無力だった。 両足が大きく開かれ、その間に要の体が入りこんだ。ファスナーの下りる音がする。 「やめろ、要……やめて……やめて……あやまるから。お兄さま、ごめんなさい、あやまるから、何でもするから……お願い、お願い、お願い……」 二本の指が乱暴に差しこまれ、左右に開かれた。激痛が走る。そしてそこへ濡れたものが押し当てられた。 吐き気がこみあげた。 絶望感に目をつぶる。 先端で襞をなぞられて鳥肌が立つ。 ――だが、いくら待ってもそのときはやって来なかった。 何度も何度もそこに性器の先が押し当てられるのに、一向に奥へと押し入ろうとはしない。 俺は不審に思って、ぶるぶる震えながら目を開けた。 下半身を見ると、髪を乱した要が何やらぶつぶつ言っている。何度も俺の後ろに性器をあてがいながら、そのたびに躊躇している。 そしてしまいにとうとう諦めたらしく、「くそっ、あの変態野郎め!」と吐き捨てて顔を上げた。 汗だくになり、額に乱れた前髪の張りついた兄の顔を、この五年間自分の主として君臨してきた絶対君主の顔を、俺はまじまじと見つめた。 なんだ、と思った。 なんてみじめな、情けない顔だろう、と感じた。 彼がなぜ挿入しないのか、その理由はわからない。 勃起できなかったのか、それとも男同士でそこまでやることに今更抵抗があるのか、彼のタブーが何かなど、俺にはわからない。 ただ、わかるのは、彼には俺が犯せない、それだけだった。 こいつは俺を犯せない。加西を変態と罵りながら、そうしたくても自分はできないのだ。 「ハハハハハハハ!」 俺の唇を割って、笑い声が飛び出した。 要がぎょっとしたようにこちらを見た。 俺は目を逸らさずに笑い続けた。 男の顔が、かっと朱色に染まった。 何も言わなくても、それが嘲笑であることは間違いなく伝わっただろう。 「こいつ……!」 要は俺の喉元に飛びかかった。 「ぐっ……」 いきなり力をこめられて、舌が飛び出す。 「俺をそんな目で見るな! 許さないぞ、彩香。おまえは俺のものだ!」 「……か、じゃない……」 「なに?」 「俺は…あや、か、じゃない……郁だっ…」 ぐぐっと締め上げられる。 ものすごい勢いで目の前が白くなり、やばい、と思ったとき、 「そこまでにしとけよ」 という声がした。 ふいに要の力が緩んだ。息を吸おうとして嘔気が起こり、俺はむせて咳き込むと、仰向けのまま何度もえずいた。 「おいおい、大丈夫かよ」 生理的な涙のにじむ目をかすかに開けた。目の前がちかちかしていてよく見えない。だが、男の声だけは聞き分けられた。 「郁。すてきな格好だな。やられちまったか?」 俺は加西の声に首を左右に振った。 「未遂か。グッドタイミングっつうやつだな」 絨毯に横たわり、両手をしばられたまま左右を見上げると、見知らぬ男たちの顔があった。 スーツ姿の強面たちが、素っ裸で両足の間に男をはさんだ俺を、無表情に見下ろしている。 俺はわずかに頭を起こして足元を見た。 腹の上に、真っ青な顔をした要。その手はまだ俺の首元に絡んでいる。そしてその背後に立っているのは――。 「加西」 俺が呼ぶと、彼はおう、と答えた。 「加西、なんで……」 なんで俺を連れ出したの? なんで助けてくれなかったの? なんで来てくれたの? なんで――。 「おまえに選ばせてやろうと思ってな」 低い、静かな声だった。だが、どこか面白がっているような響きもある。 「この男から、本当に自由になるには、おまえが自分で選ぶ必要があるのさ」 「あ、あやか……」 要が震える声で俺を呼んだ。なぜ彼はそんなに怯えているのだろう。 「これは俺にとっては仕事だが、最後はおまえに選ばせてやろう、郁」 がちり、と要の顔の後ろあたりで金属質な音がした。見ると、加西は何かを彼の後頭部に突きつけているようだった。 「おまえがいいと言えば、俺は引き金を引く」 「彩香!」 「そうすればこの男はおまえの前から消える。おまえは自由だ。どうする、郁」 「彩香!」 俺は要の顔を見た。長い間俺を支配してきた男の顔だった。俺を玩具にし、屋敷に閉じ込めて、女のように精神を腐らせた男の顔だ。 このみじめな男のどこに、そんな力があったのだろう。 俺は口を開いた。 その瞬間、要が再び喉にまわした手に力をこめた。あの白い目を剥き出しにして、俺を睨みつけてくる。 そこに浮かんでいるのは、焦燥なのか、それとも執着だろうか。 「んんっ……ぐっ!」 加西は彼を止めなかった。ただ、待っているのだ。俺のひとことを。 「……ってっ…」 「彩香、彩香、彩香!!」 「撃ってっ、加西!」 俺は結局銃声を聞かなかった。喉首を圧迫され、目の前が真っ暗になって、男の重みを感じたまま、その場で気を失った。 眼前の男はしぶい顔をしていた。 「加西さん。わしはこの女の始末も頼んだはずだが。藤城の兄妹を二人とも片づけてほしかったんだがね」 向かいのソファに腰を下ろしているのは、水嶋隆文。ついこの間まで水嶋の叔父と呼んでいた男だ。藤代要の失踪でグループ総帥の座は空いているが、いずれそこへおさまるのは彼というわけだ。 「それですがね」 俺の横に座っていた加西が灰皿で煙草をもみ消しながら言った。 「この娘は藤城とは何の血のつながりもないんですよ」 加西の言葉に、水嶋はまさか、という顔をした。 「わしの兄がその娘を認知したはずだぞ」 「認知したのは藤城彩香でしょう。彼女はすでに死亡している。死因はわかりませんが、藤城はその死体を極秘に始末したようだ。この娘は赤の他人です。血液判定の結果も出ている」 「他人? 赤の他人だと? じゃあいったい誰なんだ?」 水嶋隆文はまだ五十前だ。胴まわりに肉はつき始めているが、その目は野心に燃えている。 「それはあんたは知らなくていいことだ。ただの女ですよ。藤城要が大事に飼っていた、ね」 「あ、愛人だったのか」 俺は水嶋の視線を意識して、さり気なくスカートから伸びた足を組み替えた。今日の役は清楚な令嬢ではない。 「いろいろ噂はあったでしょうが。本当の兄妹じゃなくてかえって良かったくらいだ」 「だが、これからどうする気だ。その娘は危険だぞ。他人ならなおさらだ。知りすぎているからな」 加西はご心配なく、と俺の腰に手を回した。 「こちらで引き取りますよ。下手な口はきかないようしつけますから、ご安心を」 俺は引き寄せられるままに加西の肩に頭をもたせかけ、そのままうっすらと笑って見せた。 「君が、か」 水嶋は俺と加西の顔を交互に見やった。そこに初めて好色そうな表情が浮かんだ。 「これからもうちの組をよろしくご贔屓に、水嶋さん」 「あー、済んだ済んだ」 加西は俺を乱暴に車に押しこむと、続いて自分も乗り込んできた。 「お疲れさまです」 運転席のケータが声をかけた。 「どうします? このまままっすぐ帰ります?」 「んー、そうだな。そのへん適当に走ってくれや」 「そのへん、て……ちょっと兄貴!」 後部座席で俺を押し倒し始めた加西を振り返り、ケータはぎょっとしたように叫んだ。 「やっぱおまえはそういうのが似合うな。水嶋のとこでむらむらしてきて困ったぜ」 加西はそういうと、子供のように俺を抱き上げて自分の膝に乗せ、スカートを捲り上げて手早く下着を引きずり下ろした。今日は加西に買い与えられたドレスだ。それほど露出は多くないのだが、派手で扇情的なデザインである。 「やっぱいいよな、スカートは楽ちんで。すぐヤれる」 加西はそう言って笑うと、自分のシャツも乱暴に脱ぎ捨てた。もちろん俺に刺青を見せて煽るためだ。 「やろうぜ、郁」 「兄貴ってば」 「うるせぇ、嫌なら前向いて耳ふさいでろ」 「耳ふさいだら運転できないですよ〜」 ケータの情けなさそうな声に、俺は思わず笑ってしまった。 ふと、こんな姿を見たらナミさんは何と言うだろうか、と思う。 車の中で、やくざに足を開いている俺。自由になったとは言っても、あいかわらず男に飼われていることは変わっていない。 ふがいない、と叱るだろうか。 女の腐ったような、と憤慨するだろうか。 『十七の男なら、どこでどうやったって生きていけます』 彼女の言葉を思い出す。 そして同じように、五年間兄と呼んだあの男のことを考える。 彼は本当に死んだのだろうか、と。 彼につけられた喉もとの痣はもう消えてしまった。 俺は要の死体を見ていない。世間から、そして俺の前から消えてしまったことは確かだが、もしもう一度藤城要が目の前に現れたとき、俺は自分の力で彼の呪縛から自由でいられるだろうか。 自分が好きなように生きているのだと思いたい。今は無理でも、いつかはそうなりたい。そのために、いつか加西のもとを出たくなったときのために、俺はどうしたらいいのだろう。 「たまんねぇ」 荒い息が肩口に押しつけられる。そんなふうに囁かれて、自分の目も潤んでくるのがわかる。股間をさぐる加西の指がぬるっと滑った。 ケータはいつか大検を受ける、と言っている。一緒に勉強をするのもいいかもしれない。中学も行っていない俺が大学へ行けるかどうかは知らないが、駄目なら他にも道はある。 わわーん、と車内に大音響が流れた。ケータがオーディオのスイッチを入れたのだ。 「あいつ……」 加西が苦笑いした。片手でファスナーを下ろし、もう片方で俺の手を掴んでそこへ誘導する。 それはもうすでに熱く、大きく脈打っていた。 「俺が女の格好してると興奮するんだ?」 ふと思いついて聞いてみる。加西のもとに引き取れられて以来、女装させられるのは初めてだったが、町中の人間が俺を振りかえるたび、加西が共犯者めいた笑みを寄越してくるのが何となく楽しかった。 「そうさ。トイレで初めて見たとき、こりゃあくるなと思ったんだ」 「変態」 「今更だろ」 その会話になぜか安心している俺がいる。 うなじに手が添えられ、ぐっと下へと力がこめられる。俺はかすかに笑みを浮かべながら、促されるまま、ゆっくりと熱くたぎった彼の中心へと唇を寄せていった。 【終】 |
| 1 / 2 / 3 / NOVEL / HOME |