| 1 / 2 / 3 / NOVEL / HOME |
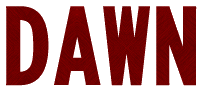 -1- 兄が自分をパーティなどに連れ出すのは珍しかった。機嫌がいいのかと期待したのだが、人々の肩のすきまから覗く白い顔は険しかった。 彼のそばに水嶋の叔父の姿を認め、ああ、と思う。二人の関係はもう修復不可能なところまで行っているらしく、人前でとりすました表情を崩したはずのない兄の眉間に、くっきりと皺が寄っていた。 藤城グループの総帥の座は現在は兄のものだが、その地位が怪しいらしいという噂はどうやら本当のようだ。 経営者としての才腕は父親譲りかもしれないが、性格にああ問題があるのでは無理もないだろう、とベッドの上で自分を撫でまわす兄の変質的な手つきを思い出して考えた。 もし兄が失脚したら自分はどうなるのだろう。また路頭に迷うようなことになるのだろうか。 だがすぐにそんなことはどうでもよくなる。せいぜい今の自分の頭を悩ますのは、今夜の兄の所行ぐらいだった。彼が今晩都内のマンションではなく屋敷の方に戻ってくるのはほぼ間違いないだろうし、そうなれば機嫌の悪い彼の相手をするのは自分の役目なのだ。 慣れたとはいえ、痛い目に合わされるのはやはり嫌だった。 ジュースの入ったコップを片手に壁際で所在なげに立っていたところ、部屋の向こうから近づいてくる若い男の姿を見てうんざりした気分になった。 自分が藤城要(ふじしろかなめ)の妹であることはここにいる人間なら皆気づいているだろうし、それを知っているなら、藤城がその妹を猫可愛がりして屋敷から一歩も外へ出さないという噂も聞いているはずだ。兄の不興を買ってまで自分に近づこうとする輩がいるとは思わなかったのだが、先ほど紹介されたときに青年の目に浮かんでいた熱っぽい光を思い出し、ますます気分が重くなった。 ばかなやつ。 そばにいたボーイを呼びとめ、コップを渡して代わりに化粧室の位置をたずねる。実際下着がずれているような感じがして、先ほどからトイレに行きたかった。 示されたドアを開けて廊下へ抜けると、そこは広間の喧騒が嘘のように人気がなく、静まりかえっていた。運良く婦人化粧室にも誰もいない。それでも用心して個室で下着のストラップを調節した。 広々として清潔な洗面所には大きな鏡がはまっていた。手を洗い、ふと顔を上げると見なれた顔が映っている。 顎のラインまで自然に伸ばされた柔らかな髪。母親譲りの大きな瞳に細い眉。ピンクベージュに塗られた唇。喉から下を覆うのは、華奢な体型をカバーするかのようなゆったりとした、それでいて清楚なイメージを崩さない浅葱色のドレス。シンプルでいながら高級品であることは見間違えようのない、兄の趣味だった。 かすかに眉をひそめてこちらを見返しているのは、どこから見ても藤城彩香(あやか)。妾腹でありながら、ただ一人先代が認知した娘だった。 ふう、と思わずため息をもらした瞬間、背後のドアがばん、と開いてびくりとする。少々酒の入ったご婦人でもやってきたかと鏡の奥を見やった自分の目に映ったのは、思いもかけない光景だった。 スイングしているドアのそばに立っているのは、見たこともない男だった。パーティの客らしくスーツを着ていたが、どこから見ても経済人らしくない。 ずばぬけた長身とがっちりとした肩幅のその体型も、張り出した眉宇の下でぎらついている両の瞳も。 男は、鏡の中で目が合ったことに気づくとにやりと笑った。 思わず剥きだしの腕をかばいたくなるような、ぞっとする笑い方だった。先ほどまで心地のよかった一人きりの空間がふいに心細くなり、助けを求めて周囲を見まわしたくなる。 男は実際にこちらがそうすると思っていたのだろう、睨みつけてやると、わずかに驚いたように眉をあげた。 「お間違えではありませんか? 紳士用はお隣ですよ」 「それを人に言える立場か? おまえが」 男の声は太く低く、決して大声ではなかったが、化粧室内に響きわたった。 なんのこと、そう言おうとして振り向いた顔が、大きな手にがっちりと掴まれた。 「なっ……」 大男のくせに、驚くような敏捷さだった。男は左腕でこちらの腰を抱えこむと、右手でこちらのおとがいをぐっと掴んだ。無理やり顔を上げさせて至近距離で覗きこむ。そんな姿勢を取らされると、身長の差を改めて感じさせられた。 「よく化けたもんだ。実物を見るまでまさかこれほどとは思わなかったぜ」 男の手を振り払おうと体をよじるが、びくともしない。 「きれいな顔だな。どこから見ても藤城の令嬢だ。だがそんなふうに睨むのはやめた方がいい。生まれが野良猫だと白状してるようなもんだぜ」 男は面白そうに人差し指で頬を軽く撫でた。 「どうした、悲鳴もあげないのか。そうだよな、人を呼ばれて俺に正体をばらされちゃ、本も子もないもんな」 「何を、はな――」 次の瞬間、男の手が思いもよらない動きを見せた。ドレスの裾を乱暴に捲り上げ、足の間に手をつっこむ。 「はっは、ビンゴ!」 そう言って片目をつむった男の顔を、驚愕の思いで見上げた。 逃げ出すまでもなく、いきなり拘束が解かれ、突き飛ばされるようにして体が離れる。 男は用は済んだとばかりさっさと背を向け、ドアに手をかけたところで振りかえった。 「俺の名は加西だ。覚えておけ。そのうち迎えに行くからな――郁(いく)」 その名で自分を呼ぶのはもう、一人しかいないはずだった。乱れた服装で大理石の洗面台によりかかる自分の前で、男の姿はドアの向こうに消えた。 男のことは誰にも言わなかった。言えるはずもなかった。兄より先に屋敷に戻った俺は、自室でドレスを脱ぎ捨てた。 「郁さん、要さまは今晩はこちらに?」 床の上のドレスを拾い上げながら、ナミさんがきいてくる。 「たぶんね」 俺がそう答えると、ナミさんは用意していたらしい二組の着替えのうちの一方を取り出した。 ベッドの上に広げてみると、それはサテン地の赤いナイトガウンだった。 「今度はこういう趣味になったのか……」 俺は素っ裸になると、おとなしくそれを身につけた。 「あの方は病気ですよ」 ナミさんは忌々しそうに吐き捨てると、残った着替えを箪笥の一番上の引き出しにしまった。 「明日要さまがお帰りになったらこちらをお召しになってくださいね」 ちらりと見えたが、ありふれた綿素材のシャツとズボンだった。 藤城の家で、たとえこの部屋の中だけのこととはいえ、俺を男として扱うのはナミさんだけだった。 亡き先代の子供だという訴えを聞き入れ、要があっさりと俺を引き取ったときの母親の驚いた顔を、俺は五年たった今でもよく覚えている。 まさか藤城グループの総帥ともあろう人間が、一介のホステスの言葉などを真に受けるとは夢にも思っていなかったのだろう。 先代がいっとき母の客であったことは事実だったようだし、あわよくばスキャンダルの口止め料でも、という気持ちだったに違いない。 だが、要はやせっぽっちの小学生の子供を一目見て、自分のものにすることに決めた。亡くしたばかりの腹違いの妹の代わりに。 母は血液判定など言い出されないうちにと、二度と顔を見せない旨の誓約書にサインしてさっさと姿をくらました。子供の目から見てもずいぶんと美しい女だったが、母性愛とは縁がなかったようだ。 その先息子を待ちうける運命を知っていたら、少しは躊躇しただろうか。今でもときどきそんな風に思う。だが考えてもしかたのないことだ。 当時十ニ才だった俺は、たやすく自分の立場を受け入れた。 要に捨てられたら行き先がないことはわかっていたし、三度三度の温かな食事を捨ててもとの貧乏生活に戻るのは純粋に嫌だった。 俺は買われたペットのごとく、要を唯一絶対の飼い主として認識した。 藤城彩香の戸籍をあてがわれ、女として育てられることも、要の夜の相手をすることも、すぐに当たり前の義務だと思うようになったのだ。 子供の適応力と言うのはおそろしい。ナミさんさえいなかったら、俺は自分のことを股間に余分なもののついた女なのだと思うようになっていたかもしれない。 ナミさんは俺がこの家に来たときからすでに住みこみで働いていた。おそらく五十代くらいなのだろう。家族がいるという話は聞いたことがない。 彼女は俺に繰り返し繰り返し、要の異常性を言ってきかせた。テレビを見せ、マンガや本を買い与え、二人きりのときは男言葉を使うよう厳しくしつけた。要不在のときは、俺はいつもユニセックスな服装をしていた。ナミさん以外の使用人の前では完璧に女性として振舞っていたから、屋敷の人間のうちいったい何人が俺の性別に気づいているかは知らない。 とにかく、俺はナミさんのおかげで二重の生活を送るようになったのだった。彼女のしていることに要が気づかないはずはなかったが、自分の前で妹であればいいのか、それとも彼女が苦手なのか、不思議と何も言われなかった。 ナミさんが何を思ってそんなことをしてくれるのかはわからない。聞いたこともない。好意はあるのだろうとは思うが、時折ひどくさげすんだ口調で俺を叱った。 「まるで女みたいな」 そう言って俺を軽蔑した。 「女の格好をさせられているのは兄さんのせいだし、体が小さいのはしょうがないじゃないか」 声変わりを迎えても、俺の声はわずかに低くなっただけだった。すぐに破綻すると思われた要の計画は、俺の成長に裏切られることなく、もう五年も続いているのだった。 「姿かっこうのことじゃありませんよ。こんな家に閉じこめられて、一生変態性欲の相手をしているつもりですか」 「だってどうするの? ここを出たら俺、どこにも行くところがない」 ナミさんは馬鹿にしたように鼻を鳴らした。 「十七歳の男なら、どこでどうやったって暮らしていけます」 俺は力なく頭を振った。 ナミさんが「女の腐ったようなの」というのは、俺の顔かたちではなく、この性根のことなのだった。 どんなに彼女にかばわれても、要との生活は俺の精神を確実に蝕んでいた。 藤城要は俺にとって絶対だった。 体をまさぐられながら内心どんなに罵ろうと、変態と陰口を叩こうと、彼が俺の支配者で俺が彼の所有物であることは動かしようがないのだ。 この生活を嫌だと思い、自由を願うことがあっても、その思いつきは、要の顔を思い浮かべるだけであっけなく霧散するのだった。 窓の外で車の音がする。兄が帰って来たのだろう。 ナミさんはドレスを手に急いで部屋を出て行き、俺はベッドの上で主の訪れを待った。 |
| 1 / 2 / 3 / NOVEL / HOME |