| 1 / 2 / 3 / NOVEL / HOME |
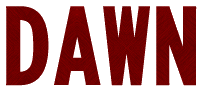 -2- 四日後のことだった。俺が部屋で本を読んでいると、数台の車の音がし、続いて階下が騒がしくなった。 要がこちらに来るときはたいがい事前に連絡が入る。なんだろう、と思って本を傍らに置き、立ちあがりかけると、ドアが開いてナミさんが転がりこんできた。 「お嬢さん、逃げてください、早く!」 だがすぐに荒っぽい足音がして数人の男たちが姿を現した。先頭に立っているのは、パーティで会ったあの男だった。 「よう、郁。迎えに来るって言ったろう」 男は親しい友人にでも会ったかのように、軽く片手を上げて挨拶をよこした。 「加西……」 男が俺の本名を呼んだことと、面識があったことは、明らかにナミさんを驚かせたようだった。それでも俺のそばに来ようとするのを、加西の脇にいた別の男が無造作に振り払った。たいして力をこめた様子でもなかったのに、ナミさんの小柄な体は絨毯の上に転がった。 「ナミさんに乱暴するなよ!」 要のちゃちな苛め以外、暴力というものに接したことのなかった俺はひどく怖かったが、それでも彼女をかばうように前に出た。 「そんなことしないさ。おまえがおとなしくついて来るならな」 男たちは土足だった。加西はきれいに磨かれた革靴を行儀悪くベッドの端にかけると、興味深げに広い室内を見まわした。 「行くって……どこへ?」 「どこだっていいだろう。こんな屋敷にこもっていたら気も滅入るぜ。外へ出たくはないのかい」 「外……」 俺の心がわずかに動かされたのに気づいたのだろうか、ナミさんが「お嬢さん!」ときびしい声を出した。郁の名前で呼ばないのは男たちの前だからだろう。 ナミさんは、俺が男であることが加西にばれているとは知らないのだ。 「心配すんな。〝お嬢サン〟を傷つけたりはしないよ」 加西は今日もスーツ姿だった。ベッドから足を下ろし、俺のそばへ寄ると、化粧室でしたようにあごに手をかけて上を向かせた。 「へえ、化粧してなくてもこんな顔なのか」 俺は男の目を見上げた。瞳孔は小さかったが真っ黒で、そこに女みたいな俺の顔が映っていた。 「行くよ」 「お嬢さん!」 「だって行かなきゃこの場は済まないんでしょう」 俺がそう言うと、加西は「いい子だ」と言ってにやりと笑った。そして俺の肩に手を回すと、あごをしゃくって残りの男たちを促した。 他の使用人たちはどこへ行ったのか、屋敷内は妙に静かだった。 昼間に外へ出ることは滅多になかったので景色が見たかったのだが、車の窓にはカーテンが引かれていた。運転席との間に仕切りはなかったが、座席が深いせいでフロントガラスを覗くには上半身を乗り出さなくてはならず、身じろぎするのはためらわれた。 自動車の種類など知らないが、車内は藤城家のものに負けないほど広く、後部座席で俺と並んだ加西は長い脚を投げ出していた。 運転しているのはサングラスをした男だった。たしか、ナミさんに手をかけたやつだ。彼もスーツを着ていたが、中の派手なシャツはだらしないほど襟元が緩められ、妙に安っぽく見えた。そして男は加西に卑屈なくらいの敬語を使っていた。 俺はふと、こいつらはドラマや小説の中に出てくるヤクザなのではないかと気づいた。加西の危なそうな目の光も、男たちの乱暴なふるまいも、それで説明がつくような気がする。 だからと言って特に怖くなったということはなかった。ヤクザと言ってもイメージばかりでピンと来ないし、まだ自分が殴られたりしたわけでもない。第一こうして昼日中に知らない人間の車に乗せられていることが、俺にとっては何より非現実的なことだった。その相手がヤクザだろうが異星人だろうが、あまり違いはないことのように思えた。 「今日はそういうふうなんだな」 加西の声にそちらを向く。なんのことかと首をひねり、相手の視線に服装のことを言っているのだと気づく。 「兄さんがいなかったから」 「藤城がいないとズボンはいてるのか」 うん、とうなずいてから、「兄さんはこのこと、知ってるの?」と訊ねてみた。 「まさか。今ごろ連絡がいって大騒ぎだろうよ」 加西はさもおかしそうに顔をゆがめた。 予想していた答えだったが、俺は目をそらしてカーテンのかかった窓をじっと見つめた。 「どうした。あとでお仕置されるのが怖いのか」 からかうような口ぶりだったが、その通りだったので、俺は何も言わなかった。 物珍しさは消え、代わりにだんだん息苦しくなってくる。 加西がチッと舌を鳴らす音が聞こえた。 一時間ばかり車に揺られ、着いたところは大きな屋敷だった。とは言え洋風の藤城邸とは違って純粋な和風建築で、俺はきょろきょろと辺りを見まわした。 「ここ、どこ?」 「俺の家だ」 車が止まるとすぐに屋敷内からわらわらと人が現れ、ドアを開けてくれた。 加西はその一人をつかまえて「用意はできているか」と訊ねた。 「はい、離れのほうに。ですが――」 男が耳打ちすると、加西は 「ああ、何言ってんだ、馬鹿やろうが。話つけとけって言ったよな」 と大声を出した。年上のようにも見える男の肩を、どん、と突く。不機嫌そうに口の端をゆがめ、ばりばりと頭を掻いた。 「ちっ、しょうがねぇな。ケータ! ケータ!」 その声に、男たちの後ろから一人の少年が姿を現した。背は俺よりわずかに高いほどで、年齢は同じくらいに見えた。スーツ姿ばかりの男たちの中で、原色のカジュアルな服装をした彼はひどく場違いに見えた。 「兄貴」 彼は加西をそう呼んだ。 「ケータ、こいつを離れに連れてけ。俺は出かけるが、八時には戻る。メシ食わせて風呂にいれとけ」 「了解」 ケータと言われた少年は俺の腕を掴むと、屋敷の右手に向かった。俺はおとなしく引いて行かれながら振りかえって加西を見たが、彼はすでに車内に戻っていた。 加西は離れと呼んだが、そこはそれだけで一軒の家のようだった。玄関もちゃんとついていて、部屋はすべて和室だった。母親と暮らした薄汚いアパートとは比べようもなかったけれど、それでも足の裏の畳の感触が懐かしかった。 「ここ、こっちの部屋だ」 そう言って通された奥の部屋は、がらんとして何もなかった。二十畳ほどだろうか。家具がないのでいっそう広々として見えた。 こんな何もないところでいったいどうしろと言うのだろう。俺は困ってケータの顔を見たが、相手も同じように感じているらしく、そわそわとシャツの裾で手をぬぐっていた。 「兄貴は八時に戻るってさ」 さっきそう言っていたので黙って頷く。 「腹は減ったか。もう少ししたら母屋から食事を運んでくるから」 これも聞いていたので頷く。藤城邸ではそろそろ早い夕食の時間のはずだったが、見知らぬ場所に連れてこられて空腹どころではなかった。 「そのへんに座れよ」 座布団いるか、という言葉にかぶりを振って、俺は迷ったあげく、その場に正座した。ケータは少し離れたところにあぐらをかいたが、こちらに露骨な視線をよこしてくる。なに、というように顔を上げると、彼は奇妙な目つきでこちらを見つめていた。 「おまえ、口きけないのかよ?」 首を横に振る。 「じゃあなんで黙ってんの? 兄貴に俺とはしゃべんなって言われた?」 俺は困った顔をした。この少年と話すことができない理由は二つある。一つは、もう長いこと同年代の人間と口をきいたことがなかったのでひどく緊張していたから。もう一つは、彼がどこまで知っているかわからなかったので、男として振舞えばいいのか女として振舞えばいいのかわからなかったからだ。 「なあ……」 ケータは俺に負けないくらいの困った顔で、たずねてきた。 「おまえ、男? 男だよな?」 「そう見える?」 俺が初めて口をきいたことで安心したらしく、ケータもわずかに笑みを見せた。 「うん。細いけど男だろ? それとももしかして女なのか?」 「ううん、男」 そうか。ちゃんと男に見えるんだ。 俺は思わず嬉しくなって笑みを浮かべた。ケータも相合を崩し、そうするとずいぶん人懐こい顔になった。 「はー、よかった。変だと思ったんだよな。兄貴は藤城の妹を連れてくるって言ったのにさ。それに着替えも同じサイズで男もんと女もん、両方用意しとけって言うんだ。双子でも来るのかと思ったよ」 屈託のない言い方だった。俺は黙って微笑んだ。 そうこうしているうちに、母屋の方から男たちが大きな座卓と夕食を運んできた。食事は刺身が中心で、藤城の家に負けないくらい豪華だった。 「俺は母屋の方で食べるけど……良かったらしばらくここにいてやろうか」 「うん」 俺はまだ警戒を解いていなかったし、ケータも何か言い含められているのか、会話はあたり障りのないものになった。しばらくしゃべっていて二人は同じバラエティ番組が好きだということに気づき、タレントの話などで盛りあがった。 久しく忘れていた楽しい食卓だった。ナミさんとドラマの感想などを言い合うことはあったが、しょせん年代の違いか見ている番組も違う。どの女の子がかわいいの、どの芸人がおかしいのという他愛もない話は本当に久しぶりだった。 自分ではわからないのだが俺が時々おかしなことを言うらしく、ケータが妙な顔をする時はあったものの、俺は浮かれるあまり、要のこともすっかり頭から消えていた。 そんなときに加西が帰宅した。 「なんだ、まだ風呂入ってなかったのか」 スーツの上着を脱ぎながら、加西は呆れたようにこちらを見下ろしてきた。 「あ、兄貴、お帰りなさい」 ケータがあわてて立ってそれを受け取る。 「早かったっすね、すいません……」 謝るケータへ、加西はいい、いい、とうざったそうに片手を振った。 「連中に言って机片づけて布団敷かせろ。そしたらおまえはもう帰れ。こっからはお楽しみの時間だからよ」 加西の言葉に、ケータが驚いたように俺を振りかえった。俺はわけがわからず、眉をひそめる。 「おまえは早く風呂に入れ。ケータ、着替え出してやれ」 楽しい時間は終わりを告げた。ケータの表情から、俺はこれから何かが始まるのだと知った。 離れの風呂を出ると、脱衣所に浴衣が出されていた。下着はなかった。帯の締め方などわからないので、適当に前を合わせて結んで出た。 加西はさきほどと同じスーツの下とシャツ姿だったが、室内はきれいに片づけられ、畳の上には盆が置かれて、彼は手酌でビールを飲んでいた。 「あったまったか? きれいになったか?」 俺が頷くと、加西はちょいちょい、と手招きした。おとなしく近づくと、いきなりぐい、と手を引かれた。 「じゃあ、やるか」 「なにっ、なに?」 胸の中に抱き込まれると、強い煙草の匂いがした。俺は驚いて反射的に手をつっぱねた。 「離せよ。何するんだよ」 だが加西は俺の抵抗などなんなく封じると、顔を寄せて例のいやな笑いを見せた。 「何ってことはないだろ。かまととぶんなよ。いつも兄貴の相手をしてんだろうが」 あ、と思った俺は思わず口に出していた。 「もしかしてあんたも変態なのか」 とたんに、ばん、と顔をはたかれた。大して痛くはなかったが、俺は驚いて加西の顔を見た。 「口のきき方に気をつけろよ」 すごんだ声を出した加西だが、俺の表情に気づくとわずかに掴んでいた手をゆるめた。 「おまえの兄貴は変態なのか?」 「うん」 「なんで」 「俺に女のかっこさせて……セックスするから」 「なんでおまえとセックスすると変態なんだ?」 「それは……俺が男だからだよ。男が男とセックスしたがるのは変態なんでしょう? ナミさんがそう言ってた」 「ナミさんておまえの部屋にいた、あの婆さんか」 俺はうん、と頷いて、ちょっと迷ってから付け加えた。 「ナミさんは俺が女のかっこするの嫌がるんだ」 加西はふうん、と呟くと、こきこきと首を左右に倒して音を鳴らした。そして俺の手を掴んだまま、立ち上がると、隣室に続くふすまを開けた。 「ま、そういう意味では俺も変態かもな。まあいいや、ここにはあの婆さんもいないし、気がねなくやろうぜ」 こちらは十畳ほどの部屋に、布団が敷いてあった。並んで二組。 俺は自分がされることを知った。そしてすぐに体の力を抜いた。 これは俺の義務なのだ。 要が家と食事を与えてくれるように、加西は何か思惑があるらしいにしろ、俺をあの家から連れ出してくれた。俺はその代価を払わなくてはならない。 掛け布団の上に突き飛ばされて顔を上げた俺の目の前で、加西はファスナーを下ろした。 「さて、まずはいい気持ちにさせてもらおうかな。藤城仕込みのテクニックを見せてもらうぜ」 俺はぽかんと、剥き出しにされたそのものを見上げた。 そんな至近距離で他人の性器を見たのは初めてだったからだ。それはまだ勃起していなかったが、太くだらりと垂れ下がり、その色も形も、根元に絡みついた太い毛も、全く自分のものと違っていた。 「ほら、舐めろよ」 目が離せないでいる俺の頭を、加西はぐいと掴んで自分の腰に近づけた。 口での奉仕を求められていることに気づく。その行為は知らなくはなかった。ナミさんは俺のためにとポルノ雑誌まで買ってきてくれたことさえあったのだ。テレビでは見られないような女の股間や絡みの構図は確かに興味深かったが、残念ながらそれで催すということはなかった。俺は自慰の習慣もあまりなかったのだ。 手を伸ばし、彼の性器を握った。手のひらの中で、それはどくんと波打った。舌を出しておそるおそる先端に近づける。 怖くも気持ち悪くもなかった。ただ、どうしていいかわからない戸惑いだけがあった。写真で見た女の様子を懸命に思い出しながら、舐めろと言われたのだから、とまずは側面にちろりと舌を這わせた。 伺うように上目遣いで加西の顔を見ると、眉間にはくっきりと皺が寄っていた。慌ててもう少し熱をこめてあちこちを唇で探った。 だが、あいかわらず加西の性器は下を向いたままで、そのうちじれったくなったのか、「もういい」という苛立たしげな声がした。 「あ……」 舌を伸ばしたまま、顔が引き離される。 「おまえ、もしかしてしたことないのか」 嘘をついてもしかたないのでこくりと頷く。俺は要の性器をしゃぶったことはなかったし、触れたことさえ滅多になかった。 「しょーがねぇなぁ。ま、そのうちおいおい覚えさすか」 彼の言葉に、俺はどきりとした。そのうち、ということは俺はしばらく藤城の家には戻らないらしい。もしかしたらこのままずっと帰れないのかもしれない。喜ぶべきか悲しむべきか、よくわからなかった。 加西は俺を仰向きに突き倒すと、そのままのしかかってきた。浴衣の襟元を乱暴に引き剥ぎ、首筋に唇を這わせる。 俺は目を閉じた。体を好きにされることには慣れていた。 ただひどく乱暴にされると思っていたのに、その予想はかなり裏切られた。 加西の手は、見かけの無骨さとは裏腹に手際良く俺の体を高めていった。初めは殴られるのではないか、痛い目に会わされるのではないかとびくびくしていた俺も、あっという間に快感の波に攫われてしまった。 大きな手のひらで性器を握り締められ、優しく上下に扱かれると、堪えきれない声が漏れてしまう。頭の中がかーっと熱くなって、すぐに何も考えられなくなった。 「ん……ん!」 背筋をのけぞらせ、つい腰を突き出すような格好になってしまう。俺は握ったこぶしの中で親指の爪をたて、なんとか堪えていたが、かすむ目で見上げた加西の顔のどこにも非難の表情が浮かんでないのに気づき、ほっと体の力を抜いた。 勝手にいっても怒られない。我慢しなくていいんだ。 安堵のせいで目尻に涙が浮かんだ。 ただ射精するとき、いつものくせで「要、ごめんなさい、お兄さま、ごめんなさい」と連呼してしまい、「気色悪いことを言うな」と頭をはたかれた。 さすがに要の名を呼んだのはまずかった、と荒い息を整えていた俺は、突然濡れた指で下肢の奥をまさぐられて、ぎょっとした。 「なっなにっ?」 布団の上に跳ね起きて、脚の間に差しこまれた男の腕を引き剥がそうとする。見ると浴衣などほとんど脱げかけて、帯だけが腹の上に残っているという情けない格好になっていた。 「何って、一回いかせてやったろ。今度はこっちの番だろうが」 「う、うん」 つまり加西も射精したいってことだ。言っている意味はわかるので、ためらいつつ頷く。 「わかったけど、変なとこ触らないでよ」 俺は力をこめて加西の腕を押しやった。 「郁、おまえ――」 シャツの前をはだけ、ファスナーを下ろした格好で、加西は俺と向かい合うように座りなおした。 「おまえ、藤城と寝てたんだよな。セックスしてたってさっき言ってたもんな」 「……うん」 「どんなことをしてたのか、教えろ」 「どんなことって、そんなの……」 「いいから言え」 俺はためらった。要とのことは絶対人に言ってはいけないとナミさんに言い聞かせられていたし、そのナミさんにも具体的にどんなことをさせられているかを打ち明けたことはなかった。ただ異様な行為だという認識ばかりが強かった。 だが加西は譲らず、彼がその気になれば俺の口を割らせることなどたやすい。 俺は五年間、ベッドの上で要にどんな目に会わされてきたかを逐一白状させられた。 「おまえ……それは、セックスじゃねえよ」 俺の話を聞いたあとで、加西は呆れたような口調で言った。 「セックスじゃ……ないの?」 「いやまあ、色んなやり方があるからなぁ。セックスっちゃあセックスかもしれないが、うーん。とにかく変わった野郎だよ、藤城ってのは。ある意味変態ってのは的を射てるかもしれないな」 「だからそう言ったじゃん……」 俺はうつむいて、裸足のつま先を片手でいじった。加西は呆れたのか失望したのか。何より要との行為の異常性に念を押されたようで、いたたまれない気持ちだった。 だが白々とした空気が流れたのはほんの短い間のことだった。 加西はふいににやり、と笑うと、再び俺の体を引き寄せた。 「それじゃおまえはバージン、てわけだ。五年もあんな格好させられててなぁ」 急に変わった加西の表情は上機嫌のようにも見えた。俺はわけがわからないまま体をまさぐられた。 「あっ。ちょっと、やだ……」 「ここになぁ、挿れんだよ」 「いれる……」 「俺のこれをさ」 加西はそう言って、兆し始めていた自分の性器をぎゅっと俺に握らせた。 「これを入れるの? 女みたいに?」 驚いて加西の顔を見た。冗談を言っているのかと思ったからだ。 「女だって後ろに挿れることはあるんだぜ」 「む、無理だよ。気持ち悪いし。入らないよ」 「入るって。心配すんな。俺は慣れてる。おまえの兄貴と違ってベッドの相手に痛い思いをさせるのは趣味じゃないしな」 俺はまだ半分信じられない気持ちで、抵抗らしい抵抗ができなかった。 そのあと、朝までかかって、加西は自分の言葉を証明したのだった。 「何読んでるの?」 次の日俺は腰がだるくて起きられず、部屋でごろごろしていた。テレビもない部屋だったが、何もしないでいることには慣れている。昨晩のことなどを考えながら、床柱に寄りかかってぼんやりしていたのだった。 目が覚めるとすでに日は高く、加西の姿はなかった。体はきれいにされていたが、一応自分でもシャワーを浴びて出ると、朝食とケータが待っていた。 たぶん俺の世話係兼、監視役というところなんだろう。 今朝のケータは昨夜ほどおしゃべりではなかった。俺も起きぬけだし疲れていたから、半分夢心地のまま食事を済ませたのだった。 朝食のあとしばらく手持ち無沙汰な様子だったケータだったが、やがて思いついたように母屋へ戻ると分厚い本らしきものを持ってきて、あぐらを書いて読み始めた。 「ねえ、何の本? マンガ?」 熱中していたらしいケータは、少し声を高めてきくと、はっとしたように丸めていた背筋を伸ばした。 「マンガじゃねぇよ。勉強してんの」 そう言って、ほら、と見せてくれた参考書のタイトルは『よくわかる数学・中2』と書かれていた。 「……ケータ、年いくつ?」 「十八」 「一個上なんだ。どうして中学の勉強なんかしてるの?」 ケータはしばらくためらっていたが、「俺、大学行きたいんだ」と呟いた。 「でも高校の教科書なんか見ても全然わかんないからさ。高一で中退してっから……」 「すごい、ケータ、高校行ったんだ」 俺はうらやましそうに言った。 「おまえ、行ってねえの?」 「うん、中学も行ってない」 「中学も!?」 ケータはびっくりしたように俺の顔を見た。 「中学って義務教育じゃなかったっけか」 「さあ、わかんないけど……兄さんが行かせてくれなかったから」 「おまえ……」 あ、でもね、と俺はつけくわえた。 「家庭教師がついてるから、勉強はしてるよ。わかんないとこあったら教えてあげる」 俺がそう言うと、ケータは、ホントか、とうれしそうな顔になってさっそく問題をきいてきた。 俺たちは座卓を出してもらって、その上にノートなんかを並べると、参考書を間において二人で勉強を始めた。 正直言ってケータは中1の分野も怪しい感じだったが、それでもつまづいていたところが理解できると無邪気に喜ぶので、俺も楽しくなった。 「おまえ、すげえな。頭いいのな」 そんな風に誉められたのも初めてだった。勉強は嫌いではないけれど、それは単に他にあまりすることがなかったからだけなのだ。 「ねえ」 小一時間ほどまじめに勉強してから、ケータが持ってきたジュースを飲んでいた俺は、ふと思いついてたずねた。 「加西ってやくざなの?」 ケータは咥えていたストローを口から離した。 「そうだよ、知らなかったのか」 「彼がボス……じゃなくて何だっけ、その、組長?」 加西の年齢はよくわからないが、兄よりいくらか年上なくらいだろう。ドラマなどで見るやくざの親分はどれももっと年配だった。 「違うよ。兄貴の親父さんが組長。それよか、兄貴のことそんなふうに呼ぶのよせよ」 「なんで? 皆そう呼ばないの?」 「組の人たちは補佐とか、場合によっては名前で呼んでる。矩人(のりと)さんとか」 でも加西と名乗ったのは本人なんだけどな。俺はそう思ったけど口には出さなかった。 「ケータは兄貴って呼んでるけど、本当の兄弟じゃないんでしょ」 「まさか、違うよ。俺は弟分なんだ。ちゃんと兄弟盃も交わしたんだぜ」 ケータの顔は誇らしげだった。ずー、とジュースの残りを吸い上げる。 「ケータもやくざ?」 「ああ、そうさ。でもまだちゃんとしたシノギとかねぇから、準構成員扱いだけどな。俺、体はちっちぇえけど、喧嘩とか強ぇんだ。郁は喧嘩なんかしたことないだろ」 「喧嘩ぐらいあるよ」 シノギって何だろう、と思いながら、俺は答えた。 「へえ、人殴ったことあんのか?」 「うん」 小学生のときだけどね、とこれは心の中で付け加えておく。 「へえ、結構やるじゃん」 ケータはあまり興味なさそうに言って、でもなぁ、とため息をついた。 「将来兄貴の片腕になりたかったら大学くらい行っとかなきゃ駄目だっていうんだ。組は若頭――ってこれは兄貴の本当の兄さんだけど――が継ぐからさ、兄貴はいずれ表の会社とかビジネスの方を担当するとかって」 「ああ、それで勉強してるんだ」 「うんそう」 でも、先は長いよなぁ、とケータはため息をついた。 それでもいいじゃないか。 どんなに遠くたって、ケータには将来がある。自分が望む未来の形がある。 俺にはない。 「んっ、んっ……!」 四つんばいになって背後から貫かれながら、俺は敷布を握り締めて喘いでいた。 ぎゅうっ、と跡がつくくらい、尻を強く掴まれ、腰を揺さぶられる。 「あ、ああ!」 加西はまったく玩具でも扱うように、たやすく俺の体を翻弄した。俺は一晩に何度も何度も吐精させられ、息も絶え絶えになって懇願させられた。 それでも、やがては彼も逐情するときが来る。 たがが外れたように動作が激しくなると、その瞬間が近づいてくるのがわかる。 加西は長い腕を伸ばすと、乱暴に俺の頭と肩を布団に押し付けた。俺の腕力では抵抗しようもなく、肘を折って顔からシーツに突っ込んでしまう。下半身だけを高く上げた格好で、がたがたに体を揺さぶられた。 泣いているみたいな悲鳴は自分のものらしい。それすらもわからないほど頭の中は真っ白だ。感じているのはただ、かつてないほど近くで聞く、他人のあからさまな生の呼吸。肉の熱さ。その重み。 痛いのか気持ちいいのかもわからなくなる――。 ふいに獣のような唸り声があがり、背中に頭が押しつけられると、体内に熱い飛沫を感じた。 体の奥で他人の体液が広がるなんとも言えない感覚。 吐き出された精液をそんなところで受けとめるなど、かつては想像したこともなかった……。 「はあっ、はあっ、はあっ」 突っ伏した俺の上に、大きな男の体がどさりと圧しかかってくる。だが、俺が完全につぶれてしまう前に、加西は性器を抜いて、俺を抱えたまま、ごろりと仰向けに転がった。 「あ……」 締めていないとすぐに漏れ出してしまう。俺は顔をしかめたが、体に力は入らなかった。 「だいぶ慣れたな」 「……」 「どうだ、気持ち良かったか?」 目の奥がちかちかする。俺は答えることもできず、しばらく黙って息を整えていた。 最初に加西に体を拓かれてから七日目になる。その間、俺は自分が楽しむことも、また相手を悦ばすことも教わった。 これをセックスというのなら、要との行為は確かにそうは呼べないだろう。 俺は加西の胸の上で背後から抱かれたような形で横向きに体を伸ばした。 すぐ目の前に鮮やかな色がある。 肉の盛りあがった肩をそっと辿ると、加西が笑う気配がした。 「おまえ、好きだな、それが」 「見せて。うつ伏せになって」 俺がそう言うと、加西は黙って布団の上で体を返した。 |
| 1 / 2 / 3 / NOVEL / HOME |