| 1 / NOVEL2 / HOME |
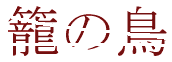 「うわ……っ!」 ドアを開けたところに立っていた小柄な女性が誰だかわかり、悲鳴ともつかない声をあげる。そんな俺を押しのけるようにして、黒スーツの男たちが三人、どやどやと室内に押し入ってきた。 「ちょ、ちょっと!」 「ケータ? どうしたの?」 玄関の騒ぎに、奥から郁が出てきた。 「い、郁……」 あわてて走り寄ろうとした俺を、男の一人が背後からぐっと押さえこんだ。その脇を、すっと通りぬける影。 「ふうん、この子なの」 きれいに手入れされた細い指先が、顎先をくっと持ち上げる。 「ケ、ケータ?」 見知らぬ女性に顔をつかまれてさぞ驚いたろうが、それでもこの雰囲気に何かを感じたのか、幸いその手を振り払ったりはせずに、郁はただ困惑した顔で俺の方を見た。 「噂には聞いてたけど、ずいぶん可愛らしい子ね」 女はそう言って、満足そうに目を細めた。 「気に入ったわ」 「ね、姐さん」 俺は蒼白だった。 どうすれば、という思いで頭がいっぱいになる。郁のことは、兄貴に任された責任がある。だが、朝早くマンションを訪れてきたこの女性にも逆らうわけにはいかなかった。 加西理沙――加西組若頭、加西将人の正妻である。つまり矩人(のりと)の兄貴にとっては、義理の姉にあたる人だ。だが、厄介なことに、組にとってはそれだけの人間ではないのだ。 理沙というのは日本名で、日本語もペラペラ、すでに帰化もしているが、もとは大陸の出身らしい。幼いときに姉と二人で台湾へ流れ、そこから身一つで逞しく生き延びた。妹はさらに日本へ来て、ホステスをしているときに若頭と知り合ったのだが(もちろん当時はまだ若頭ではなかった)、姉の方は台湾の財閥の御曹司をものにした。 彼女の夫は、台湾黒社会とも深いつながりがある。つまり加西には、財政面のバックアップだけでなく、そちらにも強力なコネができたわけで、深川系のちっぽけな末端組織に過ぎなかった加西組が、ここ十年でぐんぐん頭角を現しているのは、ほとんどそのおかげと言ってもよかった。 要するに、加西組はこの理沙姐さんに頭が上がらないのだ。 賢い女で、決してでしゃばって表に出てくることはないが、自分の価値もよく知っていて、周囲を振りまわすことも多い――これは兄貴から聞いた話だ。 最近ではあまり組事務所や屋敷の方には出入りすることはなくなった俺だが、兄貴に可愛がられているせいか、姐さんと顔を合わせたことも数度ある。 ぱっと見には、かなり小柄だし、顔立ちも派手ではないので、それほどのいい女とは思えないのだが、わずかに眦の吊り上った目には独特の色気があって、その目でじーっと見つめられると、どこか落ちつかないものを感じてしまう。 男を不安にさせる、加西理沙はそういう女だった。 そして、どこからこのマンションの場所を聞いてきたのかは知らないが、兄貴が後生大事に飼っている郁に好奇心を覚え、ちょっかいを出そうとしてやってきたに違いなかった。 「ね、姐さん……」 俺は後ろから肩を掴まれたまま、声をしぼり出した。 「そいつは、勘弁してやってください、たのんます」 姐さんは、振りかえって、わずかに俺を睨みつけた。オフホワイトのパンツスーツに、引き締まった体を包んでいる。一方、蜘蛛の巣にかかった態の郁は、グリーン系のセーターに、焦茶のコール天の細身のズボンを身につけている。どれも兄貴が買い与えているものだが、無造作に見えてどこかのブランドもので、普段着だというのに、びっくりするほど値の張るものだった。 兄貴は郁に身内の話をほとんどしないようだが、俺が姐さんと呼んだことで組関係の人間だということはわかったのだろう。身動きもせず、その場でじっと成り行きをうかがっていた。 「姐さん、俺が兄貴に叱られます、どうか勘弁してください」 「矩人さんにはわたしがあとで言っておくわ、ウサギちゃんをちょっとお借りしました、ってね」 そんなこと言われても全くあてにならない。それに、あとでは困るのだ。 「姐さん、後生です……」 さらに言い募ろうとしたおれに、姐さんは初めて苛立ちをあらわにした。 「その子うるさいわ。外に出しちゃって」 「ケータ!」 数人に押さえこまれた俺に、郁が初めて近寄ろうとする。が、 「あなたは、こちら」 姐さんがやんわりとその体を押さえた。そして俺に向かって言った。 「この子は、矩人さんのオンナでしょ。オンナ同士でちょっと親睦を深めるだけよ」 「ケータ……!」 不安そうな郁を見て、俺は唇を噛んだ。八方塞がりだった。姐さんを相手に騒ぎを起こすのは得策ではないし、大体この人数に俺ひとりで何ができるというのだ。唯一救いの種なのは、この調子なら郁はそんなにひどい目には合わないだろうということだった。 「郁、ごめん……。おとなしくしていてくれ」 俺の表情に何かを感じたのだろう。郁はちょっとためらったあげく、小さく頷いた。 そのまま姐さんにうながされ、小さな背中は奥の部屋に消えた。 俺はようやく押さえられていた体をよじって自由になると、そのまま靴を履いて、部屋を出ようとした。 とにかく早く兄貴に連絡しなくては。すぐにかけつけてもらえば何とかなるかもしれない。 だがポケットの携帯電話に伸ばそうとした手首を、再びごつい手に握られた。 「おっと、おまえはしばらくドライブだ」 「くそっ、放せよ、てめえらっ」 スーツの男たちは――見覚えのない顔ばかりなのは、姐さん専用の手駒なのだろう――一人を残し、残りは俺を引きずってエレベーターへと向かった。 「二時間てとこかね、ご休憩」 「まったく、あの女も好きだね」 密室の中で、一人がそんな軽口を叩いた。 「けどよ、普段男に突っ込まれてヒーヒー言ってるようなのが、女相手に勃つのかね」 男たちは、聞こえよがしに言って笑っていた。俺がチビでガキだからって、明らかになめている。 くそっ。 だけど、俺は我慢した。何より郁のことが心配で、俯いて、こぶしを握っていた。 俺を乗せたでかい車は近所をぐるぐると適当にまわっていたが、男の一人の携帯電話に連絡が入ると、マンションにもどった。 そこで俺はぽいと路上に放り出され、代わりに姐さんをうやうやしく迎え入れると、車はさっさと走り去った。 俺は見送りもせず、マンションの階段を駆け上がると、郁の部屋に飛び込んだ。 「郁、郁!」 リビングには誰もいなかった。 「郁!?」 俺が意を決して寝室に向かおうとすると、 「ケータ……」 がちゃっとノブが回る音がして、ローブ姿の郁が、バスルームから現れた。髪が濡れている。 「郁……」 シャワーを浴びていたらしいその姿に、俺が思わず情けない顔をすると、郁も苦笑いのようなものを顔に浮かべた。 「やっぱ、食われちまったか……」 俺の言葉に、郁は、うん、と小さく頷いた。 「でも、別に、平気だったよ。特に何しろとも言われなかったし、痛い目にもあわなかったし。それに、きれいな人だよね、あの人」 そういうもんじゃないだろ、と、俺がため息をつくと、郁はさらに、 「ただ、マキさんとは随分違ったけど……」 と、のん気なことを言った。 「そりゃ、そうだろ、だってあれは兄貴の――」 そう言いかけて、俺は「ああ!」と頭を抱え込んだ。郁の安全を確認してほっとしたのもつかの間、次の問題が待っている。 「ど、どうしたの、ケータ。もしかして、殴られたりした?」 「違うよ、ああ、兄貴になんて言えばいいんだ! 殺されるー!」 郁は、そんな大げさな、と笑った。 「ばか! 何が大げさなもんかよ! 兄貴にはお前のことをくれぐれも頼むって言われてんだぞ。それを他の女にやらせたなんて知れたら――!」 「だって、組で力のあるお姐さんなんでしょ、不可抗力じゃないか。ケータのせいじゃないよ」 「そんないいわけきくもんか!」 郁には、俺の不安がいまいち理解できないようだった。 「加西がそんなに怒るかな。マキさんのときだって、加西、何にも言わなかったよ」 それは当たり前だ。マキ姉さんは兄貴の女の一人で、その件は兄貴がお膳立てしたんだ。 ある日、「女の人と寝てみたい」と言ったのは、郁だった。俺がそれを兄貴に伝えると、兄貴はマキ姉さんをよこした。 マキ姉さんは、超売れっ子のホステスで、俺だって相手になんかしてもらえない。あのときは、まじで郁が羨ましかった。 ともかく、兄貴は郁のわがままは――郁がそんなことを言うのは滅多にないけど――たいがい何でも聞いてやっているようだが、それも兄貴の手の中で、という条件がつく。 兄貴は郁を屋敷から出してしまい、このマンションの一室を与えて、俺以外の組の人間にはほとんど会わそうとはしなかった。郁自身がそれを不自由とは思っていないので、監禁とか拘束とかいう言葉はあてはまらないのかもしれないが、俺にはどう見ても「籠の鳥」状態だ。 高価な服や食べ物をあてがわれて、郁はと言えば、のん気にテレビを見たり本を読んだり、もしくは俺と勉強なぞしているのだが、自分がやくざの囲い者であるという自覚は薄い。 姐さんの言葉を借りれば「オンナ同士」ということで、面子の問題はないのかもしれないが、郁が自分の知らないところで勝手に別の人間と寝たと知ったら兄貴がどんなに怒るか、想像するだけで俺は憂鬱になった。 「それなら、内緒にしておけばいいじゃん」 いつまにか二人分のコーヒーを入れた郁が、カップの一つを俺の前に置いて、自分はソファに腰を下ろした。さすがにどこか動作がけだるげだ。 「そういうわけにいくか!」 「そうなの?」 このときばかりは、郁が本気で憎くなった。 いつのまにか彼の世話係のようになって、組の仕事にはあまり関わらせてもらえなくなったことを、おもしろくないと思うこともある。でも、郁のやつが心配だったし、ほっとけなかったし、何より郁が好きだったから、これでもいいか、とも思っていた。 郁は世間知らずで変なところはあるが、いいやつだ。やくざで喧嘩っ早い俺を色眼鏡で見ないし、勉強も教えてくれるし、こっちを頼りにして色々訊いてくるところなんかは、弟みたいでかわいい。俺は兄貴と違って、郁に突っ込みたいなんて思うことはないが、それでも人形みたいな郁の容姿は鑑賞用としても悪くない。 でも、こうして時々、人の気持ちなんててんでわかっちゃいない郁の鈍感さが、憎たらしくなることもあるのだ。 そして案の定、兄貴にはすぐばれた。 どうも、理沙姐さんの方がわざわざ何か言ったらしい。 あとで断っておく、というのは冗談だと思っていたのに、まったく余計なことをしてくれたものだ。 俺は兄貴に呼び出され、言い訳もさせてもらえず、顔を数発殴られた。 前歯の一本が折れ、血を流している俺を、兄貴は何を思ったか、郁のマンションに連れていった。 着いたときには珍しく郁の姿は見当たらず、俺を部屋の一室に放りこむと、兄貴は 「いいと言うまでそこにいろ」 と言って、どこかへ出かけていった。 俺は高価なカーペットを鼻血で汚しながら、しばらくうんうん一人でうめいていたが、そのうち疲れ果てて眠ってしまった。 夜中に泣き声のようなもので目が覚めた。それがあのときの声だとすぐにわからなかったのは、昼間に殴られたせいで、頭がぼーっとしていたからかもしれない。 すすり泣くような、小さな悲鳴のような声に引かれるまま、俺は無意識のうちに、居間に続くドアを小さく開けていた。 郁がいた。 素っ裸で、手足を椅子に縛られていた。 顔の上半分を、黒いスカーフのようなもので覆われていて、小作りな鼻と、半開きの赤い唇だけが見えていた。たったそれだけでも郁は美形なんだな、と俺はのん気なことを思った。 未だそこで何が起こっているのか、ぴんときていなかったのだ。 びくびくと仰け反って悲鳴をあげている郁のそばに、スーツの上着を脱いだだけの兄貴がひざまずいていた。 兄貴は郁の肩に顔を寄せるようにし、左手でその体を撫でさすりながら、右手を郁の中心に伸ばしていた。 その手が動いて、郁はまた、 「ひいっ」 と悲鳴をあげて、がたがたと椅子を揺らした。 そこでようやく、俺は郁が何をされているのか気づいた。ノブを掴んだままの手にぎゅっと力を入れる。拍子で大きく開いてしまいそうになったドアを慌てて引き戻した。その間も、俺は居間のシーンから目が離せなかった。 天井にはこうこうと蛍光灯が輝いていた。その下に、四肢の自由を奪われた、郁の真っ白い体があった。 彼はお気に入りのアンティークな布張りチェアの、肘かけに手を、椅子の脚に膝の下と足首の二箇所を、やはり黒いシルクのようなもので縛られていた。 「ああ、うっ、ひっ、ひいっ!」 郁は椅子ごと体を揺らし、何度も何度も頭を仰け反らしていた。彼の体はこちらを向いて開かれていたので、俺にはその中心がよく見えた。 兄貴は左手で飛びあがりそうになる華奢な体を押さえながら、右手でその股間に何かを突っ込んでいた。 おもちゃ。俺も女に使ったことがある。 兄貴は俺ほど乱暴ではなく、だが容赦ないやり方で、それを郁の後ろに出し入れしていた。 俺は兄貴と郁がセックスしているのは知っていたが、実際に現場を見るのは初めてで、瞬きもできないほどショックを受けていた。 「ううっ、…めんなさ…! かさい、あうっ」 郁の、半分が黒い布で覆われているために、白さがいっそう目立つ顔は、涙と涎でびしょびしょになっていた。 「やめ……ひぃっ!」 兄貴が抉るように右手を動かしたので、郁はいっそう悲愴な声をあげた。 「どうした。おまえの好きなやつだぜ」 そこで初めて兄貴の声がした。 俺の位置からだと、兄貴の顔はほとんど見えなかった。だがその声色から、何となくその表情の想像がついた。悪魔のような笑いを浮かべて、もだえ苦しむ郁を眺めているに違いない。 「んん? 好きなやつって言っても、どれかわからないか? あててみるか」 「いやっ、いや!」 「イヤじゃねえだろ、悦んでるじゃねぇか」 兄貴の言葉通り、郁の股間のものは、上を向いていた。距離があるのでよくはわからないが、電灯の光が反射して光っているところを見ると、すでに先は濡れているらしかった。 「いや、放して、いやだっ」 「わからないなら、もっと奥までつっこんでやろうか、ん?」 「いやぁ……」 郁があんまり泣きじゃくるので、俺は可哀相なのか興奮しているのかわからなくなってきた。どんどん股間に血は集まってくるし。 あまりひどいことはしないでやってくれ、と思いながらも、もっと泣かせて、苛めてほしいという、複雑な感情が俺を支配していた。これは郁に対する裏切りかもしれない、という思いが頭のどこかでちかっと光ったが、すぐどこかへ消えてしまった。 郁は確かに女みたいにきれいだったが、ただそれだけだと思っていた。一人前の男ではなく、半分オンナ、どっちつかず――やつのことは気に入ってはいても、同時に、男のくせに男に抱かれて、その代わりにその庇護を受けているようなやつだと見下していた。 だけど、俺はようやくここへ来て、郁を妹として飼っていたやつの兄――藤城要(かなめ)――の気持ちも、どんなに忙しくても週に一度は必ずマンションに顔を出す兄貴の気持ちも、ほんの少しだけ理解できるような気がした。 そのように作り変えられてしまったのだとしたらそれはそれで哀れなことだが、郁の体や仕草は、確かに男の劣情を誘うようにできている。 人形みたいだと思っていた肉のない細い体は、真夜中の照明の下で全身に汗をにじませ、AV女優も真っ青という艶めかしさでのたうっていた。 「さあ言えよ」 「あう、う……」 「どれだ? ん? おまえを悦ばせてるのは? いっぱい買ってきてやったろう。並べて、おまえに選ばせてやったこともあったよな」 ――何やってんだ、この二人。 俺は頭がくらくらした。 「あう、あ……ピンクの…」 「ちがう」 「ひいっ!」 郁があんまり仰け反ったので、俺は椅子ごと後ろに倒れるんじゃないかと心配した。 「痛いっ……痛い、加西、抜いて、苦しい…っ」 「よしよし。ちゃんと言えたら抜いてやろう」 「白いの、しろいの…」 「白い、どんなのだ」 「しろいの、しろくて、長いの、ぐねぐねするやつ……」 卑猥なことを口走る郁はだんだん正気を失っていくようだった。白かった顔は紅潮し、激しく頭が振られると、濡れた頬に髪の毛が何本もへばりついた。 びくっ、びくっ、と見ているこちらが心配になるほど何度も体を痙攣させる。見ると、兄貴の右手はそのままで、いつのまにか左手が郁の前を握っていた。 「あう、ああ……」 前と後ろを同時に攻められて、郁は明らかに感じていた。兄貴の手が動くたびに、しばられた手足がスカーフを引きちぎろうかという勢いで上下して、それだけで、郁がどんな気持ちなのかがリアルに伝わってきて、俺の股間はますます切なくなった。 「はあっ、はあっ、んうっ、はあっ」 郁は何度もこらえるように唇を噛み、そのたびすぐに我慢できなくなって喘ぐように大きく息をしていた。 天井の高い、広々としたリビングには、玩具を動かす音と椅子のきしむ音、そして郁の荒い息だけが響いていたが、その間隔がどんどん狭くなってきて、俺は、一つのクライマックスが近づいているのを知った。 郁の、唯一自由になる上半身が、折れてしまうのではないかと思うくらい反り返り、顎が突き上がって白い喉が剥き出しになった。手足の指先の一本一本にまで力が入って、腰が前へと浮き上がる――。 「いや、あ、あ、もう、もう許して、許して、ああ、おにい――」 「加西だ!」 口走る郁ヘ、兄貴が初めて大きな声を出し、手を放して立ちあがった。俺もびくっとしたが、惑乱状態だった郁がハッと顔を起こすのが見えた。 「加西だ。勘違いするな。おまえにこんなことをしてるのは、俺だ、おまえの兄貴じゃねえぞ」 「かさ、かさい…っ、かさい……」 郁は鼻を啜りながら、すがるようにその名を何度も呼んだ。 「そうだ、俺だ、わかるな。他の誰かと寝たかったら言え。許してやる。好きなやつができたら言え。渡りをつけてやる。だが、俺の知らないところではだめだ。いいか。俺の知らないところではだめだ」 「かさ、い…」 「わかったか。反省したなら、許してやる。おまえの望み通りにしてやる」 「は、はんせ……」 郁は、目隠しをされた顔を、必死で上に向けた。 「もうしないか」 「しな、しない……抜いて、加西……」 「よし」 兄貴は無造作に郁の中心から玩具を引き抜き、床の上に投げ捨てた。それは俺の視界から消え、フローリングの上をごろごろと転がる音だけが聞こえた。 「それから?」 「目隠しを取って……」 兄貴が言われた通りにスカーフを取ってやると、真っ赤になった目が現れた。汗と涙でぐちゃぐちゃになった顔は、それでもかわいらしかった。いつものどこかとりすました、表情の乏しい彼とは別人のようで、なるほど、これが郁の夜の顔なのだ。男のくせに同じ男を捕えて離さない、彼の一面なのだ。 郁はその涙で濡れた瞳で、じっと兄貴を見上げた。まだ体は細かく震えていた。 「加西、俺も加西がいい……」 郁は小さな声で言った。 「そうか? こんなひどいことされてもか?」 郁は、こんなの……と言いかけてやめ、 「され…てもだよ」 と俯いて答えた。 兄貴がちょっと笑ったのが、気配でわかった。それから身をかがめて、郁の手足の布を解き、ぐったりと一人では立ち上がれることもできなくなっている郁の体を抱き上げると、散らかった居間はそのままにして、奥の寝室へ消えていった。 俺は左手をノブに、右手を自分の前に伸ばした姿勢のまま、深い深いため息をついた。 そのまままた寝入ってしまったらしい。 俺は頭を蹴飛ばされて目が覚めた。 「おい、起きろ」 兄貴の声に、あわてて飛び起きる。室内はすでに明るく、カーテンの隙間から射す光が、俺の目を突いた。 「起きろ、歯医者に連れてってやる」 そう言われて、口元に手をやる。今まで忘れていたのに、急にまた痛みがぶり返した気がして、俺は顔をしかめた。 兄貴は俺を起こすと、さっさと背を向けた。 そのあとを追って、俺は居間へ出た。 そこはすでに片づけられていた。床に転がっていた玩具も、郁をしばっていた布もなく、お気に入りの椅子は、淫らな遊びに使われたのが嘘のように、テレビのそばのいつもの定位置に戻されていた。もちろん郁の姿もない。 昨日のことは夢だったのかもしれない。郁がここで、足を開いて、泣いて――。欲求不満が見せた幻だったのか? だが夢ではない証拠に、玄関へ続くドアのところで振り向いた兄貴が意地悪そうに言った。 「抜けたか?」 兄貴の視線をたどって視線を下ろすと、開けっぱなしのズボンのファスナーがあった。俺はあわててそれを上げた。 「おまえは女専門だと思ってたがな」 おもしろそうな口調に、わざと見せたくせに、と言いたかったが、俺は黙っていた。 「おまえも郁を抱いてみるか?」 どんな顔で兄貴がそれを言ったのか見ていなかった俺は、何も考えずに答えていた。 「いや、いいっす。俺にはとても」 それが本心だった。それに郁は兄貴がいいと言っていた。郁にとってもたぶんあれが本心で、俺はそれを忘れたくなかった。 俺は手洗いに寄って、ついでに顔を洗い、こべりついた血をざっと洗い流した。顔はずきずきと痛み、鏡を見ると腫れあがってえらいことになっていた。 おそらく郁はまだ寝ているのだろうが、会わなくて済んでほっとした。 「郁のことだが……」 俺が靴を履くのを待っている間に、兄貴が言った。 「来年にはおまえと一緒に大学にやる」 俺は顔を上げた。俺よりずっと大柄な兄貴と二人でいると、広々とした玄関も窮屈に感じた。 「皆が、俺が郁を飼い殺しにしていると思っているようだが、それを望んでいるのは俺じゃない。俺はあいつを鎖につないでいるわけじゃないし、部屋に鍵をかけてるわけでもない。金も渡してるし、自由に出かけようと思えば出かけられるのに、あいつはそうしようとはしない。ここを出たいと、俺から離れたいと、おまえに言ったこともないだろう。わかるか? あいつはそれ以外の生き方を知らないんだ。籠の鳥以外のものになったことがない。 本当にあいつを閉じ込めて出さないようにすれば、あいつは外に出たがるだろう。あの兄貴から解放されたがったようにな。だが、戸が開いていることさえ知らせてやれば――あいつは安心して籠に入っているのさ。それが楽なんだ」 哀れなもんだろ、と言って兄貴は笑った。 けれど、そういう、俺には理解できない郁の一面を、兄貴はちゃんとわかっているようだった。 「まあ俺にはそっちの方が都合がよかったんだが、いつまでも外が怖いじゃ困るしな。別に隠してるつもりはないのに、昨日みたいなことも起こる」 兄貴は思い出したように忌々しげな顔をし、俺はちょっぴり後ずさった。 「しかたねぇ、ちょっと強引に外へ出すか。おまえと俺と兄貴以外にまるで関心がないのも問題だぜ、あれは。だから理沙と寝たって罪悪感がないんだ。どっかの知らないやつにちょこっと体触られたくらいにしか思ってねぇ。けろっとしやがって、腹が立つ」 またカッカし始めた兄貴に、俺は、そんなんじゃ本当に郁が大学に行き始めたらどうするんだ、と思って訊いてみた。 「でもその、好きな人ができたら橋を渡してやるとかなんとか、きのう……」 俺がそう言うと、兄貴は、あああれか、というように頷いた。 「だからそのためにおまえがいんじゃねえか。郁に変な虫がつかないように見張ってろ。万一それっぽいのができたときには――」 「できたときには?」 「あいつが自覚するまえに俺に知らせろ。手をまわす」 その笑みの獰猛さから、俺は「手をまわす」というのが、「橋を渡す」とは反対の意味であるということを悟った。 小さな脱力感を覚えて、今は郁の城となっている、マンションの中を見まわした。 郁はこれから少しずつこの巣を出る。だが兄貴はどうやら、その小鳥が他人から餌をもらうことを一生許しそうにない。 そして俺のちんけな仕事――小鳥の世話も、当分続きそうで、喜んでいいのか悲しむべきなのか、正直よくわからなかった。 でもどうするかと訊かれたら、やっぱり俺は郁を見捨てられそうにない。 世間知らずで、鈍感で、淫らで――でも、やっぱりかわいい郁。今は高価な羽布団の下で、すやすやと眠っているであろう、きれいで可哀相な籠の鳥のことを。 【終】 |
| 1 / NOVEL2 / HOME |