| 1 / NOVEL / HOME |
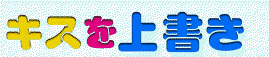 曙光学院新聞部による校内新聞『Aurora(オーロラ)』。ローマ神話の曙の女神の名前だそうである。その記事はささやかながら、校内に波紋を投じた――主に、新校舎と旧校舎のそれぞれ最上階で。 ――好きな科目はなんですか? えーと、音楽と美術。 ――苦手な科目は? 数学と理科と社会。と英語。 ――生徒会役員になって良かったと思うことは? 生徒会室に扇風機と冷蔵庫があること。あとクラス役員の免除。 ――では反対に困ったと思うときは? 特にないけど、そうだなー、帰りが遅くなるのでお腹がすくことかなぁ。 「うーん。相変わらず質問もマンネリだけど、これが高校二年生の答えとはちょっと思えないな」 声に出してインタビュー記事を読んでいた岡村兵三は、呆れたように肩をすくめた。 『生徒会役員に突撃』シリーズ第四弾。ちなみに生徒会長である兵三自身は、第一弾でとっくに義務を果たしている。 「うっさいな。その日急に言われたんで、何も考えていかなかったんだよー」 駆は反対向きに跨った椅子の背に、ぷうっと膨らませた頬を乗せた。 ――彼女はいますか? ……いないです。 背後から、兵三のものとは違う、澄んだ声が記事の続きを読み上げる。駆はわずかに身を縮こませた。 ――好みのタイプは? ええと、髪が長くて色が白くて、おとなしい子がいいです。あんまり人を叩いたりしない……。 バシッ。 「いてーっ」 丸めた新聞で見た目も中身も柔らかい栗色の頭を叩いたのは、駆の双子の妹、言わずと知れた副会長の中和恵だった。ちなみに彼女はシリーズ第二弾であまりにも辛らつな答えばかり並べたために、記事にならないと新聞部員たちを半泣きにさせた張本人である。 「なんなのよ、この〝人を叩かない〟ってのは!」 「いてーな。言葉通りだよ。そんなん人のことバンバン叩いてる奴は彼氏のなり手がいねーぞっ」 恵はフン、と鼻を鳴らした。きりりとしたその美貌が一生その手には不自由しないことを、周囲はもちろん、本人もよく知っているから憎たらしい。 「だいたい、何だよ。おれがインタビューにどう答えようと勝手だろ? 兵三や恵の悪口言ってんじゃないんだからさ」 「ばっか」 「いてっ」 もう一度ぽかりとやられた。 「生徒会役員として、もうちょっと威厳のある受け応えをしてもらわなきゃ困るのよ。こんな幼稚園児みたいな人間に執行権を与えて大丈夫かって生徒が不安になったらどうするの」 駆は唇を尖らせてそっぽを向いた。十六歳男児でこういう仕草が似合うのは彼の特権だ。 「……実際に予算を組んだりするのは恵たちじゃないか。会計なんて言ったって、どうせおれは電卓しか叩いていないんだから……」 「あ、こないだの収支、また数字が合わなかったぞ」 絶妙のタイミングで兵三が口をはさんだ。 ぴしっと音がする。 恵の手の中の新聞が裂けた音か、彼女の額に青筋の立つ音か。 「駆っ!!」 「あー、くそくそ、恵のばっかやろう……」 運動部の連中が賑やかに駆けまわっている放課後の校庭を、駆は文句たらたらで横切った。 扇風機のある涼しい生徒会室を追い出されたのも腹立たしければ、行く先が苦手な旧校舎というのもそれに拍車をかける。 『第二資料室へ行って、過去五年の文化祭の部屋割り資料をとってきて』 もちろんそんなことは会計である駆の仕事ではない。だが反論しようと見上げた恵の顔には、「同じことは二度言わないからね!」とはっきり書かれていた。 「あーあ、ヤだな。旧校舎……」 曙光学院の歴史ある木造校舎は、ほとんどが特別教室や一部のクラブの部室に使われているが、さまざまな理由から空き室になっている教室も多い。そういうところは大概物置か資料室になっていて、駆のお使い先もその一つだった。 だが空き室になっている理由を考えると、駆は憂鬱な気分になる。つい一ヶ月ほど前、噂に聞くだけだった旧校舎の怪異を実際に体験させられちゃった身としてはなおさらだ。 「あーあ……」 擦れ違った柔道部の面々が「不機嫌そうな顔も可愛いなー……」などと密かに思っていたことなどには露ほども気づかず、駆はようやく重い足を旧校舎に踏み入れた。 「あれ……」 「やあ」 昇降口で駆を出迎えたのは、いかにも偶然今降りてきました、という格好のオカルト研究会部長だった。 「生徒会の用事?」 「あ…あ、うん」 駆の返事は煮え切らない。 このオカ研の佐上篤士とは春から犬猿の仲にあったのだが、色々あって、今は会うと何となく複雑な気持ちになってしまう駆である。 色々ったって、色々ったって、ちょっとだけどな! 自分に言い訳しながらも、ちょうど例の事件絡みで彼のことを考えていなかったわけでもないので、駆はわずかに頬を紅潮させて横を向いた。 もしそこで視線を逸らさず、正面から佐上の顔を観察していれば、いつもは涼しげなその顔にわずかばかりの怒りが浮かんでいることに気づけただろうか――いや、所詮中和駆にその手の鋭敏さを求めるのは無理というものだろう。 どちらにせよ、目線を泳がせていた駆は、眼鏡のレンズが怪しく光ったことには気づかなかった。 「どこ行くんだ?」 「第二資料室……」 「案内してやろうか」 「えっ、いいよ!」 駆はびっくりして、階段に立った相手を見上げた。いくら旧校舎に寄りつかないとは言っても、第二資料室がどこにあるかくらい知っている。 駆がそう言うと、 「第二資料室はこないだ移動したんだよ」 「えっ、ほんと?」 「うん。やっぱり知らなかったんだな。おいで。三階になったんだ」 佐上はそう言うと、さっさと背を向けて階段を上り始めた。 「あっ、あの……」 「何?」 振りかえってすぐについてこない駆を見下ろし、佐上は眉をひそめる。 「あの、あんたはいいの? 何か用事があったんじゃ……」 意外にも殊勝な駆の態度に、佐上は一瞬目を見開き、すぐにくすりと笑って、いいんだよ、と答えた。 「どうして第二資料室が移動になったか教えてやろうか」 ちょうど、どうして旧校舎は空調設備があるわけでもないのに涼しいのかなぁ、と考えていた駆は、先を行く佐上の声に顔を上げた。先ほど校庭を渡ってくるときにかいた汗が、なんだか冷やりとする。 「……どうして?」 何となく嫌な予感がしながらも、駆は聞かずにはいられない。 「〝お部屋さま〟って知ってる? それがねぇ、第二資料室に出るってんで立入禁止になったのさ」 開け放した窓からグラウンドの喧騒は聞こえるのに、階段では誰ともすれ違わない。部活が終わるのがまだ先の中途半端な時間帯だからかもしれないが、駆は薄暗がりに浮かぶ白いシャツの後ろ姿を見上げて、急に心細くなった。 そんなに先に行くなよ。 「……知らない。何、それ」 「おれもよく知らないんだけど、部屋に棲みつくらしくてねぇ。失せ物を探してくれたりとか、いい面もあるけど、気に入ったものがあると逆に隠したりするらしい。神隠しみたいにいなくなった生徒の記録がうちにあってねぇ……」 こっち向いて話せよ。 「き、気に入ったものって、人間もなのか?」 駆の声が震えているのに気づかないのか、佐上はどんどん階段を上っていく。 「ま、古い話だけどね。とりあえず大事をとって第二資料室は封鎖したんだよ――と」 引き離されまいと足を速めた駆は、突然立ち止まった佐上の背中に鼻をぶつけた。 「な、何だよ、急に!」 「何だって、三階に着いたんだよ。ほら、資料室はそこ」 そう言って佐上は、何の変哲もない木の引き戸を指差した。どこにも『第二資料室』とは書かれていないが、以前の教室も手書きの紙が貼ってあっただけだったし、急な移動だったので、まだそこまで手が回っていないのだろう。 目的地に着いた安堵感もあって、駆は促されるままにガラリと戸を開けた。 かび臭い教室内はがらんとしていたが、部屋の中央に机、隅にいくつか棚が並んでいる。あれが資料だろうか。 そう思ってそちらに駆けだそうとした駆は、後ろから、ぐいとシャツの襟をつかんで引き戻された。 「ぎゃん!」 散歩中に不意に飼い主に引綱を引かれた子犬のような悲鳴が上がる。 「な、何すんだよ!」 「……その前に」 背後から地を這うような声が聞こえ、顔の前にべろん、と紙が垂らされた。 「これはナニかな?」 「えっ、えっ? あれ……何だ、これ、『Aurora』じゃんか」 突然のことで驚いたものの、身を引いて紙面から顔を離してみれば、それは確かに本日発行されたばかれの校内新聞。先ほど恵がぺちぺちと兄の頭を叩いていた、それである。 これが何だよ、と言わんばかりの駆の耳元で、インタビュー記事が読み上げられた。 「〝好みのタイプは?〟〝ええと、髪が長くて色が白くて、おとなしい子がいいです。あんまり人を叩いたりしない〟」 「もう、またそこかよ! 叩くってのは別にあんたのことじゃないよ!」 「え? 叩く? あ、いや、ここは、まあいい。許容範囲だ。許す。問題はその次だ」 なーにが許す、だ。おまえは何様だ。 そう言ってやりたいが、耳元でこそこそしゃべられると何となくくすぐったく、駆は首をすくめるようにしてその場でじっとしていた。 「〝ずばり、ファーストキスはいつでしたか?〟〝まだです〟」 たっぷりと沈黙があってから、駆の不満そうな声が響いた。 「……それが何だよ。どうせあんたも、高二にもなってまともに女のコと付き合ったこともないのか、って馬鹿にしたいんだろ。いいさもう、さんざんクラスで笑い者にされたんだから。だけど、恵相手じゃなかっただけマシだって言ってくれる奴もいたんだからな」 キャンキャンと喚く子犬の背後で、確かにその可能性もあり得たな、と頷きかけた佐上の顔が、はっと思い直したように引き締まった。 「……その言いようじゃ、隠そうとしてごまかしたってわけでもなさそうだな。おれは別に唇の処女性なんかにはこだわらないつもりだったが」 「何でごまかす必要があんだよ。したならしたっておれは言うよ」 「馬鹿」 ゴン、と駆の頭に拳骨が降ってきた。 「いってぇ~。何だよ、もう! あんただって人のこと叩くじゃないか!」 「怒ってんだから、当たり前だ!」 「痛いっ! ボカボカ殴るなよ。馬鹿になったらどうすんだよ」 「それ以上馬鹿にはならないから安心しろ。……って、おまえ、おれが何で怒ってるのか、本当にわからないのか?」 佐上の声に呆れたような響きが混じった。 「わかんない」 「おまえなぁ」 目の前に垂らされていたインク臭い紙のカーテンが取り除かれたので、駆は目をぱちくりと瞬かせた。 「こっち向け」 言われるままにおとなしく後ろを振り向く。 くしゃくしゃの新聞を握ったまま腕組みをした佐上がじろりと見下ろしていた。 「おまえ、忘れてないよな」 「何を」 「おれがおまえにしたことだよ。先月。部室で。おまえが乗りこんできた夜」 「あっ、あっ、あっ……」 小さなピンク色の耳朶がたちまちカーッと赤くなった。 それを見て、佐上がほっとため息をつく。 「良かったよ。おれはまたおまえのことだから、犬に噛まれたのと同じくらいに考えてるんじゃないかと心配した。比喩じゃなく」 「おっ、おれだってベロチューくらい知ってるよ!」 駆は真っ赤になってうつむいたが、本当のところは半分くらい嘘だった。 オカ研のソファの上で、佐上に舌を舐められたりかじられたりしていたときは、わけのわからないお化けのようなものに襲われた直後で怖かったし、正直何をされているのかはよくわかっていなかった。幽霊を撃退するおまじないか何かかと思ったくらいだ。 後日自宅のテレビで洋画のラブシーンを見ていて、「あれはひょっとしてキスだったのか!」と思い至った、というのが真実である。だが賢明にも駆はそのことを黙っていることにした。恥ずかしかったからである。 「それじゃこのファーストキスがまだっていうのはどういうことだ? 男としたキスはキスに入らないとでも?」 「だってあれは……」 「だって、何? もっと大きな声で」 「だってあれはキスだけど!……ファーストキスじゃないだろ?」 「なんで?」 佐上は本心からわからない、という顔をした。 「だって!」 駆はじれったげに足を踏み鳴らした。 「あれは確かにキス……だけどさ! あんな! 舌噛んだり、歯ぐき触ったり、涎を舐めたりするのが初キスのわけないだろ? ファーストキスってのはもっとこう、かわいいもんじゃないか。放課後の校庭の隅とか、図書館の本棚の陰とかで、こう、ちゅっと……」 言っているうちに自分でも恥ずかしくなったのか、駆はごにょごにょと語尾を濁してしまった。 これ以上はないというほど真っ赤になって深くうつむいている相手の柔らかそうなつむじを、佐上は唖然として見下ろした。 「つまり、おまえが言いたいのは、あれはファーストキスと呼ぶには……ええと、その、ディープ過ぎると、そういうことなのか?」 少しの間。 そして、こっくり。 佐上は本気で頭を抱えたくなかった。 中和駆の思考が人とは違ったように働くことは知っていたが……。 ――しかし、すっげえドリーム入ってるなぁ。 放課後の校庭か。きっとバックには夕陽が、校庭にはサッカーボールの一つも転がってるんだろうなぁ。 だが、佐上のそれは小学校の図書館だったのだから、あながち的外れな夢とも言えない。それに部室で思わず理性を飛ばし、初心な子犬に情熱的なやつをかまして相手の理想を壊すような真似をしたのは、自分にも反省する余地はあると思う。 「わかったよ」 佐上はもう一度軽くため息をつくと、眼鏡を外して尻ポケットに入れた。片手を伸ばして華奢な腰を引き寄せると、小さな顔がはっと上を向く。 思わぬ至近距離におどおどと泳ぐ目を優しく見下ろし、佐上はにっこりと微笑んだ。 「ご期待に応えよう。あいにくここは校庭じゃないが……。放課後の、人気のない教室、じゃだめか?」 「だ、…だめってことはないけど……」 「ちょっと埃っぽいしかび臭いな。ご希望なら場所移すけど?」 「えっと、えっと……」 「このままでいい? だめ?」 「……」 「黙ってるってことはいいのかな?」 鼻先を触れ合わせると、駆が必死で焦点を合わせようとして、きゅうっと寄り目になった。 「目、閉じなさい。そういうのがイイんだろ」 低い声で囁かれ、駆はうっとりと目を閉じた。 なんと流されやすい子犬だろう。催眠術の実験台なんかにしたら一発でかかりそうだな、と佐上は考えた。 それでも伏せたまつ毛がふるふると震えている様子は、このまま時間を止めてしまいたいほどかわいい。小さな箱根細工か何かの箱に入れてしまっておきたいな、と半ば本気で思えるほどだ。 そのまつ毛に触れるか触れないかのところまで唇を近づけかすかな感触を楽しんでおいて、いったん顎を引き、顔を傾けて、再び唇を寄せた。 彼の指定通り、一瞬だけ、ちゅっと音をたてて触れる。離れる感触を惜しむようにかすかに前のめりになる華奢な体を、肩と腰にまわした手でしっかりと支えてやり、何気なさを装って、そのまま薄い背中の肉を撫で上げた。 「……はい、おしまい。これでいいか?」 ぴくぴくっと震えたまぶたが、ゆっくりと開いた。 右手が上がり、無意識のように人差し指と中指が下唇をたどる。 この仕草を高校生男子がやって、しかも似合ってしまうから凶悪である。 見下ろす佐上は、自分もこっちをファーストキスにしちゃおうかな、と考えた。もともとファーストキスなんてものは自分以外の誰にも証明できないのだから、都合のいいように捏造してしまえばいいのである。 ――たいして好きなコでもなかったしなぁ。もうあんまり顔も思い出せないし。 相手の女の子が知ったら憤死しそうな言いぐさだった。 一方駆の方は、夢心地から覚め始め、もう少し現実的なことを考えていた。初キスもまだだと馬鹿にしたクラスメイトたちに、どうやってそれを済ませたかを知らせるかである。 いや、クラスメイトだけでなく、今や自分の未経験は全校生徒の知るところであり、早くそのイメージを払拭したいのだが、まさか新聞記事を訂正させるわけにはいかない。 どうしようかなぁ、と悩み、それでも嬉し恥ずかし青少年のハードルを一つ越えた余裕からか、「今晩ゆっくり考えればいいや」というところで気分は落ち着いた。 ファーストキスの相手が男で、軽々しく誰彼に言えるようなものではないと気づくのは、その「今晩」であろう。 ふいに、教室のどこかで、かたん、と音がした。 このまま手を離そうか、いやいや、いくらなんでもこれだけではあまりにもレベルダウン、ちょっぴり剥いてしまおうか、などと不埒なことを考えていた佐上は気づかなかったが、その腕の中にいた駆は物音に振り返った。 見ると、ぽつりと置かれた机の上で、書類の束がぱらぱらとめくれている。 「あれ……」 入ってきたときは気づかなかった、と思いながら、駆は佐上から離れて机に近づいた。ぱらりと閉じた表紙を見て、素っ頓狂な声をあげる。 「よくわかったね。おれ、言ったっけ?」 「何の話だ?」 少々不満げに、それでも教室の真ん中までやってきた佐上は、駆と並んで机を覗きこむ。 「文化祭の部屋割り資料。出しといてくれたんだろ。ありがとう」 佐上は黙りこんだ。 あのタイミングで、いつ自分に駆の探し物がわかったというのだ。 昇降口で会ったのは偶然ではないが、それは部室の窓から校庭を渡ってくる駆の姿を見つけてあわてて下りてきたからなのだ。 大体、第二資料室が移動したというのは嘘である。あれは適当な教室に駆を連れこむためのでまかせだった。 膨大な資料の山から探さずに済んだ、と無邪気に喜んでいる駆の横で、佐上は思わず教室の中を見まわした。 ――嘘だろう? 第二資料室に〝お部屋さま〟が出る、というのも、もちろん嘘だった。臆病な駆を怖がらせようと思って、先日昔の部活ノートを調べていて見つけた名前を拝借したのだ。 世の中には、嘘からでたまこと、ということわざがある。常に冷静なはずのオカルト研究会部長、佐上篤士の喉が、ごくりと鳴った。 失せ物探し。 そして気に入ったものがあると――。 ――まさか。もしかして。この部屋に? 閉めきったはずの教室で、まるで風に吹かれでもしたように資料のページがまたぱらぱらとめくれ、どこかの床がきいっときしんだ。 振り向きたくて、振り向けない。 〝お部屋さま〟に気に入られてしまったのは、いったいどちら? 【Fin.】
|
| 1 / NOVEL / HOME |