| 1 / NOVEL / HOME |
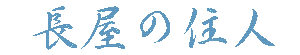 佐治(さじ)がそれを見つけたのは、本当の偶然だった。 鳶(とび)仲間の寅と一杯引っかけた帰り道。働き者の夏のお天道さんも、さすがにそろそろ店じまいという時刻で、ふらつく足をそれなりに急がせて渡ろうとした小さな橋のたもとで、何か白いものが動くのが目についた。 なんだ、と思う間もなく、それはごろっと転がってぽしゃっと川の中に落ちた。 「おいおい」 佐治はあわてて草の茂った土手を降りた。川といっても水はちょろちょろ、底の砂利が見えるほどである。 その中に、灰色と茶色の中間のような、汚れた毛皮が横たわっていた。 「犬……いや、猫かい」 佐治は特に動物好きということはなかったが、さよが小さな生き物が好きで、怪我をした雀を飼っていたこともある。 ぐっしょりと濡れたかたまりに手を伸ばしたのは、嫁に行ったばかりの娘に対する感傷があったからかもしれない。 「あー、こりゃやっぱり猫だな。おい、生きてんのか」 力を失った体は見かけによらず、ずしりと重かった。佐治が懐に抱えると、妙に長い尻尾がだらりとぶら下がる。 顔をのぞきこむと、小さな口は力なく半開きだったが、長い髭の生えた鼻がぴくりと動いた。 「おっと、よしよし、生きしぶてぇのはいいことだ。これも何かの縁だ、おれが面倒見てやろう」 佐治は猫を抱えたまま器用に半纏を脱ぐと、それで濡れた相手を包みこんだ。 「ん?」 ふと、どこかから視線を感じて、佐治は当たりを見まわしたが、周囲に人影はない。 「いけねぇ、ぼやぼやしてたら日が暮れっちまう」 佐治はひとりごちて、足早にその場をあとにした。 「けえったぜ」 声をかけて腰高障子の戸を開けたが、もちろん応える者はいない。さよが幼なじみの加吉に嫁いではや三月だが、佐治はいまだに独りの生活に慣れなかった。 流行り病で恋女房を亡くし、遺されたさよを形見と思って十七年間、男手一つで大事に育ててきた。裏長屋のせまい一間で、身を寄り添うように暮らしてきた、仲の良い父娘だった。 自分がこれと見こんだ加吉に不満はないが、やはり宝物を取り上げられたような、空虚な気持ちは否めない。救いは二人の住まいがここからすぐ近くだということだろうか。今も畳の上に布巾をかぶせた皿が置いてあって、おそらく父親のためにさよが持ってきたのだろう。 くすん、と鼻を鳴らした佐治は、腕の中のもののことを思い出し、家へ上がると、畳の上にそっとそれを下ろした。 濡れた半纏の中から出てきたかたまりは相変わらずぐったりしていたが、佐治はその目が開いているのに気づいた。 物言いたげにこちらを見上げてくる瞳は黄色だった。 「おお、気づいたか。おめぇ、どうしたよ。イタチか犬にでもやられたのかい」 佐治は行燈に灯をともすと、ざっと猫の体を調べてみたが、どこからも血が流れているようすはない。 「おっと、牡か。そいじゃ孕んでるってわけでもねぇだろうし、なんか悪いもんでも拾って食ったか」 猫は力なく横たわったまま、何度か口を開いたり閉じたりした。 「喉かわいてんのか? そっか、おめぇ、水でも飲もうとして落っこちたんだな。よしよし、今飲ませてやろう」 佐治は土間の水瓶から柄杓で水をすくって口元へ持っていってやったが、猫は佐治の顔を見上げたまま、体を起こそうとはしない。 佐治は思いついて自分の指を濡らすと、それを差し出した。 猫はしばらくためらったようすだったが、やがてゆっくりと小さな赤い舌を出して、さり、とその指を舐めた。 「うんうん」 佐治は猫がしずくを舐めてしまうと再び濡らし、何度かそれを繰り返した。 猫は満足したように目を閉じた。 佐治は手ぬぐいで濡れた毛皮をぬぐってやり、部屋の隅に置いてあるつづらを漁って、さよが赤ん坊のころの着物を引っ張り出してきた。あらためてそれで猫を包むと、自分の布団の枕元に置く。 猫はされるままになっていて、もう目は開けなかった。だが時折ぴくりと耳が動いて、生きていることはわかる。 佐治は自分も横になり、その夜はそのまま寝てしまった。 翌朝目が覚めると、猫はすでに着物から這い出て畳の上にうずくまっていた。佐治が目を開けた気配に、頭を起こす。 「おお、元気になったか」 佐治の呼びかけに応えるように、猫は首をわずかに傾けて、黄色い目でじっと見つめてくる。 明るい中で見ても、薄い鼠色のような、なんとも冴えない色の猫だったが、長い首といい、尻尾といい、体つきはすらりと引き締まっていた。 目の上の毛が庇(ひさし)のように長く伸びてかぶさっている。左の目尻に一箇所だけ、黒い小さな斑があって、人間の泣き黒子のようだな、と佐治は思った。 猫は昨晩のようすが嘘のようで、布団を畳む佐治の邪魔にならないように軽やかに身をかわす。 さよの置いていったいなり寿司をやると、なかなかの健啖ぶりを発揮した。 今日は向島の方で足場を組む仕事が入っている。猫のことは気になったが、連れていくわけにもいかない。湯のみに水を入れて、残りの寿司を畳の上に置くと、戸を猫が通れるくらいの隙間を開けて家を出た。 元気になったのなら、さっさと出ていくだろうと思いながら……。 だが、佐治の予想に反して、猫は十日経っても長屋を出ていかなかった。 仕事から帰っても姿が見えないことは何度かあったが、それでも佐治が飯を食っているとどこからか帰ってくる。蚊柱の立つ泥溝板(どぶいた)を音もなく踏んで、自分のために開けられた隙間からするりと体を滑りこませ、当然のように相伴に預かるのだった。 実際、猫は何でもよく食べた。猫の好物など、佐治はよく知らなかったが、自分が食べるものを少しずつ同じように食べ、おもしろ半分に勧めてみると、酒まで舐めた。 「お父(と)っつぁん、最近帰りが早いんだね」 いつものように野菜の煮たものを父のもとに届けに来たさよは、畳の上で所在なげにしている佐治を見つけて、驚いたように言った。 「そうかい、前からこんなもんだったろ」 鳶の仕事は暗くなるまでするものではないし、実際、佐治もさよが嫁ぐ前は、まだ日の高いうちにまっすぐ家へ戻ってくることが多かった。仲間と飲みに行ったり、遊びに行ったりするようになったのは、独りになってからである。 「そうかねぇ」 それでも、早く帰って何をするでもなく、ぽつんと部屋に座っている父親へ不審そうな顔をする娘へ、佐治は猫を飼いはじめたことを打ち明けた。 「お父っつぁんが、猫を! どんなのだい」 動物好きのさよはさっそく見たがったが、猫がまだ帰っていないと知ると、残念そうな声をあげた。 「おめぇ、おれがいない間に時々汚れもんを片づけに来てくれてるだろ。今まで見たことはねぇのかい」 さよは、猫など一度も見たことがない、と首を振った。 実際、さよだけでなく、どうやら長屋の住人でさえ、猫の存在に気づいていないようだった。佐治自身は別に隠すつもりもなかったし、人さまの家を汚したり悪戯したりしなければ、気のいい長屋連中のことだ、うるさく言ったりはすまい。 だが、佐治の家に我が物顔で出入りしている猫のことをたずねてくる者は誰一人いなかった。 その原因の一つは、猫がほとんど音をたてないことにあるだろう。猫はほんのわずかしか足音をたてなかったし、寝起きを共にしていてさえ、佐治はそれが鳴くのを耳にしたことは一度もなかった。 にゃーでも、なーでも、一度聞いてみたいもんだとは思ったが、飯を食べたあとさえ、満足げに舌で口周りを舐めるだけで、感謝のひとこともなかった。 佐治もなんとなくそれでいいかな、という気になっている。 さよがいない孤独な毎日が、たかが猫でも同居人がいるというだけで、違う色になる。 ちょっと一杯、と誘う仲間をことわって、まっすぐ家へ向かう。大好きな銭湯だけは欠かさないが、熱い風呂から上がっても二階でゆっくりすることもあまりなくなった。 仕事場では女ができた、と噂されているようだった。男やもめで四十近くでも、佐治はまだまだ逞しく、日によく焼けて張りつめた二の腕などは、そこらの若い者には負けないだけの力を蓄えていて、遊びに行けば声をかけてくる女に事欠かなかったからだ。 だが現実には名前もつけていない薄汚れた猫のために、佐治はせっせと家路を急ぐ。途中の屋台で天ぷらを買ったりもしてみる。 下手に猫の存在を知らせて、お節介な長屋の女共に邪魔をされることを思うと、自分から言ってまわるのはやめておこうと思うのだった。 あん……。 佐治はごろりと寝返りをうった。 ああん、あん……。 佐治は布団の中で、ちっと舌打ちをした。 貧乏長屋の壁などあってなきがごとしである。そのあたりは大っぴらなもので、夫婦者の夜の声が漏れ聞こえてくるのは珍しくもなかったが、数日前から隣に入った若い二人の場合はちょっと度を越していた。 今朝、井戸端で噂好きの女たちに耳打ちされたところでは、どうも駆け落ち組ではないかということだったが、嬌声や泣き声が一晩じゅう絶えない。 特に佐治の部屋との間には壁の破れ目があって、以前住んでいた羅宇(らお)屋の爺さんとは、そこから物をやりとりしたものだが、今はこちらから紙を詰めてある。 「……ったく」 佐治は暗闇の中、ごそごそと下に手を伸ばした。ゆるめた下帯の横から手を差し入れる。 煽られて兆しはじめている部分を掴んで扱く。 「そういや、しばらく遊んでなかったからなぁ」 佐治の相手はすべて玄人だが、それでもさよが一人前になる前から付き合いのある、馴染みの女もいる。彼女たちの白い手やら柔らかい壺やらを思い出しながら、佐治は自分のものを引っ張りだし、布団の上で横向きになってごしごしと擦りはじめた。 あん、あん……。 ああん……。 ただでさえ蒸し暑い夜である。若い女の張り上げる声を壁越しに聞きながら背をかがめて励んでいると、すぐに汗が流れてきた。 「うう、」 もう少しだ、と佐治が手を早めたとたん、 「ほあああ……」 突然、足元から声があがって、佐治はぎょっとして頭を上げた。 足元、というか、膝のすぐそばに、黄色い目が二つ、光っていた。 「お、おめぇ」 猫だ、と気づいて佐治は半分あわてたが、手の中のものははちきれんばかりで、あとちょっとで往生、というところである。止めるわけにもいかず、握ったままにしていると、剥き出しの亀頭の先を、さり、と何かがかすめた。 もちろんそれが決定打となった。 熱い、ざらざらするものに舐められた途端、佐治の物はびゅうっと吹き上げた。 「う、うおっ」 佐治は、思わず目を閉じて、溜め込んでいた精を存分に吐き出したが、すぐにはっとして跳ね起きた。 「おいっ、おめぇ」 あわてて行燈の引き出しをさぐり、火打と付木を取りだし、震える手で灯をともす。 ふわっと黄色い明かりに浮かび上がったのは、体を濡らした猫の姿だった。 そうだろう、声からして、あの位置ではまともに佐治の出したものを浴びたはずである。 「す、すまねぇ、」 佐治は真っ赤になって、そのへんにあった手ぬぐいで拭いてやろうと、猫に手を伸ばした。 だが、猫はさっ、とそれを避け、部屋の隅に逃げる。そこで「ふああああ」と、もう一度鳴いた。 「お、おめぇ……」 ぞくりと体の芯に響くような声だった。 言葉もない佐治の目の前で、猫はぺちゃ、ぺちゃ、と音をたてながら、体中についた白いものを、丹念に舐めとった。 「まったく、どういうこった……」 佐治の悩みは深い。 悩みがあっても食欲は変わらないが、夕飯が終わるとまた頭が痛くなる。 猫は今日も満足そうに飯をたいらげ、顔の毛をつくろっている。もはや彼の寝床となって長い、色あせたさよの赤い着物の上でくつろぐその様は、何度見ても普通の猫である。 だが、佐治が灯かりを落として横になってしばらく経つと、 「ほわあああ」 という声がして、太腿にちくちくしたものが押し当てられる。 「駄目だ」 佐治は目を閉じたまま、きっぱりと言う。 「ふあああ」 猫は佐治の腿に足をかけたまま、ねだるように鳴く。よそには聞こえないような小さな声だが、佐治には言いたいことがわかるような気がする。 佐治が黙っていると、猫は太腿を越えて、下帯の膨らみそのものに足を伸ばす、 「こらっ、何やってんだ」 佐治は乱暴にならないよう気をつけながら、猫を手で払いのけた。 「ほあああ」 「駄目だっ」 もう一度強く言うと、猫はそれ以上はしつこくしない。 あああ、と残念そうに鳴いて、寝床にもどっていく。佐治はなんとなく、そちらに背を向けてしまう。 今や猫が鳴くのは珍しくない。だが、それは夜だけである。佐治が眠る体勢に入ると、足元に来て鳴くのである。放っておくと、体を登ってきて、腹や股を踏む。 普通なら猫に踏まれるくらいなんということはないだろうが、その意図がわかるだけに、こちらも反応してしまう。またその踏み方が絶妙なのである。 佐治は初めて引っかけてしまった晩を含めて二度、これまでに猫相手に逐情してしまった。 さすがに二度目は何かの間違いだと己をごまかすこともできず、それ以来下帯を固く締め上げて寝るのが習慣になってしまっている。 「いってぇ、どうなっていやがるんだ……」 遊女屋で、犬の狆相手にいたす奥女中、という枕絵を見せられたことがあるが、あれが猫の好物だという話は聞いたことがない。それとも一度舐めたら病みつきになってしまったのだろうか。 そんなものが好きな猫もこわいが、そんな畜生を追い出そうともしない自分はもっとこわい。 だって、おれはあいつがかわいいんだ……。 「ああああっ、くそっ」 佐治は仕事中何度もうなり声を上げ、仲間をぎょっとさせて、しまいには親方に怒鳴られる始末だった。 佐治は悩んだ挙句、ある晩、家に帰らなかった。 茶屋の女で、みつ、というのがいる。かなりの年増だが色気はまだまだ健在で、気に入った男なら、金を出せば抱かせてくれる。佐治はそう何度も世話になったわけではないが、誘って断られたことはなかった。 一戦終えた女の布団の中で、けだるげに胸をまさぐられながら、佐治は長屋の暗い部屋でひとりいるであろう、猫の黄色い瞳を思った。 たかが拾った猫相手に、なぜ後ろめたいような気分になるのだろう。 「どうしたの、眠れないのかい」 「……なんでもない、おみつさん、もういっぺん、いいかい」 「ふふふ、いいよう、強い男は好きさ……」 佐治はぷるっと頭を振って、女の柔らかな乳房に顔をうずめた。ちくちくと毛の生えていない、つるっとした肌だった。 てやんでぇ、気になるもんか……! ところが、次の晩、帰ってこなかったのは、今度は猫の方だった。 まさか自分の外泊に関係するはずはないと思うものの、もしかしたら昨日も戻らなかったのかもしれないと思うと落ちつかなくなった。 猫はその次の日も帰らず、佐治は心配でたまらなくなった。拾ったときの事情が事情で、またどこかで行き倒れているのかもしれない、と思った。 猫のいない晩が三日続き、その翌朝は小雨が降っていた。仕事は休みである。 猫を探したいとは思うものの、どうしたらいいのやら検討もつかない。 長屋の連中に訊いてみたが、案の定、知らない、という答えしか返ってこなかった。やはり佐治が猫を飼っていたのは全く知らなかったようである。 佐治は破れ傘をさして、さよをたずねていった。さよの夫である加吉はぼてふりの魚屋だが、やはり雨だというので家にいた。 猫が帰らないというと、さよは残念そうにしながらも、逃げたのだろう、と言った。 「よそで飼われてるかもしれないねぇ」 「そんな人が飼いたくなるような、きれいな猫じゃなかったけどよ」 「でもお父っつぁんがそんなにかわいがってたんだから、見る人が見ればいいとこがあるのかもしれねぇよ」 佐治はうう、とうなった。 娘夫婦は、もしどこかでそのような猫を見かけたら必ず知らせる、と約束してくれた。 加吉は若くて気風がよく、得意先もたくさんあって稼ぎもいい。傷心気味な義理の父親を気遣って、雨の中、蕎麦屋に誘ってくれた。 佐治がどうしてそんな猫に執心なのか、今いちわからないようすではあったが、佐治がぼそぼそと語る猫との出会いやこの夏の一緒の暮らしなどに辛抱強く耳を傾けてくれた。 時折、佐治が何かを思い出したように顔を赤らめるのを不思議そうにしつつ、だいじな一人娘を手放してやはり寂しいのだな、と結論づけてくれたようだった。 加吉と別れ、佐治は傘をさしたまま、猫を探してうろつきまわった。 雨のせいだろう、雀一羽見当たらない。それでも露地の奥、天水桶の陰を一つ一つ確かめてまわった。 猫はいなかった。 佐治の頭の中に、最初の晩、猫が力なく自分の指先から水を飲んだようすや、同じ飯を食べて満足げに目を細めていたしぐさ、障子戸の隙間からするりと入りこんできて、汚れた畳の上に飛び乗る優雅な動作が、くりかえし浮かんだ。 いつの間にかかなり遠くまで来てしまい、足は泥はねでさんざん汚れ、いい加減あきらめて帰ろうと思ったときだった。 小さな稲荷神社の境内で、女がひとり、後ろ向きにうずくまっている。木陰で雨宿りでもしているのだろうか、と思ってさらに近づくと、女の向こうに灰色の影が見えた。 あの猫だ、とすぐわかった。 女と猫はまるで内緒話でもするように、顔を寄せ合っている。 と、佐吉の気配に気づいたように、女が振り返った。 佐吉はぎくりとした。 女の目が、白目も何もない、真っ黒に見えたからだ。二つの眼窩は、底無しの闇のようだった。 だがそう思ったのは一瞬で、佐治が目をしばたたいてもう一度見ると、女の目は普通だった。 女というよりは娘という年頃で、立ち上がると、綺麗な澄んだ目でにっこりと笑った。 「これ、おじさんの猫?」 「あ、ああ、そうだ」 佐治は答え、足もとの猫に目をやった。 猫は目元に小さな黒斑のある黄色い目で、糸のように降り注ぐ雨の向こうから、じっと佐治を見上げていた。 佐治が手を伸ばしても、暴れたりせず、おとなしく抱かれるままになっていた。汚い色の毛皮は初めて出会った時のように湿っており、佐治はそっと懐へ入れた。 「もしかして、探してたの?」 「ああ、しばらく帰らなくってね」 佐治がさしていた傘を差し出すと、娘はためらうようすもなく、受け取った。 「猫はね、すぐどこかへ行っちゃうよね」 娘は、綺麗な着物に不釣合いな破れた傘を、それでも嬉しそうにくるくると回した。 「でも、絶対帰ってくるから、待っててやってね」 娘の声を背に、佐治は濡れながら神社を後にした。 佐治と猫は夕飯を分け合い、二つの湯のみに注ぎ分けた酒を飲んだ。 雨のせいで暗くなるのも早く、佐治は早々に灯かりを落として横になった。 ああん、あん……。 おそらく昼間から乳繰り合っていたのではないかと思われる隣の若い男女が、さっそく始めたらしい。 佐治は暗がりの中で、じっと目を開けていた。 「ふあああ」 すぐ近くで、細い鳴き声がした。 佐治は黙って待った。 「ほわああああ」 猫は再び鳴いた。 太腿にちくちくしたものが触れてきた。 佐治はごくりと唾を飲み、それから下に手を伸ばすと、あらかじめゆるめてあった下帯を解いた。そしてすでに期待で高まっていたものを、両手で握った。 さり、とざらざらした熱いものがそれを舐めた。 「あ、うう」 佐治はわずかに身をよじった。 猫は開かれた脚の間に入り、太腿に片足をかけて、佐治のものを舐め続けた。 「うう……」 佐治は猫に先端を預けたまま、ゆっくりと自分のものを扱いた。猫はその指も一緒に舐め、それから小さな舌で、少しずつ溢れてくるものを丹念にぬぐった。 太腿にかけていた足が動いて、佐治の袋を刺激し始めた。決して爪をたてたりはせず、柔らかく押すように踏んでくる。 「ああ、うう」 佐治の体じゅうからどっと汗が吹き出した。 夏の夜の闇がねっとりと一人と一匹を包んだ。 ふいに猫が佐治から離れた。 「あ……?」 かたん、と何かが倒れる音がする。先ほど飲み残した湯のみの酒がこぼれたらしい。 不審に思う間もなく、また風のようにもどってきた猫が、股間の刺激を再開した。 「あ……」 冷たいものが、軽く膝を立てた佐治の脚の間の、さらに奥を探ってきた。 それは毛羽立ち、濡れていた。 佐治は、双丘の奥に忍んできたものが猫の尾であることに気づいた。 気づいてさらに脚を開いてしまった。 濡れた猫の尻尾は、くねくねと進みながら、後ろの門に触れてきた。 「あ、おい……」 さすがに手を止めてしまった佐治だったが、猫はなだめるように、ふあああ、と鳴いた。 最初のときから、猫の鳴き声は佐治の体の奥を直截刺激した。細いのによく響くその声を聞くと、佐治の体はじんわりと熱くなってしまい、どんな女の媚を含んだ声よりも、彼の耳には艶かしく聞こえるのだった。 佐治はまさしく、もうどうにでもなっちまえ、という気分だった。 猫の供物として恭しく差し出された鯉か何かのように、まな板ならぬ、煎餅布団の上で、息も絶え絶えに脚を開いていた。 佐治が軽く腰を突き上げるようにすると、猫はぐっと力をこめて、後ろを貫いた。 「う、あああっ」 佐治が逞しい肩で支えるように背を反らすと、猫の長い尾は、さらにずるずると中を突いてきた。 猫は闇をも見とおす黄色い目で、紅潮した佐治の体をじっと見つめながら、尾を引き出し、押しこみ、同時に舌でしとどに濡れ始めた筒の先を舐め続けた。 ああ、ん、あん……。 隣ではまだ女の嬌声が続いている。 だが佐治の耳にはもはやそれは届かず、彼は鼻息を漏らし、髷をくじゃぐしゃにつぶしながら、汗の染みこんだ布団の上で体をのたうたせていた。 棟割長屋の、その遥か頭上では、何時の間にか晴れた夜空を統べる月が、人とそうでないものの交わりを、黙って見下ろしていた。 「おや、佐治さん、お帰り」 「早いねぇ」 井戸端でおしゃべりをしていた長屋の女たちは、足取り軽く帰ってきた佐治を見つけて声をかけた。 「よう、精が出るねぇ」 佐治は機嫌よく挨拶を返しながら、戸を開けて自分の家に入った。 「けえったぜ」 応える声も、出迎える気配もない。 猫がいなくなってから、すでに一年近くが経とうとしていた。 熱い夏はあの晩で終わった。 秋になり、冬が過ぎて春が来る間に、猫の気配は佐治の周囲から綺麗に消え去り、帰りに屋台で寿司や天ぷらを買ってくることも、戸をわずかに開けて仕事に行くこともなくなった。 人肌が恋しくなれば遊びに行く。 あの狂ったような悦びは女相手では得られないが、もちろん男を試そうという気にもなれなかった。 「ふう」 買ってきた酒の入った徳利を、そそけた畳の上に置く。 寂しいな、とは思うがしかたない。でも恋女房を亡くしたときの、あの何物でも埋めがたい、うつろな寂しさとは違う。 『絶対帰ってくるから、待っててやってね』 稲荷神社で出会ったあの不思議な娘の言葉を、なぜか信じているからだ。 いつかまた音もなく泥溝板を踏んで帰ってくるような、そんな気がするからだ。 もし再びあの猫がこの長屋の住人となったら、今度は昼日中にも鳴き声を聞いてみたい。佐治を布団に縫いとめるような、あのあだっぽい夜の鳴き声だけでなく、もっとのん気な、平和な鳴き声を。 あの猫とだったら話ができるような気さえするすら不思議だ。好きな食べ物を知り、どこから来たのか、何をしてきたのか、聞いてみたいと思う。 今度こそ、さよや長屋の連中にもちゃんと見せて、お天道さんの下でかわいがってもらうか。女連中に体を洗ってもらったら、あの薄汚れた毛皮の色も、ちったぁましになるかもしれねぇ。 佐治は欠けた二つの湯のみを出してきて、どちらもなみなみと酒で満たした。 「おい、今日はめでてぇんだ、さよにやや子ができたんだぜ」 佐治は湯のみの一つを取り上げると、上機嫌でそれを飲み干した。 「あら、いけないよ、あたしゃ大家さんに掃除を頼まれてたんだった」 「ああ、そうだったね、佐治さんとこの隣に新しい人が入るんだって」 「ようやくかい。あの駆け落ちもん以来、なぜか空いたまんまだったけど。また夫婦もんかねぇ」 「それが、独り者なんだよ。こないだ大家といっしょにいるところを見たんだけど」 「若いのかい?」 「さあそれが年はよくわからなかったんだよ。でも割りといい男だったよ」 「へえ、そりゃ楽しみだ、早く見てみたいもんだね」 「すぐわかるよ、左っかわにおっきな泣き黒子があったからねぇ――」 【終】
|
| 1 / NOVEL / HOME |