| 1 / NOVEL / HOME |
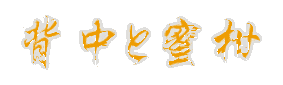 「朝方でしょー、寒くて目が覚めるもん」 「そっかなー、あたしは寝るときの方がツライ。足とか冷たくて痛いくらい」 「あんた冷え性だもんねー。湯たんぽでも買えば?」 「きゃはは、今時湯たんぽはないっしょー」 「それがけっこうイイんだって。今度貸してあげよっか」 「いらなーい」 「なんでよ?」 「新しいオトコできたもん」 「えーほんと? あんた本当にクリスマスはずさないよね。そいじゃ温めてもらってんだ」 「うんこう、太腿の間につま先挟んでもらってさー」 「やだぁ。なんかヤらし〜」 「いいじゃん。あいつ体温高いんだもん」 「ああわかる。カレシがありがたい季節になったよね〜」 「この時期一人寝は寂しいっしょー」 背後の同年代らしい女たちの会話に、加納は口元を緩めた。 彼氏がありがたいというか、確かに人肌が恋しい時節ではある。 そういえばいつの間にか狭いシングルベッドで朝まで抱き合って寝ても鬱陶しくなくなっていた。夏の間はたとえクーラーを効かせていても、たいていどちらかが我慢できなくなって床に逃げ出していたものだ。 暦の上ではいつからが冬なのかは知らないが、季節の訪れを恋人の体温で知るというのも悪くはないな、と、加納はカップに入ったホットコーヒーを甘ったるい気持ちで啜った。 あの男を恋人と言い切るのに抵抗がないわけではない。少なくても今まで付き合った女性たちと同列に並べることはできない。 だがそれなりの独占欲も執着もあって、定期的にセックスもしている相手を、他にどう呼んでいいのかわからない。 誰かの前でそう呼ぶことはきっとないだろうから、自分の内ではとりあえず恋人と呼んでも悪いことはないだろう。親友と呼ぼうがセックスフレンドと呼ぼうが、彼が今のところ自分と一番近い位置にいるのは間違いないし、やってることも変わらない。言葉による意味付けなど、加納には些細なことだった。 そういう意味では、自分は今、恋人を待っている。 ジムで泳いでいる相手と待ち合わせをしているのだ。 「あれ」 ガラス越しに、建物の入口から出てくる背の高い人影を見つけて、加納はカップを下ろした。 「何やってんだ、あいつ」 女性と連れ立って現れたのは藤堂だった。通りを渡ってくるかと思いきや、そのまま二人で建物の右手へと向かう。 「なんだよ、待ってるって言ったのに――」 加納はあわてて左手で上着を掴み、右手でトレイを持って立ちあがった。 まだわずかにコーヒーの残ったままのカップをダストボックスに放りこみ、急いでファーストフード店を出る。 手間取っている間に二人の姿は消えていた。 加納はブルゾンに手を通しながら左右を見極めて車道を渡った。 「ちぇ、どこだよ」 スポーツセンターの右隣は小さなショッピングビルになっている。テナントは二階からで一階はパティオになっているのだが、そこに足を踏み入れたとたん、加納の耳に女性の声が聞こえてきた。 「……だって……ちっとも……誘っても…だからわたし……」 藤堂さん、という言葉がはっきり聞こえて、加納は思わず足を止めた。 吹きさらしで寒いせいか、ビル自体がはやらないせいなのか、パティオには他に人影かもなく、その中央で藤堂と小柄な女性が向かい合うようにして立っていた。 「へえ……」 どう見ても藤堂が女に告白されている図、である。加納は興味を押えきれずに耳をすませた。 無口で地味な藤堂が意外にもてるのだと知ったのは、付き合い始めてしばらくたってからだった。 仏頂面でとっつきにくいが、ずば抜けて背が高く、肩幅も広い。男の加納が見てもいい体だな、と思うし、一度プールで泳ぐ姿を見てますますその度を深めた。 寡黙な性質を男らしいと評する女性は少なくないだろうし、見かけほど無愛想な性格でもない。どうでもいい人間に対しては素っ気無いが、友人や恋人にはひどく甘いところもある。 浅い付き合いではわかりにくいこの男の良さに気づくだけの審美眼を、かえって誉めてやりたいくらいだった。 だからといって、もちろん譲ってやる気などこれっぽっちもないが。 加納はコンクリの壁に寄りかかり、相手を無表情に見下ろしている藤堂の横顔を遠目に眺めた。 女の子は大学生か、もしかしたら高校生かもしれない。この寒いのにミニスカートで、ニーソックスとの間に覗く素肌のバランスが絶妙で可愛らしかった。 そっか、好きな相手にコクるともなりゃ、服装だって吟味するに決まってる。 加納は苦笑いした。変り映えのしない藤堂のジーパン姿よりも、女性の格好に目がいくのは今だ正常な男性の証拠だろうか。 「……どうしても……一度……もし……」 女の子は俯いたまま、まだぼそぼそとしゃべっている。緊張しているらしく、胸に抱えた鞄を何度も持ち替えていた。 藤堂の方は一度も口を挟まない。 やがて女の子が口を噤んでしまうと、沈黙が下りて、辺りにはビル内から響くクリスマスソングが聞こえるだけになった。 しばらくして、藤堂が口を開いた。 ぼそりと一言。 「悪いけど、付き合っているやついるから」 それだけ。 それだけ言って、ますます俯いてしまった相手をその場に残し、こちらに向かってくる。 パティオの入口で加納の姿を見つけ、わずかに目を見開いたが、藤堂は何も言わなかった。 ゼミ以外で藤堂と会うのはだいたい週に一度。セックスを前提としているので、大概翌日が休みの週末になる。 互いの部屋に泊まり合うが、夏にクーラーの効く加納の家が多かった反動で、涼しくなってからはずっと藤堂のところだった。 普通のアパートに住む加納のところと違って、一階が酒屋の倉庫になっている藤堂の部屋は、防音をあまり気にしなくていいので加納も気が楽だ。 ただしエアコンが故障しているので、窓を開けなくてはならない暑い時期は抵抗があった。 五台ほどの自販機が並ぶ倉庫の横の細い階段を、カンカンと音をたてて登っていく。 もとはどこかの事務所に貸していたという二階は藤堂が独占していたが、家賃は驚くほど安かった。 加納はその理由を初めて泊まった夜に実感した。 夜中に誰かが自販機を使うと、そのたびにがたん、がたんと飲み物が取り出し口に落ちる音がする。 そんなに大きな音ではないと思うのになぜか二階によく響いて、慣れないうちはそのたびに目を覚ましていた。 繊細な方ではないのでじきに藤堂同様、気にならなくなったが。 藤堂が携帯のストラップに留めていた鍵で部屋を開け、背後に立っていた加納を先に通した。 促されるままに上がった加納は、一人暮しには不釣合いな大型冷蔵庫の横で足を止めた。知り合いからタダでもらったというのでこんなに大きいらしい。 そこで立ち止まったのは別に冷蔵庫に用があったわけではない。台所を通り抜けようとして、背後から藤堂に抱きしめられたせいだ。 「シャンプーの匂いがする。風呂入ってきた?」 背の高い藤堂が髪に鼻先を埋めるようにして囁く。加納は頷いて体の向きを変えた。 「今日は四限が休講だったから……いったん家に帰った」 「うん……」 どちらも自然囁くような声になる。 「おまえはプールの臭いがする」 「シャワー浴びたけど……」 「だけど、する」 加納が両手を上げて、藤堂の二の腕の肉を強く掴んだ。 洗髪液よりも何よりも、飢えた体は互いの発情の匂いを敏感に感じ取る。 先週は藤堂の、その前は加納の都合で抱き合えなかった。 息を荒げて探り合う。三週間ぶりのセックスが目の前にある。 相手の体が欲しいことを隠さない。隠す必要もない。そこが今までの恋人たちとは違う。藤堂との間に肉体の秘密はない。 自分の奥の奥にある劣情をさらけ出して、引き換えに相手を手に入れる。他の誰にも見せない自分を許して、その代わり相手にも逃げを許さない。 余裕のないキスを交わしながら、藤堂は加納を冷蔵庫の扉に押し付けた。 唇を離すと唾液が糸を引き、二人はそこから目を離さずに、ゆっくりと頭を引いた。 耐えきれずに糸が切れて顎に落ちると、加納がうっすらと笑った。藤堂にしか見せない、無邪気であるがゆえに淫蕩な笑みだった。 周囲の空気は密度を増し、ねっとりと二人に絡みつく。 藤堂は加納の前にひざまずき、ジーンズのファスナーを下ろした。同時に自分の前もくつろげておく。 ここからの時間が長いことを知っているからだ。 下着から兆し始めている加納のペニスを取り出すと、藤堂は上目遣いに「舐めてもいいか?」と訊ねた。 そのとたん、手の中のものがぴくりと跳ねた。 「あの女の子……」 加納は全く関係ないことを口にする。 「女……?」 「パティオの、おまえにコクってた……」 「ああ……」 「大学生?」 「いや、高校生。同じスイミングクラブの……」 「かわいいじゃん」 「まあな」 意味もない会話だということはわかっている。互いに遊んでいるだけだ。 「泳ぎうまい?」 「うまいよ、バックストローク……」 上と下で、二人の目が合う。 一人は冷蔵庫にもたれかかり、一人はその前で彼の性器を掴んでいる。 藤堂は加納の答えを待っている。承諾を得られるまで、決して先へは進まない。 恋人を尊重してるのでもなんでもなく、これが暗黙のルールだからだ。 藤堂が訊ねる。 加納がはぐらかす。 藤堂が待つ。 加納は堪える。 焦らす。 焦らす。 時間を稼いでぎりぎりまで我慢する。その方が快感が高まることを知っている。 だからこそ藤堂も答えを急かさない。 これが二人のコミュニケーションで、楽しい時間なのだ。 「そういえば梅原が、連絡欲しいって言ってた」 藤堂の眉がかすかに寄せられる。 「梅原が……?」 「来月のゼミの発表の話……」 「ああ」 見下ろす加納の目が潤む。 女の子の必死の告白を一言で切り捨てた藤堂が、自分の前に膝をついて、男の性器を舐めたがっている。 それがたまらない。 ブーン、と低い音がして、背後で冷蔵庫が気まぐれのように作動し始める。 がたん、と階下で誰かがジュースを買う。 二人は動きを止めたまま、照明も点けないキッチンで、息だけをどんどん荒げていく。犬のようにハァハアと呼吸しながら、その瞬間を待っている。 「ああ、藤堂……」 加納は舌先で何度も唇を舐めながら、他に何か話題はないかと視線を宙にさまよわせた。 さらに引き延ばして快感を高めようとする、自分の卑しさにも目眩がする。 「藤堂、藤堂……」 見下ろすと、燃えるような目で自分の男がこちらを見上げていた。 陥落の時がくる。 許しを出すのは自分だが、征服するのは彼。 「藤堂、舐めて――」 お預けを与えていたはずの主人の方に、すぐにご褒美が与えられる。 セックスのあと、加納は必ずシャワーを浴びる。へろへろになっていても、必ず夜中にいったん目を覚まして風呂場へ行く。 体液でべたべたするのが耐えられないのだ。 当然一緒に寝る藤堂にも同じことを要求するし、シーツも換えさせる。 だがそのおかげで朝はすこぶる気持ちいい。毛布の中で肌はさらさらしている。 うつ伏せに寝ていた加納は、翌朝寒さで目を覚ました。 「なに、今何時……?」 「八時ちょっと過ぎ」 頭の上から藤堂の声が降ってきた。彼はすでに起きてベッドから抜け出していたらしい。 「まだそんなもんか」 枕に顔を埋める。 布団をめくられた裸の上半身に鳥肌が立つ。 「寒いな。何やってんだよ。やめろよ」 「腹すかないか?」 「まだいい。おい、布団」 「俺は食いたい」 勝手にしろよ、と言いかけて、加納は藤堂の言葉の意味に気づき、深くため息をついた。 「あれか……」 「いいか?」 「いいけど……ジャムとかバターは無しな」 付き合い始める前は加納の尻に固執していた藤堂だが、最近彼の興味は背中に移っている。 彼が変っているのはそこを舐めたり触ったりするだけでは――もちろんそれもさんざんされるのだが――満足しないということだ。 最近彼は、加納の背中で食事をするという楽しみを覚えてしまった。 加納の背中を皿代わりにし、そこに食べ物を並べるのである。 そんなことをして何が楽しいのか知らないが、絶妙な肉付きの滑らかな曲線にチーズやピクルスなどを並べると絶景なのだと言う。 始めそれを聞いたとき、何せ告白の仕方が仕方であったから、藤堂の性向にいささか問題があることは気づいていた加納ではあったが、思わず相手の顔をまじまじと見つめてしまった。 だが結局許してしまう自分も問題なのかもしれない。 叩いたり縛られたりとなると話は別だが、背中を貸すくらいまあいいか、という気分になってしまう。 男とアナルセックスまでしておいて、何が正常で何が異常かという問題も今更という気がする。 恋人がやりたがっていて、自分が嫌でないならば、誰に知られるわけではなし、いいと思うのだ。 ただ寝具が汚れるのは嫌だから、これを許すのは藤堂の部屋でのみだ。だからこそ最近藤堂は自分の家に呼びたがるのだが。 すっかり目が覚めてしまった加納は、寒いからヒーターを入れろ、とだけ命じて体の力を抜いた。 「さっき入れた。もうすぐ点く」 藤堂のわずかに嬉しそうな声と、続いてキーっというかすかな金属音がした。 ぎし、とベッドが沈んで、藤堂が自分の横に腰を下ろす気配がする。 次の瞬間、冷たく濡れたものがぺたりと背中に触れて、加納は思わず「ひゃああっ」と悲鳴を上げて体を起こした。 「つっ、つめたっ。おまえ、何のせたんだよっ」 加納の過剰な反応に驚いたらしい藤堂は、目を丸くしてして固まっていた。 「何って……蜜柑」 「ミカン〜?」 見れば、彼の手には、蓋を開けた蜜柑の缶詰が握られている。 シーツの上には、加納が動いたせいで背中から落ちたオレンジ色の欠片が転がっていた。 「ミカンって缶詰のか……。おまえ、べたべたするもんはやめろよ。ジャムとかよせっていうのはそういうことだよ」 「あ、悪い……」 藤堂が情けなさそうな顔をする。普段無表情な相手がそんなふうに眉尻を下げているのを見て、加納は再びため息をついた。 「くそっ……もういいよ。好きにすれば?」 「いいのか?」 「だってもうやっちゃったんだからさ。いいよ。あとでもっかいシャワーするから」 「悪い」 本当に悪いと思ってるのかよ、と加納は口の中で毒づきながら、再びおとなしくうつ伏せになった。 ボッと音がし、部屋の隅でファンヒーターが温風を吹き出し始める。加納は顎の下に枕を敷き、ついでに枕元をさぐってテレピのリモコンを見つけ出した。 スイッチを入れると、ちょうど朝の天気予報が始まっていた。 「うわっ、午後雨だってさ。映画行くとか言ってたけど、どうする?」 「出かけるの、よすか? そういえば、すぐ裏のとこにレンタルビデオ店ができたぞ」 「あ、そう? じゃあなんか借りてくるか」 平和な会話を交わす間も、加納の背中には次々に冷たい蜜柑が置かれていく。 肩甲骨の上から尾骨の辺りまで、縦いくつ、横いくつと綺麗に並べられているようだ。 自分の背中に小さな果物が並べられている様を想像する。角の丸まった三日月のような橙色。別にどうってことはない。色気も素っ気もないはずのそれを柔らかな女の裸に換えてみても、特に感じるところはなかった。こういうところで藤堂と自分の違いを感じる。彼がなぜ自分の尻や背中にそんなに拘るのか、未だにわからない。 ただ、いつものことながらそのくすぐったさと、今朝は特にその濡れたような感触のせいで、妙な気分になりがちだ。うつ伏せているからそうなると困るのは自分であり、加納は必死で他に気を逸らそうとした。 「そういえば、梅原の伝言、俺、伝えたよな」 「うん?」 背中に吐息がかかる。 蜜柑を並べ終わった藤堂は、加納の背中に口を寄せ、素肌の上から濡れて光る果肉を直に食べた。 「来月のゼミの発表、やつとコンビだって?」 「ああ……」 二つ目。 加納の背中に藤堂の柔らかな唇が触れる。 「おまえさ、梅原がぼやいてたぞ。愛想無くてやりにくいってさ。直接電話しろって言ったのに俺に言付けてくるし。おまえに睨まれてるような気までするんだと。気のせいだってフォローしといたけどさ……」 背中のすぐ上で、三つ目を挟んだ藤堂の唇が止まった。 「藤堂……?」 不審に思った加納は頭を横に向けた。 「おまえ、まさか……本当に梅原にガン飛ばしてんじゃないだろうな?」 この場合の沈黙は肯定を意味するように思える。 「なんでだよ。やつ、おまえに何かした? 梅原はあの通りだから調子もいいけど、悪いやつじゃないぜ?」 「……いいから」 「あ? 聞こえねえよ」 「あんたと仲いいだろ? 面白くない」 「はあ?」 加納は思わず体を起こしそうになり、藤堂の手に肩を押さえられた。それでもころころと幾つかの蜜柑がシーツへと落ちる。 落ちたものには興味がないのか、藤堂は顔をしかめてそれらを摘み上げ、ベッドサイドのゴミ箱へと捨てた。 「あの、なあ!」 加納は脱力して枕に顔を埋める。 「梅原は友人! 焼餅焼くのは筋違いだろ? 俺がおまえにコクってきたジムの女の子に嫉妬したりすんのはいいんだよ。だけどおまえが梅原に妬くのは違うだろう!?」 「嫉妬したんだ、昨日」 「ただのたとえ! 別にしてねえよ。それよか梅原の話だろ。やつに当たるのはよせよ。あいつとの付き合いはおまえより長いんだ。サークルだって同じだし。本当のこと言うとおまえより趣味合うしな。的外れな焼餅焼いて余計な真似したらただじゃおかないからな!」 背後からは返事はなかった。 少なくとも口に出しては。 むっとした藤堂は言葉の代わりに、手に持ったままだった蜜柑の缶を、加納の体の上でゆっくりと傾けたのだった。 背中から尻、下肢まで冷たいシロップでべたべたになった加納が怒り狂ったのは当然である。 藤堂は彼がシャワーを浴びている間にシーツと毛布を剥がして、あとでコインランドリーに持っていくために床に丸めた。あちこちに転がった蜜柑の果肉も拾い集めた。 だが、熱いシャワーでも恋人の機嫌は直らず、結局その日のデートはおしゃかになった。 あとに残ったのは、ベッドから風呂場に続く絨毯の染みと、藤堂の顎の青あざ。 後者については、その数日後ゼミの打ち合わせのために会った梅原の目にもつくほどだったが、いつもに増して不機嫌な様子の藤堂に、どうしたのかと尋ねることもできなかったと言う。それは正解だろう。 【終】
|
| 1 / NOVEL / HOME |