| 1 / NOVEL / HOME |
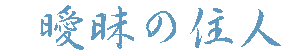 「だから、悪かったって言ってるだろう?」 俺は掛け布団を剥いだ布団の上であぐらをかき、必要以上に卑屈に聞こえないよう、だが十分下手に出ていると相手にもわかるように呼びかけた。 開け放した障子の向こうに、白い月が見える。きりりと遠い暗紺の空が完全な円にはわずかに足りない形に切り取られている。くりぬかれた破片の方はこの庭に落ちて、今は池の水面でゆらゆらと揺れている。 時折ぴしゃりと魚が跳ねる音がして、原型をとどめないほどにくしゃくしゃに壊される光の円が、静けさが戻るごとに再びその形を取り戻す――その不思議な遊戯の繰り返しを、先ほどから飽きずに眺める銀色の目があった。 ひょっとしたら彼の興味をひいているのは鯉の方かもしれないが、それならそれでかまわない。 たとえ一尾何十万、何百万のサカナだろうと、そんなもので彼の機嫌が直るならいくらでも悪戯してくれてかまわなかった。 まあ、そんなわかりやすい真似をこいつがするはずがないが。 「千耶(ちや)。なあ。なあ」 我ながらよくやるよ、というくらい甘ったるい声を出す。 「いい加減、機嫌なおしてくれよ。もう十日だぜ。こっち来いって。抱っこしてやるから、な。いい気持ちにさせてやるから」 本当は気持ちよくなりたいのは自分だけど、別に嘘は言っちゃいない。もし相手が折れてくれるなら、とりあえずはひたすら奉仕にまわってもいい。そのくらいの反省はしている。実際こんなに長く彼に触れないのは初めてのことで、俺は千耶の肌の匂いが恋しくて気が狂いそうだった。 「アレなら、同じやつが手に入ったって津久見から連絡入ったから。そしたら今度はもちろん、まるまるおまえの好きにしてかまわないから」 そう言ったとたん、縁側にうずくまっていた影の一部がぴくりとするのを俺は見逃さなかった。 よし、もう一歩だ、と見えないところでぐっとこぶしを握り締め、俺はできるだけ無邪気そうに見える笑みを浮かべてみせた。 「さっ、こっちおいで。ほら、そんなところ寒いだろ。一緒に寝ようぜ。あー、もちろん、おまえが嫌ならなんもしないから。な」 ぽんぽん、と空いた布団の上を手で叩いて示す。 実際俺の方こそ風邪を引きそうである。春先とはいえ、真夜中に雨戸を開け放し、寝巻き一枚で月を愛でる趣味もない。 「おーい、千耶……」 黒い影は振り向こうともしなかった。 「くそっ」 頑なな相手の態度に舌打ちする。今日こそは最後まで辛抱強く機嫌をとろうと誓っていた決心が、もろくも崩れ始める。根気がないのは自覚している己の短所だ。 だいたいなあ、確かに奴があの酒を楽しみにしていたのを知っていて飲んじまったのは俺が悪かったよ。だけど貰ったのは俺だったんだし、珍しく訪ねて来た友人にそれを振舞ったとて、それほど責められることなんだろうか。 いや、千耶が完全に機嫌を損ねたのはその晩のことであったから、やっぱり体で誤魔化そうとした姑息なやり方が怒りを買ったのか……。 「ちーや、千耶、千耶」 面倒くさくなって、猫にするように彼の名を呼ぶ。そうされるのを何より嫌うと知っていながら。 案の定、銀色の目がきらり、とこちらを向いた。 「う……」 空の月と水の月、二つの光源で庭は不思議と明るい。室内は照明を落としてあるはずなのに、吊り上った二つの大きな目がこちらを睨むさまはよく見えた。 「ち、千耶……」 心なしか後ずさった自分の前で、細い足がすっくと立ち上がる。 「千耶ちゃん?」 音をたてない優雅な動作で、とん、と縁側から下りる。 わずかにかけた望みも虚しく、今晩も恋人は庭先へと消えた。 しんと冷えた夜気に微かにただよう梅の香の中、長い尻尾をくるりと揺らしながら……。 遠い昔、まだ世の中が混沌としていた頃、人とそうでないものの棲み分けもまた曖昧だった。神、精霊、化け物――呼ばれ方、扱われ方は様々であったが、一日に昼と夜があるように、光を灯せば自然に影もできることを、人間たちはその身で知っていた。 だが時代が下るにつれ、昼の時間が夜のそれを、光が影をしのぎ始め、人ならぬものの居場所はだんだんと制限されるようになった。人間たちとそうでないものたちは、無用な争いを避け、またそれぞれの身を守るために境界として一本の川を引いた。 そしてそこに五本の橋がかけられた。 この国がまだ外の世界から閉ざされていた頃、人とあやかしの一部はこの橋を使ってそれぞれの領域を自由に行き来したと言う。 やがて一の橋は朽ち、二の橋は壊され、四の橋は呑まれた。今や聖なる川は誰の目に触れることもなく、地中深くその流れを移し、残された二本の橋も巧妙にその存在を隠された。橋のこちら側に残ったあやかしたちは、今や人工的な光の満ち満ちたこの人間界で、ある者は人と交わり、ある者は身を潜めて暮らしている。 俺の名は三ツ橋了介(みつはしりょうすけ)、二十六歳。先祖代々の財産と人よりちょっとばかし恵まれたこの容姿を利用すれば、もっと享楽的な人生を送れそうなものだが、この体に流れる血によって、職業は生涯橋番と決められている。 翌日、日が高くなってもまだ未練たらしく惰眠をむさぼっていた俺は、ジーッジーッという耳障りな玄関ブザーの音で目を覚ました。 「……なんだよ、うるせぇな。坂本は……あ、そうか、先週から敬一連れてばばあんとこ行ってんだっけ」 不承不承起き出して、寝ぼけまなこで台所を覗いてみたが、通いの家政婦は買い物にでも行っているらしかった。 「ちっ、誰もいねぇのか」 もちろん千耶の姿もなく、テーブルの上にはラップがかけられた朝食が一人分、寂しく置かれている。 その間も遠慮ないブザー音は瀕死のセミみたいにうるさく鳴いており、俺はしかたなく寝巻き姿のまま玄関へと向かった。 「うっせえっつーの。黒猫やらペリカンやらだったら毛ェむしって羽もいで吊るすぞ――」 裸足でたたきへ下りてねじ式の鍵を外すと、「了介!」という声と共に、待ちきれないように引き戸が外からがらりと開き、小柄な影が飛びついてきた。 「――なんだ、おまえらか」 寝起きで不機嫌な顔にますます皺を寄せる。 「ご挨拶だねぇ」 へらっと返したのは道夫。その横に彼に負けないほど長身のスズ子、そして俺にすがりついているのがワタルで、三人とも遊びで知り合った悪友たちだ。 「なんだよ、こんな早くから」 「もう昼近いじゃない。相変わらずごろごろして、いい身分ねぇ」 スズ子は呆れたように鼻を鳴らすと、「あがるわよ」と言って、かってに俺の横を通り抜けると、サンダルを脱ぎ捨てた。 「おいっ、何の用だよ。おまえらこんな時間から、仕事はどうしたよ。学校は?」 「別に、ただ遊びに来ただけだよ。それに今日は土曜。あいかわらず了ちゃんは曜日感覚がないのな」 色付き眼鏡をかけた道夫は律儀にスズ子のサンダルを並べ直すと、自分も勝手知ったように屋敷にあがりこんだ。 「遊びにって、うちにか?」 俺は玄関先でワタルに抱きつかれたまま、眉をひそめた。 確かにちょっと前までは、ほとんど毎晩こいつらとつるんで夜のクルーズにくりだしていたし、家に押しかけられたのが初めてとは言わないが、おてんとう様のあるうちに顔を合わせるのは珍しいのだ。 「ねえ」 呼ばれて視線を下ろすと、頭一つ以上低いところから、ワタルがじっと見上げてくる。 「ねえ、あいつ、出てったって、ほんと?」 その美少年ぶりで男も女もたらしてきた繊細な顔が甘ったるい表情を作る。 未だにくらりとしかける自分に気づいて、ひそかに苦笑いする。自分の売りどころを知っている人間というのは、決して嫌いではないのだ。どちらかというと好み。この柔らかい体に溺れそうになったこともある。 「あいつって、誰だよ」 さりげなく腕をほどいて奥へと促す。 「誰って……」 離されて瞳を揺らしたワタルが、悔しそうに下唇を噛んだ。 ワタルは千耶を徹底的に毛嫌いしている。その第一の理由が俺にあることは決してうぬぼれではないだろうが、千耶の態度にも問題がある。 ちやほやされることが当たり前のワタルを、千耶は小うるさい幼稚園児か何かのように扱うのだ。もしくはまるで視野に入らないかのように。 二人は全く違ったタイプの違う美形だが、純粋に容姿の点から言えば女性的な可愛らしさのあるワタルに軍配が上がるだろう。経験も豊富で他人を操る手管にも長けている。だがそうして優位に立とうとするワタルを千耶は鼻にもかけない。 たぶん本当に関心がないんだろうとは、さすがの俺にも言えなかった。 「あ、あいつ、先週全然学校に来てないって聞いた」 「……」 なんの因果か、二人は同じ大学の学生だ。学年から言うと、千耶の方が下。 「なあ、別れたの?」 「別れてねえって」 薄暗い廊下を、振り向きもせず大股に進む俺の後ろを、ワタルが懸命についてくる。 「だって、今だっていないじゃん、あいつ……」 「……ちょっと出かけてんだよ」 「ねえ、もし了介が――」 「あっ、スズ子、勝手に人の朝飯食うなよ!」 台所に足を踏みいれた俺は、我が物顔でくつろいでいる二人を見つけて目を吊り上げた。 「いーじゃない。どうせ食べないんでしょ。あら、これおいしいわ。なんの果物?」 「了ちゃん、ビールどこ?」 「てめえらなぁ!」 「まあま、喚いてないで座りなさいって。千耶ちゃんにふられたって聞いて、慰めに来てあげたんだから」 「ふられてないっつーの! まったくどいつもこいつも……」 「あら、ほんと?」 カットフルーツ入りヨーグルトをせっせと口へ運ぶスズ子の隣の椅子を引いて、俺はぐったりと座りこんだ。 その隣に首尾良く缶ビールを見つけた道夫が腰を下ろす。ワタルは迷った挙句、椅子の背に手をかけて、俺の後ろに立った。 「なんだ、ガセかあ。とうとう了介に愛想つかせて出てったって聞いたけど」 「縁起でもねぇこと言うな」 ぶすっと答えると、スズ子はきゃらきゃらと笑った。 「はっはっ、その言いぐさ、相変わらずベタ惚れなのね。可哀相なワタルちゃん」 これ以上この場にいない千耶のことを話題にしたくなくて、俺は「本当に何の用だよ」と道夫の飲みかけのビールを奪って訊いた。 「つれないわねぇ。用がなきゃ来ちゃいけないの? 最近全然遊びにも出て来ないしさ。どうしてるかな、と思って」 「夜遊びすると坂本がうるせえんだよ」 「まったまた。坂本さんのお小言なんて今日や昨日始まったことじゃないでしょ。そんなの平気で聞き流してたくせに。来週末、ヒューイでバーテンのタカちゃんの送別会あんのよ。田舎帰るんだってさ。ねえ、千耶ちゃん連れて、いらっしゃいよ。綺麗なかっこさせて来てよ」 「……」 スズ子が千耶のファンだと言うのは知っている。千耶も珍しく彼女には懐いているようだ。面白くはないが、友人の少ない千耶のためだと思って黙認しているのだ。 「……わかったよ。長居はしないけどな」 「オッケー。タカちゃんも喜ぶよ。アンタ本当に不義理してるんだから」 俺にビールを奪われた道夫は文句を言うわけでもなく、首を伸ばして屋敷の奥を伺うような素振りを見せた。 「なあ、敬ちゃんは? 今日も学校か?」 「いや、坂本と一緒に別宅に行ってる。なんでだ? あいつに用?」 「うん、あの子が欲しがってたフィギュアが手に入ったんでね。じゃ、了ちゃんから渡しといてよ」 そう言って、ビニールに入った小さな玩具のようなものを俺の前に置いた。 「レアなんだよ、それ」 そう言ってさも嬉しそうにふふふ、と笑う。 「あいつ、こんなもんに興味あるのか?」 ちゃちな作りのプラスティックに、敬一のおよそ子供らしくない、小利口そうな顔を思い浮かべて首をひねった。 「あらあら、子供の興味の対象も知らないなんて、薄情なパパねぇ」 意地悪なスズ子の言葉に同意を示すような笑みを向け、道夫は「庭見せてな」と席を立った。 すかさずワタルがそのあとに座り、俺の腕を握り締めてくる。 「おい……」 「了介、ねえ、これから出かけない? 車もう一台出してさ、ドライブ」 「めんどくせぇよ」 「運転なら、俺がするから……」 「いや、違った、人が来んだよ。だから駄目」 「了介……」 その震えるような声に、俺はぎょっとしてビール缶から唇を離してワタルを見た。 「うわ、おまえ、泣――」 「なんでそんなに冷たくすんの? 俺、俺、あいつのことはもう言わないからさ。たまに会ってくれたっていいだろ? 俺、本気で――」 異国の血が入っているという噂の、大きな茶色い瞳が、懸命にこちらを見つめてくる。まばたきすまいと精一杯開かれたそこに湛えられた涙を見て、俺はさすがにちょっとほだされた。多分半分は演技が入っているんだろうけど、一方的に手を離したのはこちらだという自覚があるからつれなくもできない。 ちなみに、横目で伺うと、スズ子はさも愉快そうにこちらを眺めている。 「ワタル、悪かったよ。けど、もうおまえとは付き合えないんだ、わかるだろ? 俺は千耶と暮らしてんだし……」 「だから、それはいいって言ってるじゃないか。なんなら、そっち本命でいいから……」 「ワタル、そんなこと言うな。おまえらしくない」 思わず顎に手をかけると、ワタルは目を閉じて顔を近づけてきた。俺は黙って受けてやった。 本命だろうと遊びだろうと、もう千耶以外とは抱き合えないんだよ。俺が誰かに操を立てるなんてこと、想像もつかないんだろうけどな。 さすがに舌が唇を割って入ろうとするのは押しとどめ、顔を離した俺はスズ子の方を向いた。 「悪いけど、こいつ連れて帰ってくれよ。午後に本当に人が来るんだ」 「あら、マジで客だったの? いいけど、タダで?」 俺が困っているのを楽しむように、スズ子は派手なネイルアートを施した指を顔の前で組んだ。 「わかったよ。蝶子んとこで何でも好きなもの買え」 「やった! こないだインポートのドレスのいいやつが入ってたの〜。さすがにちょっと手が出なかったんだけど」 「ああ。店にはこっちに請求まわすように言っとくから」 現金なスズ子は大喜びで立ちあがると、ぐすぐすと鼻を鳴らしているワタルの手を引いて立ちあがらせた。 「ちょっと、道夫、道夫どこ? 買い物に行くわよお」 俺は寝巻きの袖でワタルの目元を拭ってやった。 「スズ子、こいつにも何か見立ててやってくれよ。あそこ確かメンズも入ってたよな」 「りょーかい。おーい、道夫ったら! 運転手! 早くおいで!」 うるさく呼ばれて戻ってきた道夫は、「あれ」と辺りを見まわした。 「どうした」 「いや、チヤちゃん、来なかった?」 「えっ、千耶? いたのか?」 俺が思わず腰を浮かせると、道夫は「違う違う」と首を横に振った。 「チャーちゃんだよ、猫の。さっき見かけて、こっちに来たと思ったんだけどな」 なんだ、と肩を落とす。 「ああ、そう言えばいたわねぇ、黒い子でしょ。でもなんでチャーなんて名前なの? 茶色いってわけでもないのに。千耶ちゃんとまぎらわしいでしょ」 まぎらわしいもなにも、それは千耶本人だよ、とは言えないのだった。 千耶の一族は主に信州の片田舎に暮らしている。彼らはヒトと猫の形態を行ったり来たりする。 厳密に言えば、それは猫ではないらしい。実際千耶がその姿で外をうろついても、普通の猫は寄りつきもしない。 だが人間から見ればそれは間違いなく、少々尾の長い猫だ。 今、俺の目の前で、千耶はその長い尻尾を男の首に這わせていた。 ははは、くすぐったいな、なんて何も知らない男が笑うたび、俺の腹は嫉妬で煮えくりかえりそうになる。 絶対、わざとだ。 男の膝の上でこちらを見上げている銀色の瞳をにらみつける。 「はい、これが頼まれもの。けっこう苦労したんですよ」 男――津久見は、重そうな細長い風呂敷包みを座卓の上に乗せた。 「ああ、わざわざ悪かったな。助かったよ」 「滅多に外には出さないらしくて、どうやって東京の三ツ橋さんが知ったんだ、って不思議がってましたよ」 「人にもらったんだよ」 津久見はへえ、と言って風呂敷を解いた。 現れた一升瓶に、千耶の小さな口が開いて赤い舌が覗く。 こいつは見かけによらず、本当に飲兵衛なんだ。気に入りの酒を人に飲まれて、十日も俺におあずけを食らわすほど。 だがそれも今日で終わりのはずだ。 千耶の機嫌を取るために必死で調べまわった挙句、津久見の田舎にその小さな蔵元があると知った俺は、無理を言って融通をつけてくれるよう、彼に頼んだのだ。 本当は千耶絡みのことは津久見には頼みたくなかったのだけど。 津久見は――雑誌の編集者で、この目の前に座っている無害そうな大男は、かつて千耶が好きだった男だ。そして津久見も満更ではなかったはずだ。 結局は芽生えることすらなかった恋だが。 常識の固まりのような津久見には、自分が男に惹かれるということすら認められなかった。まして、ヒトではない千耶の存在など、理解の範疇を超えていた。 俺は頼まれて、津久見から千耶の記憶を抜いた。それが俺たちが知り合ったきっかけだ。人とあやかし間の秩序を守る橋番として、俺にはその権限と能力があるから。 今、津久見には、千耶は知り合いの俺の同居人という認識しかない。千耶は津久見の何もかもを覚えているが、津久見は違う。 そのことを考えると、こうして津久見の膝に抱かれている千耶の気持ちが切なくなる。 まあ、見方を変えれば、こんなふうに俺への嫌がらせに使えるってことは、すでに千耶にはこだわりがないとも考えられるんだが。 うん、やっぱりこれはわざとだ。 そうだろう、千耶。 俺が苛々するのを見て楽しんでいやがる。 「津久見さん、重いだろ。毛も付くし。チャー、こっちへおいで」 引きつった笑顔を浮かべて俺は手を伸ばしたが、千耶はふいっと横を向いた。 こ、こいつ……。 「あ、大丈夫ですよ。俺、猫好きですし。それにチャーちゃんは本当に手触りがいいですよね。こうして撫でると気持ちいい」 妙にエロくさいことを言われて、俺はどっかん、ときた。 「チャー! こっち来い!」 千耶は津久見の膝の上でちょっとためらっていたが、俺の表情を見て、ゆっくりと下りてこちらへやってきた。 俺は待ちきれずに抱き上げて、あぐらの中へ彼を抱えこむ。津久見の言葉通り、千耶の毛並みは本当に滑らかで、久しぶりに触れた彼の感触に、苛々や不安がすうっと消えていくのを感じた。 千耶、俺の千耶。 柔らかな首や腹をやさしく撫で擦る。見上げてきた銀色の目が思いもかけず気持ちよさそうで、俺はすっかり嬉しくなった。 じゃれるように千耶が俺の指を舐めてくる。そのざらざらした愛撫に、思わず股間が熱くなった。 気づいた千耶が、服の上からぎゅっとそこに爪をたて、咎めるように柔らかく指に歯を立ててきた。 くそっ、このまま――。 あ、駄目か。ちくしょう、津久見の奴、もう用は済んだんだから、早く帰れよ。 充血した股間を抱えて、自分勝手なことを考える。 「そういえば、今日は珍しく誰もいないんですね。ほら、いつもそばにいらっしゃる――」 「坂本? あれは息子連れて別宅の方へ行ってるんだ」 「あ、そうですか、敬一君とね。へえ。それで、えー、あの、千耶さんは……?」 「さあ、出かけてるみたいだな」 俺はにっこりと微笑んでやった。 もう腹は立たない。嫉妬もない。とりあえず今はな。千耶は俺の膝にいるんだし。 何度忘れても性懲りもなく千耶を気にせずにはいられないこいつを、可哀相だと思うだけ。何一つできやしないくせに。惚れていることすら認められないくせに。 「あ、はあ、あ、あ、了介……!」 俺の頭をぐっと太腿で締め上げ、千耶はのけぞりながら吐精した。 後ろをいじっていた指を入れたまま止め、痙攣する内部を感じながら、口内に溢れてきたものをためらわず飲み干す。さらに先を吸い出すように綺麗に始末してやると、「ウン…!」というかわいい声が上がった。 誘われるように股間から体を起こして千耶の顔を覗きこむと、愛しそうに指で口の端を拭われた。 「ば、か……まずいだろ」 「うまいよ。おまえも飲むか?」 「いいよ、了介のなら……」 「マジか? けど、後でな」 目元が赤く染まっているのは酒のせいばかりではあるまい。きれいな千耶。軽く吊り上った瞳、小さくはないが薄い唇。小作りな顔を縁取る、無造作にカットされた柔らかな黒髪。普段はよそよそく人をよせつけない雰囲気をまとっているのに、俺の腕の中ではこんなにもあけすけだ。 千耶の機嫌がこれほどいいのも珍しく、かわいくおねだりされて俺はすっかり舞い上がった。 「まずはこっちな。おまえ、どれだけおあずけ食らわせたと思ってんだよ。死にそうだよ、もう俺は」 「しんじゃえば……アッ!」 笑いながら小憎らしいことを言った口は、増やした指の衝撃で悲鳴をあげた。 平べったい腹部にキスを落としながら、自分自身を入れるために、俺は千耶の中を広げていく。急ぐまいとは思うものの、股間の高ぶりと連動して指の動きも激しくなる。 「あ、あ、あ! ね、もう、了介、もう…!」 「もう? まだキツイだろ、久しぶりだし」 「いいから、もう!」 千耶は堪えきれないように、長い足で俺の肩を蹴ってきた。行儀の悪いやつ。 そこまで急かされれば俺だって我慢する必要はない。 慣れた仕草で大きく開かれた脚の間へ、俺はゆっくりと体を沈めていった。 「アア……」 時間をかけてすっかり埋めて、二人でため息をつく。 汗びっしょりになって見下ろすと、すぐ下に潤んだ瞳があった。 愛しさで体中が熱くなる。こんな気持ちは他の誰にももったことはない。 その黒い瞳は、色こそ違うものの、膝の上から俺を見上げていた銀色のものと、まったく同じだった。 どうしてそれがわからないんだろう。 可哀相な人間。 ヒトとそうでないもの。境界線など、自分たちが勝手に引いただけで、本当はどこにもありやしないのに。 柔らかくまきつき、時に受けとめ、時に引き止める千耶の内部を思う存分味わいながら、俺は曖昧である自分の存在に感謝せずにはいられなかった。 俺は橋守だ。こちらとあちらをつなぐ橋。どちらでもない中間地点。 動きを止めて舌を差し出すと、下から千耶がむしゃぶりついてくる。俺の唾液を嬉しそうに飲み、軽く腰を揺らして続きをせがんでくる。 見かけや常識にがんじがらめになって、貴重なものをそれとも知らず手放している、可哀相なやつら。 「了介、来て、もっとやって!」 シーツを乱し、汗を飛ばして俺を煽る、白い体。 けれど、それが黒い毛皮に包まれていたって、俺は同じように興奮する。小さいからさすがにつっこむことはできないけれど、俺は千耶が望むなら、猫のときでも同じように愛し合うことができる。体中を舐めあって、ビロードのような毛並みを白く汚すだろう。 どんな形であろうと俺の劣情を刺激するのはもう千耶だけだ。 津久見。ばかなやつ。この悦びを知らないなんて。そんなに怖かったのか。曖昧な世界を知ることが。人でないものを認めることが。 もっとも俺も十六で敬一の母親に乗っかられたときには、明らかに人外の者に犯される恐怖に玉を縮こまらせていたけどな。 「了介!」 「いてぇっ」 一瞬でも集中力を切らしたこちらを責めるように、千耶は白い歯をたてて俺の肩にかぶりついた。 「おまえっ、マジで噛んだな……おい見ろ、血が出たぞ」 「ワタルにキスして直してもらえば?」 あ…はは、見てたのか。 俺は詫びの意をこめ、派手に音をたてて口付けると、しっかりと膝をついて千耶の下半身を抱えあげた。 「あ、あう…っ」 肩と二の腕に新たな痛みが走る。尖った爪が、赤く長く線を引いていくさまが目に見えるようだ。 もし津久見が孤島に二人きりで千耶と生まれ育ったならば、やつもためらわずこいつと愛し合えただろう。稀有な恋人を手に入れて、幸せに暮らしたかもしれない。 ――もちろん、そんなチャンスを俺が黙ってやるはずはないけどな。 肩の上で千耶の足が跳ねあがる。 濡れて揺れる性器を握りしめ、湿った襞の中へ激しく腰を突き入れると、千耶は黒髪を振り乱して泣きじゃくった。 「あーっ、いい、了介っ、いく、もう、いくよ、ああ…っ!」 いけよ。俺を連れて、どこへでも。そんなことができるのは、おまえだけだ。 歯を食いしばって目を閉じる。痙攣する体を無理やり押えこんで、思い知らせるように、二度、三度と大きく突き上げた。 「いくッ、落ちる、アア……!」 ぎゅううっと千耶が俺を締め上げる。ぎりぎりまで堪えていたものが、千耶に引かれて飛んでいく。 「千、耶、」 うめいて、自分に許した。 何かの証しを注ぎこみながら、俺は彼方まで千耶に攫われた。 ――もし津久見とおまえがどこかの島に暮らしていても、俺が橋をかけて乗り込んでいくからな。 囁くと、千耶は涙で濡れた瞳を不思議そうに瞬かせた。 それから数日間、千耶はもらった純米大吟醸をだいじに飲み、たいそうご満悦だった。俺も相伴に預かりたかったが、以前貰った分をしこたま飲んでいたので今回は我慢した。さすがに幻の酒というだけあって、口当たりは爽やかなのに深いコクがあるのだ。 坂本と敬一はまだ帰ってこない。電話で道夫に玩具をもらったことを言うと、小学生の息子は珍しくはしゃいだ声をあげていた。うーむ、やっぱり俺は父親失格か? 今度そのおまけ付きの菓子とやらを買ってみるか? ブティックを経営している蝶子が、スズ子のドレスの請求書をまわしてきた。ちなみにワタルに合うものはなかったとかで、代りにヒューイに電話を入れて、彼の名前でボトルを入れるように言った。 ヒューイと言えば明日誰かの送別会があるとか言っていたな。千耶に言うのを忘れていたけれど……。 そう言えば、また今朝から千耶の姿が見えない。どうやらまたも一人きりらしい屋敷で、リンリンと電話のベルが鳴り響いた。 しかたなく自分で出ると、近所の魚屋からだった。ここは小さいが、たまに極上のものを仕入れてくるので、その際は連絡するように頼んである。 鯛と平目のいいのが手に入ったとかで、暇を持て余していた俺は、散歩がてら覗きにいくことにした。 「千耶! おーい、千耶、いないのか! サカナ買いに行くぞ! おまえの好きな刺身にするぞ!」 千耶は飲み助だが、食い道楽でもある。 返事がないので仕方なく一人で玄関を出ると、どこからか黒い影が飛びついてきて、軽やかに俺の肩の上におさまった。 「お? またその格好か? おまえちゃんと学校行ってるのか?」 返事の代わりに、長い尻尾がするりとシャツの胸元にすべりこんできた。 千耶の一族は、幼いときほど人と猫型との変化が激しく、成長すると自分で制御できるようになるが、老いるとどちらかに形態が固定されるという。ちなみに寿命はほぼ人間と同じだ。 俺は鼻歌を歌いながら、薄手のブルゾンのポケットに両手を突っ込んで、早春の陽気にどこか浮かれた地元商店街へとくりだした。 肩の上に黒い猫を乗っけた俺に、顔見知りが慣れたように声をかけてくる。 「鯛にするか?」 魚屋の店先で、独り言のように呟くと、千耶が長い尻尾をゆらゆらと振った。 「んじゃ、平目?」 黒い尾がタンタン、と肩を叩いてくる。 「なに? 両方? しかたねぇな。ああ、そのトロも貰っとこうかな。あと甘エビも。それと……」 満足気に尻尾が頭を撫でてくる。 千耶は年をとったらどうなるのだろう。 二人、共白髪で――いや、千耶みたいに細くて柔らかい髪をしてるやつは禿げるのかもしれないが――のんびりと縁側で茶でも啜りながら梅の香を楽しむのも、もしくは老いた猫と一緒に池の鯉をからかうってのも悪くない。どっちみちその頃にはもう俺は橋番の役目を敬一か、その子供に譲り渡しているはずだ。 魚屋のおやじが手際良く包丁を操って、刺身用にこしらえてくれるのを待ちながら、俺は何となく目を閉じた。 頬には滑らかな毛皮の感触、肩には程よい重み、人の時よりもわずかに強い獣の体臭。春の陽は人間にも俺にも千耶にも等しく降り注ぎ、ゆっくりと体を温めていく。 人型の千耶。猫の千耶。どちらを思い描いても、それはひどく幸福な光景のように思えた。 【終】 |
| 1 / NOVEL / HOME |
|
《後書きという名のいいわけ》 実はこれ、書かなかったお話の後日談なのです…。 本文中にも説明があったように、千耶の津久見への思いは報われないまま終わってしまうので、可哀相だからこのあと了介とくっつくってことにしよう、でもってベタベタに甘やかしてあげよう、と考えていたら、なんだかそっちの方が気に入ってしまって……。 意味もなく色々な設定がくっついているのはだからです。読みづらくてすみませんでした。 ちなみに本編の方はもう書くつもりはないです。ネタバレしちゃったし、ハッピーエンドではないですから。 |